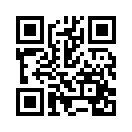2010年03月02日
鶴齢との出会い
どうして丸河屋さんには鶴齢があるの? とよく聞かれます。
このところ、毎日のようになりました。
そこで鶴齢の青木さんと私との出会いを書いてみます。
知人から言われていました。
「お酒も旨いし、人もいいんだけど、売れていない蔵元があるんだけど」
「丸ちゃん、会ってみない?」
私はどこですかと聞きました。
「新潟なんだけどさあ、鶴齢って言うんだよ」
「青木君(現社長)はいい奴でさあ」
「俺、絶対いいと思うんだけど」
「丸ちゃんところでやってもらえないかしん」
私は新潟という不安。
鶴齢という知らない蔵元への不安。
確かにこれらの不安もありましたが、
鶴齢をすすめてくれているこの方に関しては、
絶対的な信頼がありました。
この方とは20年以上、酒業界で歩んできています。
この方が会う場面を用意してくれて、ご対面しました。
同時にお酒も味見しました。
第一印象は、日本人離れした顔つきだなあ。
お酒のことよりも、青木さんの雰囲気の印象が強かったです。
私は西洋風な顔立ちを感じていましたが、
後なって、このことを打ち明けますと、
実は中東の人って言われることもあるんですよ、
とのことでした。
どちらにしても印象に残ることは大事ですね。
彼のお酒の説明から感じたことは、
製造は製造部門に任し、営業は営業をし、
事務は事務に徹している会社なんだなあ。
=個人営業蔵ではない
=社長が杜氏ではない
=会社としての何かの転換期をむかえている
そして、蔵元によくある東京農業大学卒ではないのではとも思いました。
見かけ以外の最大の印象は、青木さんの器は大きいのではと感じました。
蔵元は昔ながらの名家であり、当主は世襲であり、酒造免許も新規は下りない、
というふうな、酒業界にはある特定の決まりきった空間があります。
いろんな方と蔵元さんとお話するときには、この狭い空間を感じます。
地酒専門店と称される方々にも、同様に狭い空間を感じます。
(だからは私は地酒専門店という言葉を使うのには抵抗がありますし、
外見上は地酒専門店には見えないようなお店にしてあります。
今後も地酒専門店というくくりの中には、入らないように、
入れられないように努力しています。)
ところが、青木さんにはこの空間を感じません。
相手が地酒専門店かどうかといった、私へのかんぐりもかんじませんでした。
すなわち、丸河屋酒店と青木酒造を結ぼうとした方を信頼している。
これはうまくいくお見合いのようにも感じました。
これが出会いの場面であり、それがいつだったのか?
もう昔のことですから、おぼえてはいません。
このところ、毎日のようになりました。
そこで鶴齢の青木さんと私との出会いを書いてみます。
知人から言われていました。
「お酒も旨いし、人もいいんだけど、売れていない蔵元があるんだけど」
「丸ちゃん、会ってみない?」
私はどこですかと聞きました。
「新潟なんだけどさあ、鶴齢って言うんだよ」
「青木君(現社長)はいい奴でさあ」
「俺、絶対いいと思うんだけど」
「丸ちゃんところでやってもらえないかしん」
私は新潟という不安。
鶴齢という知らない蔵元への不安。
確かにこれらの不安もありましたが、
鶴齢をすすめてくれているこの方に関しては、
絶対的な信頼がありました。
この方とは20年以上、酒業界で歩んできています。
この方が会う場面を用意してくれて、ご対面しました。
同時にお酒も味見しました。
第一印象は、日本人離れした顔つきだなあ。
お酒のことよりも、青木さんの雰囲気の印象が強かったです。
私は西洋風な顔立ちを感じていましたが、
後なって、このことを打ち明けますと、
実は中東の人って言われることもあるんですよ、
とのことでした。
どちらにしても印象に残ることは大事ですね。
彼のお酒の説明から感じたことは、
製造は製造部門に任し、営業は営業をし、
事務は事務に徹している会社なんだなあ。
=個人営業蔵ではない
=社長が杜氏ではない
=会社としての何かの転換期をむかえている
そして、蔵元によくある東京農業大学卒ではないのではとも思いました。
見かけ以外の最大の印象は、青木さんの器は大きいのではと感じました。
蔵元は昔ながらの名家であり、当主は世襲であり、酒造免許も新規は下りない、
というふうな、酒業界にはある特定の決まりきった空間があります。
いろんな方と蔵元さんとお話するときには、この狭い空間を感じます。
地酒専門店と称される方々にも、同様に狭い空間を感じます。
(だからは私は地酒専門店という言葉を使うのには抵抗がありますし、
外見上は地酒専門店には見えないようなお店にしてあります。
今後も地酒専門店というくくりの中には、入らないように、
入れられないように努力しています。)
ところが、青木さんにはこの空間を感じません。
相手が地酒専門店かどうかといった、私へのかんぐりもかんじませんでした。
すなわち、丸河屋酒店と青木酒造を結ぼうとした方を信頼している。
これはうまくいくお見合いのようにも感じました。
これが出会いの場面であり、それがいつだったのか?
もう昔のことですから、おぼえてはいません。
日本酒の辛いとは?酒ライブで検証。
日本酒きき酒テクニック「日本酒の表現方法1.雪解け水のような 」
正雪で年間を通じて一番売れている純米吟醸
正雪から今年も「純米吟醸 嗜」が発売されます。
丸河屋酒店内で酒屋de酒ライブ2を行いました。
初夏の静岡酒その5.正雪
日本酒きき酒テクニック「日本酒の表現方法1.雪解け水のような 」
正雪で年間を通じて一番売れている純米吟醸
正雪から今年も「純米吟醸 嗜」が発売されます。
丸河屋酒店内で酒屋de酒ライブ2を行いました。
初夏の静岡酒その5.正雪
Posted by 丸河屋酒店 at 14:30│Comments(0)
│日本酒