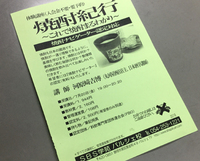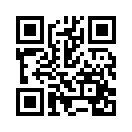2011年04月04日
静岡酒、この名役者、この名演技 5. 新しい潮流
しずおか地酒研究会の鈴木真弓さんのWEB酒場静岡吟醸伝に寄稿しています。
「静岡酒、この名役者、この名演技」の第5章です。
昭和の終りから平成の初期にかけて、各種の鑑評会で猛威を振るった静岡酵母。
それがどういうことでしょうか、平成の5年くらいから以前のような成績が取れません。
決して酒質が落ちているわけでもないのに。
むしろ酒質は上がっているとさえ思えました。
これぞっと世に出した新しい酵母を使った大吟醸。
それが予想通りの成績になりません。
しかも、静岡県内の業界人には好評なのに。
成績のよい静岡へのひがみなのでしょうか。
そんな何かの力が働いている気すらしました。
では、静岡酒よりも成績優秀なお酒はどんなタイプなのか?
全国新酒鑑評会で金賞受賞したお酒を利けばわかります。
・
・
・
それはこれまでの静岡酵母のお酒よりも香り高いお酒でありました。
確かに明治の終期から開催されてきた全国新酒鑑評会は香りの
高さを求める面もあり、それは磨かれたお米から造る吟醸酒が
出品されるからであります。
熊本酵母が一世風靡し、全国に普及されたのも香りの高さからであります。
静岡酵母もこれまでの酵母の香りの壁を打破したことにより、
優秀な成績をおさめることとなったわけであります。
もっと振り返りますと、昭和の時代、熊本酵母が誕生してからというもの、
ずっとこの酵母を使ったお酒が全国新酒鑑評会で成績がよく天下を取っていました。
そこへより優れたと感じさせる静岡酵母が参入し、”ここに静岡あり”
と言わせるくらいのお酒が誕生したわけです。
多方面から見れば、静岡酵母から造ったお酒を上回る酒質を目指します。
お酒の世界も技術進歩は日進月歩。
静岡酵母からよりも、香りの高いお酒を造れる酵母の開発が進んでいました。
周りを見渡せば、長野にアルプス酵母があり、秋田に花酵母、京都に月桂冠酵母、
石川に金沢酵母などなどと、静岡の成功を見習い、各県や各国税局単位での
酵母開発が行われていました。
中でも全国区に広がったのが、金沢酵母であります。
酵母の生産量が多いことも全国への広がりのひとつ。
金沢酵母で造ったお酒はこれまでにないタイプの香りを放ちました。
赤い果実を感じさせる強烈ともいえるくらいの高さです。
全国新酒鑑評会においても金賞受賞率は他の酵母を圧倒していました。
これが清酒なの? と首をかしげるくらいの強さのものもありました。
静岡県内の蔵元すら金沢酵母で出品するケースも目立ったくらいです。
全国的に大きな目で見れば、時代は熊本酵母から金沢酵母へと移ったのです。
(静岡酵母も熊本系です。)
まさに「新しい潮流」が生まれました。
この「新しい潮流」は静岡に悩みをもたらしました。
しかもその悩みは10年では拭い去れないほどでありました。
ほんと、文字だけでは計り知れないくらいの苦難の時代です。
次回はこの「静岡酒、苦難の時代」を書こうと思います。
「静岡酒、この名役者、この名演技」の第5章です。
昭和の終りから平成の初期にかけて、各種の鑑評会で猛威を振るった静岡酵母。
それがどういうことでしょうか、平成の5年くらいから以前のような成績が取れません。
決して酒質が落ちているわけでもないのに。
むしろ酒質は上がっているとさえ思えました。
これぞっと世に出した新しい酵母を使った大吟醸。
それが予想通りの成績になりません。
しかも、静岡県内の業界人には好評なのに。
成績のよい静岡へのひがみなのでしょうか。
そんな何かの力が働いている気すらしました。
では、静岡酒よりも成績優秀なお酒はどんなタイプなのか?
全国新酒鑑評会で金賞受賞したお酒を利けばわかります。
・
・
・
それはこれまでの静岡酵母のお酒よりも香り高いお酒でありました。
確かに明治の終期から開催されてきた全国新酒鑑評会は香りの
高さを求める面もあり、それは磨かれたお米から造る吟醸酒が
出品されるからであります。
熊本酵母が一世風靡し、全国に普及されたのも香りの高さからであります。
静岡酵母もこれまでの酵母の香りの壁を打破したことにより、
優秀な成績をおさめることとなったわけであります。
もっと振り返りますと、昭和の時代、熊本酵母が誕生してからというもの、
ずっとこの酵母を使ったお酒が全国新酒鑑評会で成績がよく天下を取っていました。
そこへより優れたと感じさせる静岡酵母が参入し、”ここに静岡あり”
と言わせるくらいのお酒が誕生したわけです。
多方面から見れば、静岡酵母から造ったお酒を上回る酒質を目指します。
お酒の世界も技術進歩は日進月歩。
静岡酵母からよりも、香りの高いお酒を造れる酵母の開発が進んでいました。
周りを見渡せば、長野にアルプス酵母があり、秋田に花酵母、京都に月桂冠酵母、
石川に金沢酵母などなどと、静岡の成功を見習い、各県や各国税局単位での
酵母開発が行われていました。
中でも全国区に広がったのが、金沢酵母であります。
酵母の生産量が多いことも全国への広がりのひとつ。
金沢酵母で造ったお酒はこれまでにないタイプの香りを放ちました。
赤い果実を感じさせる強烈ともいえるくらいの高さです。
全国新酒鑑評会においても金賞受賞率は他の酵母を圧倒していました。
これが清酒なの? と首をかしげるくらいの強さのものもありました。
静岡県内の蔵元すら金沢酵母で出品するケースも目立ったくらいです。
全国的に大きな目で見れば、時代は熊本酵母から金沢酵母へと移ったのです。
(静岡酵母も熊本系です。)
まさに「新しい潮流」が生まれました。
この「新しい潮流」は静岡に悩みをもたらしました。
しかもその悩みは10年では拭い去れないほどでありました。
ほんと、文字だけでは計り知れないくらいの苦難の時代です。
次回はこの「静岡酒、苦難の時代」を書こうと思います。
タグ :しずおか地酒研究会
日本酒きき酒テクニック「日本酒の表現方法1.雪解け水のような 」
丸河屋酒店で「酒屋de酒Live3」をやりました。
丸河屋酒店内で酒屋de酒ライブ2を行いました。
焼酎ナビゲーター取得講座開講だよ!
東海大学短期大学部「フードサイエンス」にて講演
フードサイエンス開講迫る!
丸河屋酒店で「酒屋de酒Live3」をやりました。
丸河屋酒店内で酒屋de酒ライブ2を行いました。
焼酎ナビゲーター取得講座開講だよ!
東海大学短期大学部「フードサイエンス」にて講演
フードサイエンス開講迫る!
Posted by 丸河屋酒店 at 20:30│Comments(0)
│講演・講座・執筆