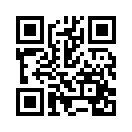2008年11月13日
相性研究の方法
お見合いをすればするほど、人を見る目が肥えてきて、なかなか相手が決まらない。これも一人だけを選ぶからでしょう。会えば会うほど、人を見る実力もついてくるのは事実かもしれません。
お酒とお料理の相性もやればやるほどわかってきます。そもそも無意識にお酒もお料理も楽しんでいるわけで、そんなのやる必要がないとおっしゃる輩もいるでしょうが、上の人間同士だって同じ。お見合いしなくても、毎日誰かには会っています。
お酒とお料理の相性を探る方法として、比較対照物が適量あった方がいいです。
ですから、よくある「このお料理にはこのお酒があいました」では、理由も明確ではないし、本来の相性研究からはほど遠い学術性の低いものです。
つまり、
1.1本のお酒に対して、いくつかのお料理をあわせる。
2.逆に1つのお料理に対して、いくつかのお酒をあわせる。
こういうことが飲食の領域を超えた研究でしょう。
この2つの内では、1.が一般的であります。1.はお酒の本数が1本ですから安上がりで、お料理共々その日に消費できます。2.はお酒の本数が必要でお金がかかり、お料理は消費できても、お酒は飲みきれません。
これをすることによって、どうしてあうのか?
どうしてあわないのか?
がはっきりしてきます。
私は酒販店という立場上、ひとつのおつまみに何本ものお酒類を用意することができます。自慢しているわけではなく、酒販店の義務でもあるのかと思います。
これは蔵元でもできないです、多種多数を揃える酒販店だからこそできる芸当。
先生方がおっしゃる「流通業者こそよくわかっている」とのことであります。
蔵元の造ったお酒にさらに付加価値をつけて、飲み手をより幸せな道に導き出す。
一生懸命な酒販店はみなさん勉強していますよ。目立ちませんがね。

このように晩酌ではなく、真剣にお酒とお料理に向かい合っています。

ノートにデータをびっしり書き込んでいます。
お酒とお料理の相性もやればやるほどわかってきます。そもそも無意識にお酒もお料理も楽しんでいるわけで、そんなのやる必要がないとおっしゃる輩もいるでしょうが、上の人間同士だって同じ。お見合いしなくても、毎日誰かには会っています。
お酒とお料理の相性を探る方法として、比較対照物が適量あった方がいいです。
ですから、よくある「このお料理にはこのお酒があいました」では、理由も明確ではないし、本来の相性研究からはほど遠い学術性の低いものです。
つまり、
1.1本のお酒に対して、いくつかのお料理をあわせる。
2.逆に1つのお料理に対して、いくつかのお酒をあわせる。
こういうことが飲食の領域を超えた研究でしょう。
この2つの内では、1.が一般的であります。1.はお酒の本数が1本ですから安上がりで、お料理共々その日に消費できます。2.はお酒の本数が必要でお金がかかり、お料理は消費できても、お酒は飲みきれません。
これをすることによって、どうしてあうのか?
どうしてあわないのか?
がはっきりしてきます。
私は酒販店という立場上、ひとつのおつまみに何本ものお酒類を用意することができます。自慢しているわけではなく、酒販店の義務でもあるのかと思います。
これは蔵元でもできないです、多種多数を揃える酒販店だからこそできる芸当。
先生方がおっしゃる「流通業者こそよくわかっている」とのことであります。
蔵元の造ったお酒にさらに付加価値をつけて、飲み手をより幸せな道に導き出す。
一生懸命な酒販店はみなさん勉強していますよ。目立ちませんがね。
このように晩酌ではなく、真剣にお酒とお料理に向かい合っています。
ノートにデータをびっしり書き込んでいます。
Posted by 丸河屋酒店 at 06:35│Comments(0)
│お酒とお料理の相性研究