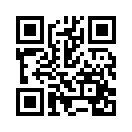2009年05月08日
酒販店の裏事情
時刻は午後の 時
時
 分になりました。
分になりました。
冒頭ではございますが、丸河屋酒店にも飲食店さんのお客さんがいます。
たくさんではありませんが、経営上の主力であります。
そして、どこのお店とも仲良く協力しあいながら、
いい関係を築いています。
今日は酒販店にしかわからいない事情をお話します。
みなさんが飲食店で飲んだ瓶はその後どうなるのか?
その後は配達している酒屋さんが担当となります。
飲食店は一軒の酒屋さんだけで取っていることもほぼなくなりました。
経営に携わっていれば別ですが、そうでなければどこで買っても自由。
丸河屋酒店としても、自店の守備範囲内できっちり仕事をさせてもらっています。
ワインはどこどこで買おう。
ビールはこれまで通りにどこどこで。
生ビールは安い酒屋が見つかったからどこどこで。
有名な地酒はそれを売っている店で。
どこで何を仕入れても、お客さんに飲んでもらえば、必ず空がでます。
その空瓶を持っていってもらうのは誰に頼むか?
本来は持ってきたお店に返すべきであります。
ところが、お客様に売れた時と酒屋への注文・仕入のタイミングがいっしょではないために、
もともと持ってきた酒屋に頼むのではなく、来る頻度が高い酒屋にお願いすることになります。
それらの空き瓶はビールの箱に入っているので、ビールを持ってくる酒屋にとなります。
ビールは配達の頻度も高いですし。
私のように配達して空瓶も回収するお店は次のようになっています。
・瓶ビールは問屋からメーカーへと戻されます。
・ワインや清酒の瓶はリサイクルに持ち込みます。
有料です。
今日も¥7,560払いました。

リサイクル業者が取ってくれない瓶は、別の業者に持ち込み、
1キロあたり数十円払って引き取ってもらいます。
・清酒の瓶は地酒メーカーに渡します。
この時、非常に申し訳なくなります。
磯自慢、八海山などの全国区の有名銘柄を扱っている酒屋さんは、
空瓶の回収をしないので、私が引き上げてきてあげて、地酒メーカーに渡します。
この地酒メーカーとしては、自社の瓶よりも、有名銘柄も瓶が目に付くことでしょう。
瓶はいっしょですから、地酒メーカーは自社製品を詰めて売れます。
酒販店は片付け屋さんのようで、情けないのであります。
売るよりも引き取る本数の方が多いので、地酒メーカーに空箱を持ってきてもらっています。

余分な仕事が増えるわけです。
このようなことは丸河屋酒店だけに起こっていることではありません。
家族経営の街の酒屋さんは、みな同じであります。
で、酒販店同士は愚痴を言いあっているか?
そういうこともままありますが、たいていは、かわいいお客さんのために、
何にも思わないよと、なっています。
有名ブランドを集めて、格好いい商売がいいのか、
縁の下の力持ちな商売がいいのかってことですね。
格好いい商売は、縁の下の力持ちによって支えられていると思うのですが。
それからお互い様ってこともありますし。
 時
時
 分になりました。
分になりました。冒頭ではございますが、丸河屋酒店にも飲食店さんのお客さんがいます。
たくさんではありませんが、経営上の主力であります。
そして、どこのお店とも仲良く協力しあいながら、
いい関係を築いています。
今日は酒販店にしかわからいない事情をお話します。
みなさんが飲食店で飲んだ瓶はその後どうなるのか?
その後は配達している酒屋さんが担当となります。
飲食店は一軒の酒屋さんだけで取っていることもほぼなくなりました。
経営に携わっていれば別ですが、そうでなければどこで買っても自由。
丸河屋酒店としても、自店の守備範囲内できっちり仕事をさせてもらっています。
ワインはどこどこで買おう。
ビールはこれまで通りにどこどこで。
生ビールは安い酒屋が見つかったからどこどこで。
有名な地酒はそれを売っている店で。
どこで何を仕入れても、お客さんに飲んでもらえば、必ず空がでます。
その空瓶を持っていってもらうのは誰に頼むか?
本来は持ってきたお店に返すべきであります。
ところが、お客様に売れた時と酒屋への注文・仕入のタイミングがいっしょではないために、
もともと持ってきた酒屋に頼むのではなく、来る頻度が高い酒屋にお願いすることになります。
それらの空き瓶はビールの箱に入っているので、ビールを持ってくる酒屋にとなります。
ビールは配達の頻度も高いですし。
私のように配達して空瓶も回収するお店は次のようになっています。
・瓶ビールは問屋からメーカーへと戻されます。
・ワインや清酒の瓶はリサイクルに持ち込みます。
有料です。
今日も¥7,560払いました。
リサイクル業者が取ってくれない瓶は、別の業者に持ち込み、
1キロあたり数十円払って引き取ってもらいます。
・清酒の瓶は地酒メーカーに渡します。
この時、非常に申し訳なくなります。
磯自慢、八海山などの全国区の有名銘柄を扱っている酒屋さんは、
空瓶の回収をしないので、私が引き上げてきてあげて、地酒メーカーに渡します。
この地酒メーカーとしては、自社の瓶よりも、有名銘柄も瓶が目に付くことでしょう。
瓶はいっしょですから、地酒メーカーは自社製品を詰めて売れます。
酒販店は片付け屋さんのようで、情けないのであります。
売るよりも引き取る本数の方が多いので、地酒メーカーに空箱を持ってきてもらっています。
余分な仕事が増えるわけです。
このようなことは丸河屋酒店だけに起こっていることではありません。
家族経営の街の酒屋さんは、みな同じであります。
で、酒販店同士は愚痴を言いあっているか?
そういうこともままありますが、たいていは、かわいいお客さんのために、
何にも思わないよと、なっています。
有名ブランドを集めて、格好いい商売がいいのか、
縁の下の力持ちな商売がいいのかってことですね。
格好いい商売は、縁の下の力持ちによって支えられていると思うのですが。
それからお互い様ってこともありますし。
タグ :丸河屋酒店
2009年04月18日
ローソン 発注制限
丸河屋酒店の私でもコンビニには行くときがあります。
食べ物を買ったり、コピーしたり。
さすがにお酒は買いには行きませんが。
今日はお昼前にちょっとお腹に入れよう。
昼食までに何か食べないともたない、と思ったからです。
フライドチキン「Lチキ」が売切中でした。
聞くところによれば、各店舗からの発注数量の制限があるとのこと。
若干安くしたら、若年層の購買が予想以上に上がってしまった。
発注制限はゴールデンウィークまで続きそうらしいです。
1店舗当たり1日の平均販売数は60個。
各店舗からの発注制限数は50個まで。
これじゃあ、私が買いに行ったときになくても仕方ない。
ローソンLチキは中国とタイで加工され、船で輸入されているようです。
在庫がなくなってきたので、空輸もしているらしいです。
明日またLチキがあるかどうか、ローソンに行ってみます。
安くなったから売れ出した、というのが本当なのか?
美味しさが浸透してきたから、売れ出してきたのか?
消費者の目で見てみます。
食べ物を買ったり、コピーしたり。
さすがにお酒は買いには行きませんが。
今日はお昼前にちょっとお腹に入れよう。
昼食までに何か食べないともたない、と思ったからです。
フライドチキン「Lチキ」が売切中でした。
聞くところによれば、各店舗からの発注数量の制限があるとのこと。
若干安くしたら、若年層の購買が予想以上に上がってしまった。
発注制限はゴールデンウィークまで続きそうらしいです。
1店舗当たり1日の平均販売数は60個。
各店舗からの発注制限数は50個まで。
これじゃあ、私が買いに行ったときになくても仕方ない。
ローソンLチキは中国とタイで加工され、船で輸入されているようです。
在庫がなくなってきたので、空輸もしているらしいです。
明日またLチキがあるかどうか、ローソンに行ってみます。
安くなったから売れ出した、というのが本当なのか?
美味しさが浸透してきたから、売れ出してきたのか?
消費者の目で見てみます。
2009年03月29日
卸の小売店切り
酒販店、街のお酒屋さんであります。
バタバタとやめていくお店が後を絶ちません。
やめてなくても、実質その地域には影響していないお店がほとんど。
これが現実です。
これまでは、お客さんが来なくなったので、売り上げが減り、店をしまう。
このケースが一番多かったです。
この頃はお客さんだけでなく、仕入先からもお断りを食うことも多くなってきました。
卸である問屋の小売店切りです。
食品流通では2大卸があります。
全国区です。
これらが個店を相手にしている現状が異常なのかもしれませんが、
そもそも地場の卸を合併吸収してきたので、個人店とのつながりがあります。
丸河屋酒店は2つの内の1つとはお付き合いがあります。
2008年までは、土曜日も配送はしてくれたのですが、
2009年からは平日だけになりました。
丸河屋酒店の近所の酒屋さんからも、取引をやめたよと言う店も出てきました。
どうしてなのか?
他の酒販店からの話だと、毎月の売り上げが○十万円いかない店は
だんだんと切っていくようだとの話です。
平日配送から曜日指定配送に変えられてしまうそうです。
月水金など。
このようにされてしまうと、注文する方が不便になります。
結果、注文が益々少なくなります。
毎月○十万円あったのが、毎月○万円以内になってしまいます。
そうすると、配送する卸屋さんも割に合わなくなります。
したがって、申し訳ないですが、お取引は・・・になるわけです。
地場の小さな問屋さんだけでもビールは揃えられますが、
その他の品物となると不自由です。
それでも来てくれていた、数少ないお客さんにも対応できなくなり、
ついに店しまいになるのです。
時代の流れで仕方ないのでしょうが、大きな店だけが残る。
それで日本もいいのでしょうか?
資本主義ですけど、配給制のような世の中に見えて仕方ありません。
バタバタとやめていくお店が後を絶ちません。
やめてなくても、実質その地域には影響していないお店がほとんど。
これが現実です。
これまでは、お客さんが来なくなったので、売り上げが減り、店をしまう。
このケースが一番多かったです。
この頃はお客さんだけでなく、仕入先からもお断りを食うことも多くなってきました。
卸である問屋の小売店切りです。
食品流通では2大卸があります。
全国区です。
これらが個店を相手にしている現状が異常なのかもしれませんが、
そもそも地場の卸を合併吸収してきたので、個人店とのつながりがあります。
丸河屋酒店は2つの内の1つとはお付き合いがあります。
2008年までは、土曜日も配送はしてくれたのですが、
2009年からは平日だけになりました。
丸河屋酒店の近所の酒屋さんからも、取引をやめたよと言う店も出てきました。
どうしてなのか?
他の酒販店からの話だと、毎月の売り上げが○十万円いかない店は
だんだんと切っていくようだとの話です。
平日配送から曜日指定配送に変えられてしまうそうです。
月水金など。
このようにされてしまうと、注文する方が不便になります。
結果、注文が益々少なくなります。
毎月○十万円あったのが、毎月○万円以内になってしまいます。
そうすると、配送する卸屋さんも割に合わなくなります。
したがって、申し訳ないですが、お取引は・・・になるわけです。
地場の小さな問屋さんだけでもビールは揃えられますが、
その他の品物となると不自由です。
それでも来てくれていた、数少ないお客さんにも対応できなくなり、
ついに店しまいになるのです。
時代の流れで仕方ないのでしょうが、大きな店だけが残る。
それで日本もいいのでしょうか?
資本主義ですけど、配給制のような世の中に見えて仕方ありません。
タグ :丸河屋酒店
2009年03月24日
キリンビールの不気味さ
日本の大手ビール4社はシェアや出荷数を非常に気にしています。
食うか食われるか。
コンビ二の冷蔵庫の陳列棚の確保。
スーパーや量販店での売り場スペース確保。
飲食店での生ビールや瓶ビールの取り扱い確保。
営業マンは必死であります。
毎晩のように、飲食店などへは顔を出して挨拶まわり。
私もずいぶんいっしょに連れてってもらって、
営業の方々の努力振りはよく知っています。
営業マンの努力は消費者からは直接見れませんから、
ある意味水面下での戦いになっていると言えましょう。
水面下ではないところ。
それは広告であります。
テレビやラジオのコマーシャルであります。
これらの宣伝費も大手企業ですから、それなりに大きいです。
毎日テレビからビール会社の宣伝を見ない日はないくらい。
タレントさんもいろいろ使っていますから、銘柄名は思い出せなくても、
ああ、あのコマーシャルねって、思い出させることでしょう。
キリンビールののどごし生はぐっさんがやっていますね。
サッポロビールは田村正和。
発泡酒や新ジャンルが目白押しの影で、ビールも新商品が出ています。
キリンの一番搾りが麦芽100%のモルツになったことをご存知でしょうか?
これって大きな話題になってもよさそう。
話題にするのはビール会社でありますが。
みなさんご存知ない方が多いと思います。
だって、テレビのコマーシャルも見たことないし。
それに一番搾りの見かけ上は、ほとんど変化ありませんから、
飲んでいても見過ごしてしまうほどです。
どうして、キリンビールは一番搾りが麦芽100%になったと宣伝しないのでしょうか?
これはキリンビールの戦略であります。
宣伝費がないのではありません。
こんなに不気味な戦略はこれまでありませんでした。
キリンビールの狙いを推定すると。
1.消費者には麦芽100%と知らせずに飲んでもらう。
↓
2.味は濃くなっているが、気がつきにくい。
↓
3.消費者の嗜好が辛口ですっきり系からコクのある方向へと向かう。
↓
サントリービールはモルツプレミアムモルツに力を入れていて、
サッポロビールはエビスビールを数種類出すくらいにモルツ系に力を入れています。
↓
4.全体的にスーパードライ離れを無意識に起こす。
アサヒビールが5月に発売する新商品ザ・マスターを先回りして
待ち構えることもできるわけです。
ザ・マスターは麦芽100%のモルツ系。
2009年のビールはモルツ系が主役であることは、
これらから間違いないでしょう。
宣伝をして、認知させて、売り込み、出荷量が多いと広告を打つ。
従来がこのようでありましたが、キリンビールは思い切った逆の戦略を選んだのでしょうか。
ビール会社からの情報は溢れるくらいです。
知らなくてもいいことも知らされている広告。
キリンビールは知らせないことで、モルツ系の世界を変えるのでしょうか。
あなたのビールの嗜好。
知らないうちに変わってくることかもしれませんね。
キリンビールのこの静かさ。
不気味であります。
明日か明後日は、実際に旧一番搾りと新一番搾りを飲み比べして、
ご報告をいたしましょう。
丸河屋酒店には、現在新旧の一番搾りがありますから。
食うか食われるか。
コンビ二の冷蔵庫の陳列棚の確保。
スーパーや量販店での売り場スペース確保。
飲食店での生ビールや瓶ビールの取り扱い確保。
営業マンは必死であります。
毎晩のように、飲食店などへは顔を出して挨拶まわり。
私もずいぶんいっしょに連れてってもらって、
営業の方々の努力振りはよく知っています。
営業マンの努力は消費者からは直接見れませんから、
ある意味水面下での戦いになっていると言えましょう。
水面下ではないところ。
それは広告であります。
テレビやラジオのコマーシャルであります。
これらの宣伝費も大手企業ですから、それなりに大きいです。
毎日テレビからビール会社の宣伝を見ない日はないくらい。
タレントさんもいろいろ使っていますから、銘柄名は思い出せなくても、
ああ、あのコマーシャルねって、思い出させることでしょう。
キリンビールののどごし生はぐっさんがやっていますね。
サッポロビールは田村正和。
発泡酒や新ジャンルが目白押しの影で、ビールも新商品が出ています。
キリンの一番搾りが麦芽100%のモルツになったことをご存知でしょうか?
これって大きな話題になってもよさそう。
話題にするのはビール会社でありますが。
みなさんご存知ない方が多いと思います。
だって、テレビのコマーシャルも見たことないし。
それに一番搾りの見かけ上は、ほとんど変化ありませんから、
飲んでいても見過ごしてしまうほどです。
どうして、キリンビールは一番搾りが麦芽100%になったと宣伝しないのでしょうか?
これはキリンビールの戦略であります。
宣伝費がないのではありません。
こんなに不気味な戦略はこれまでありませんでした。
キリンビールの狙いを推定すると。
1.消費者には麦芽100%と知らせずに飲んでもらう。
↓
2.味は濃くなっているが、気がつきにくい。
↓
3.消費者の嗜好が辛口ですっきり系からコクのある方向へと向かう。
↓
サントリービールはモルツプレミアムモルツに力を入れていて、
サッポロビールはエビスビールを数種類出すくらいにモルツ系に力を入れています。
↓
4.全体的にスーパードライ離れを無意識に起こす。
アサヒビールが5月に発売する新商品ザ・マスターを先回りして
待ち構えることもできるわけです。
ザ・マスターは麦芽100%のモルツ系。
2009年のビールはモルツ系が主役であることは、
これらから間違いないでしょう。
宣伝をして、認知させて、売り込み、出荷量が多いと広告を打つ。
従来がこのようでありましたが、キリンビールは思い切った逆の戦略を選んだのでしょうか。
ビール会社からの情報は溢れるくらいです。
知らなくてもいいことも知らされている広告。
キリンビールは知らせないことで、モルツ系の世界を変えるのでしょうか。
あなたのビールの嗜好。
知らないうちに変わってくることかもしれませんね。
キリンビールのこの静かさ。
不気味であります。
明日か明後日は、実際に旧一番搾りと新一番搾りを飲み比べして、
ご報告をいたしましょう。
丸河屋酒店には、現在新旧の一番搾りがありますから。
2009年03月23日
アサヒビールの戦略
このブログの業界裏話のカテゴリーにサントリーの凄さを書きました。
私の独断と偏見に基づいています。
今回はアサヒビールについて書いてみます。
アサヒビールの隠れざる戦略であります。
アサヒのスーパードライが単一商品としてキリンラガーを抜き、
ビール全体としての売り上げもキリンを抜きました。
ドライに目をつけたアサヒの凄さです。
スーパードライの立役者はアサヒビール関係から、幾人も出ています。
私の目からすれば、何と言っても村井・樋口コンビであります。
私が20代の時に、村井さんから話を聞いたことがあります。
村井さんはすでにお亡くなりになられていますから、
貴重な話でした。
村井勉さんはマツダのファミリアをヒットさせてアサヒに移動してきました。
住友銀行の副頭取もしていた、住友グループの核の一人でした。
アサヒビールのあとは、初代JR西日本の社長につきました。
アサヒスーパードライはビールでは、今でもシェアNO.1であります。
スーパードライが発売された頃は発泡酒のようなのはありませんでした。
節税がテーマで発泡酒は研究され、
今では機能性ビール系飲料の位置を確立しつつあります。
第三のビールも登場しました。
新ジャンルと呼ばれるようになりました。
先週のニュースにこういったことがありました。
業界ニュースとして、発泡酒や新ジャンルの出荷数を公表しない。
公表できなくなった。
公表しないメーカーが出てきたからです。
第3のビールには税法上の分類で、次の二つがあります。
・麦芽を使わない「その他醸造酒」
・麦芽を使う「リキュール」
第3のビールの総合計では、キリンがトップ。
アサヒは2位であります。
これが数年続いているために、業界では、
ビールのアサヒ、発泡酒のキリンのイメージが定着しています。
アサヒビールとしてみると、第3のビールの総合1位を取るよりも、
2つある分野のどちらか1つで1位を取る方が楽です。
アサヒのクリアアサヒが、2つの内の1つである、
麦芽を使う「リキュール」の部においてトップを取りました。
ちなみに、もう一方の麦芽を使わない「その他醸造酒」の1位は
キリンののどごし生であります。
アサヒビールはクリアアサヒがある部門によって1位を取ったことにより、
堂々と第3のビールでも1位と宣伝したわけであります。
キリンとしては黙ってはおらず、出荷量を公表しない手に打って出ました。
これにより、アサヒの1位の広告は使えなくなりました。
新ジャンルで2つの1位があるのも誤解を与えますから、
業界としても公表しなくなりました。
さて、これよりどう動くのか?
アサヒビールの戦略は何なのか?
ここに凄さがあります。
大きな宣伝費を使えるビール大手。
アサヒの戦略の1つは量。
アイテム数であります。
発泡酒や第3のビールはビールとは違って、まだまだ研究の余地があり、
いろんな新商品が出されることでしょう。
そして、消費者がビールとの認識がない、この分野に何を求めているのか?
美味しさなのか?
機能性なのか?
安さなのか?
見えてきません。
そこでアイテム数の量に打って出ています。
量より質である。・・・・・そうですよね。
でも質は量によって改善される。
天才と呼ばれているプレーヤーに共通しているのは、量的時間です。
1万時間。
天才と称されるプレーヤーに共通する時間。
これまで1万時間をかけて、ここに至っているらしいです。
1日6時間以上の練習を意味しています。
天才のイメージからは、離れていますが、量があっての記録です。
アサヒの量。
1万アイテムはありません。
キリンビールは8アイテム。
淡麗、淡麗グリーン、淡麗W、淡麗ZERO、円熟、のどごし、
スパークリングホップ、セブン
サッポロビールは5アイテム。
生搾り、ドラフトONE、麦とホップ、スリムス、冷製SAPPORO
サントリービールは6アイテム。
MD、ダイエット、ジョッキ生、金麦、スーパーブルー、ストレート
そしてアサヒビールは12アイテム。
スタイルフリー、クールドラフト、本生、本生アクアブルー、
ジンジャードラフト、贅沢日和、クリアアサヒ、アサヒオフ、
あじわい、極旨、ぐびなま、新生3
これらは生まれては消え、また新たに生まれていく。
技術者、研究者もたいへんというか、やりがいがありますね。
ちなみにビールのアイテムは次です。
キリンビール4アイテム。
ラガー、クラシック、一番搾り、一番搾りスタウト
サッポロビールは6アイテム。
黒ラベル、エビス、エビスホップ、エビスブラック、エビスシルク、エビス長熟
サントリービールは3アイテム。
モルツ、プレミアムモルツ、カールスバーグ
アサヒビールは4アイテム+オリオンビール
スーパードライ、熟撰、ザマスター、黒生
アイテム数が多いことは、それだけリスクが多いです。
人気が分散してしまう可能性があるからです。
しかし、アサヒはアイテム数で勝負をしかける。
これらからわかるように、アサヒビールは発泡酒と新ジャンル(第3のビール)
を量的なことから1位を目指しています。
各社全力で戦っています。
まだまだ美味しい新商品が出ると思われますから、
楽しみですね。
丸河屋酒店ではそんなに多くのアイテムをおけず、
選択に悩みそうであります。
私の独断と偏見に基づいています。
今回はアサヒビールについて書いてみます。
アサヒビールの隠れざる戦略であります。
アサヒのスーパードライが単一商品としてキリンラガーを抜き、
ビール全体としての売り上げもキリンを抜きました。
ドライに目をつけたアサヒの凄さです。
スーパードライの立役者はアサヒビール関係から、幾人も出ています。
私の目からすれば、何と言っても村井・樋口コンビであります。
私が20代の時に、村井さんから話を聞いたことがあります。
村井さんはすでにお亡くなりになられていますから、
貴重な話でした。
村井勉さんはマツダのファミリアをヒットさせてアサヒに移動してきました。
住友銀行の副頭取もしていた、住友グループの核の一人でした。
アサヒビールのあとは、初代JR西日本の社長につきました。
アサヒスーパードライはビールでは、今でもシェアNO.1であります。
スーパードライが発売された頃は発泡酒のようなのはありませんでした。
節税がテーマで発泡酒は研究され、
今では機能性ビール系飲料の位置を確立しつつあります。
第三のビールも登場しました。
新ジャンルと呼ばれるようになりました。
先週のニュースにこういったことがありました。
業界ニュースとして、発泡酒や新ジャンルの出荷数を公表しない。
公表できなくなった。
公表しないメーカーが出てきたからです。
第3のビールには税法上の分類で、次の二つがあります。
・麦芽を使わない「その他醸造酒」
・麦芽を使う「リキュール」
第3のビールの総合計では、キリンがトップ。
アサヒは2位であります。
これが数年続いているために、業界では、
ビールのアサヒ、発泡酒のキリンのイメージが定着しています。
アサヒビールとしてみると、第3のビールの総合1位を取るよりも、
2つある分野のどちらか1つで1位を取る方が楽です。
アサヒのクリアアサヒが、2つの内の1つである、
麦芽を使う「リキュール」の部においてトップを取りました。
ちなみに、もう一方の麦芽を使わない「その他醸造酒」の1位は
キリンののどごし生であります。
アサヒビールはクリアアサヒがある部門によって1位を取ったことにより、
堂々と第3のビールでも1位と宣伝したわけであります。
キリンとしては黙ってはおらず、出荷量を公表しない手に打って出ました。
これにより、アサヒの1位の広告は使えなくなりました。
新ジャンルで2つの1位があるのも誤解を与えますから、
業界としても公表しなくなりました。
さて、これよりどう動くのか?
アサヒビールの戦略は何なのか?
ここに凄さがあります。
大きな宣伝費を使えるビール大手。
アサヒの戦略の1つは量。
アイテム数であります。
発泡酒や第3のビールはビールとは違って、まだまだ研究の余地があり、
いろんな新商品が出されることでしょう。
そして、消費者がビールとの認識がない、この分野に何を求めているのか?
美味しさなのか?
機能性なのか?
安さなのか?
見えてきません。
そこでアイテム数の量に打って出ています。
量より質である。・・・・・そうですよね。
でも質は量によって改善される。
天才と呼ばれているプレーヤーに共通しているのは、量的時間です。
1万時間。
天才と称されるプレーヤーに共通する時間。
これまで1万時間をかけて、ここに至っているらしいです。
1日6時間以上の練習を意味しています。
天才のイメージからは、離れていますが、量があっての記録です。
アサヒの量。
1万アイテムはありません。
キリンビールは8アイテム。
淡麗、淡麗グリーン、淡麗W、淡麗ZERO、円熟、のどごし、
スパークリングホップ、セブン
サッポロビールは5アイテム。
生搾り、ドラフトONE、麦とホップ、スリムス、冷製SAPPORO
サントリービールは6アイテム。
MD、ダイエット、ジョッキ生、金麦、スーパーブルー、ストレート
そしてアサヒビールは12アイテム。
スタイルフリー、クールドラフト、本生、本生アクアブルー、
ジンジャードラフト、贅沢日和、クリアアサヒ、アサヒオフ、
あじわい、極旨、ぐびなま、新生3
これらは生まれては消え、また新たに生まれていく。
技術者、研究者もたいへんというか、やりがいがありますね。
ちなみにビールのアイテムは次です。
キリンビール4アイテム。
ラガー、クラシック、一番搾り、一番搾りスタウト
サッポロビールは6アイテム。
黒ラベル、エビス、エビスホップ、エビスブラック、エビスシルク、エビス長熟
サントリービールは3アイテム。
モルツ、プレミアムモルツ、カールスバーグ
アサヒビールは4アイテム+オリオンビール
スーパードライ、熟撰、ザマスター、黒生
アイテム数が多いことは、それだけリスクが多いです。
人気が分散してしまう可能性があるからです。
しかし、アサヒはアイテム数で勝負をしかける。
これらからわかるように、アサヒビールは発泡酒と新ジャンル(第3のビール)
を量的なことから1位を目指しています。
各社全力で戦っています。
まだまだ美味しい新商品が出ると思われますから、
楽しみですね。
丸河屋酒店ではそんなに多くのアイテムをおけず、
選択に悩みそうであります。
2009年03月21日
サントリーの凄み
サントリーがビール業界NO.3になりました。
4位からの脱出。
はじめてのことだそうです。
私が小学生の頃、サントリーは生ビール、
それも自販機の缶に力を入れていました。
その当時は生ビールはサントリーしかなかったと記憶しています。
今から35年くらい前の話。
当時は瓶ビールが主流でした。
しかしサントリーは自販機がこれからたくさん設置されるのを見込んで、
瓶よりも缶の方が良い品質だとの評判がありました。
今から想像しますと、瓶ビールよりも濾過の回数が少なかったのでしょう。
缶(生ビール含む)は瓶よりも濾過の回数が少ないことは、
10年くらい前までは普通のことでしたが、今は瓶も缶も生ビールもいっしょ。
これはどのメーカーでもであります。(特別品は除く)
キリンビールは生ビールを出さないと豪語していましたが、
アサヒのスーパードライの爆発的ヒット以来、
ラガーも火入れから生になりました。
ビールは瓶から缶へ。
火入れから生へ。
苦味から辛味へ。
このような嗜好からスーパードライが天下を取りました。
サントリーはモルツに力を注ぎ、テレビCMでもモルツオンリー。
和久井映見の宣伝は覚えている人が多いでしょう。
サントリーの純生って知ってますか?
生ビール党には受けていました。
モルツは麦芽100%のビールの呼び名。
日本ではエビスビールとサントリーモルツが双璧。
サントリーモルツは2009年の今年で30年目になると思います。
エビスビールはサッポロが買収し、
恵比寿駅近くにビールガーデンプレイスをオープン。
お値段がちょっぴり高いプレミアムビールとして知名度がアップ。
サントリーモルツはこれまで数回、ラベルデザインを一新しますが、
それほど話題には上りませんでした。
しかし、サントリープレミアムモルツ。
これは誰もが知るビールだと思います。
モンドセレクション最高金賞3年連続受賞。
すっきり辛口の傾向のさかさま。
ドライ主流の中、反対のビールを造っていたのです。
芳醇。
酒業界の中でも、スーパードライの次のヒットは何か?
それがここ20年弱くらい結論が出ていません。
サントリープレミアムモルツはモンドセレクションブームの大きな波に乗れました。
モンドセレクションの金賞や最高金賞を取ってきた酒類は多いですが、
サントリーのように大々的に宣伝したケースはありませんでした。
モンドセレクションが人々に知れ渡り、しかも最高金賞という表現。
注目されないわけがありません。
サントリーの凄さは3年連続最高金賞であることです。
それだけに品質がよろしい。
それもそうかもしれません。
意外にも意外。
誰も話題にすらしていませんが、
実は4年目は出品していないのです。
普通は3年連続を詠うのであれば、4年連続も狙います。
そうしなければ、3年はよかったのに、4年目はダメだったんだと
思われかねません。
サントリーはこういうことも承知していながら、3年で出品はやめたのです。
ここが凄さ。
恐らく、4年目も5年目も最高金賞を受賞することでしょう。
しかし広告的な意味合いはどうか?
3年で大きくPRしました。
4年目、5年目。
時間が経つにつれて、インパクトは薄れます。
美味しさの保証というPRのために仕組んだ作戦。
しかも3年連続で、この目的は達成した。
スパッとモンドセレクションからは足を洗う。
サントリーがモンドセレクションを切ったのです。
できませんよ、この大転換は。
サントリープレミアムモルツは芳醇でありますが、
会社の方針はキレのより辛口でありますね。
いやいやさすがであります。
サントリーはこれまでも歴史に残りそうな宣伝を打ってきました。
「長~く愛して。」
「細~く愛して。」
名文句であります。
サントリープレミアムモルツもこれまでの社風を感じる
凄いイメージの刷り込みを成功さた凄い商品であります。
この勢いに乗り、ハイボールの復活は成せるのでしょうか?
4位からの脱出。
はじめてのことだそうです。
私が小学生の頃、サントリーは生ビール、
それも自販機の缶に力を入れていました。
その当時は生ビールはサントリーしかなかったと記憶しています。
今から35年くらい前の話。
当時は瓶ビールが主流でした。
しかしサントリーは自販機がこれからたくさん設置されるのを見込んで、
瓶よりも缶の方が良い品質だとの評判がありました。
今から想像しますと、瓶ビールよりも濾過の回数が少なかったのでしょう。
缶(生ビール含む)は瓶よりも濾過の回数が少ないことは、
10年くらい前までは普通のことでしたが、今は瓶も缶も生ビールもいっしょ。
これはどのメーカーでもであります。(特別品は除く)
キリンビールは生ビールを出さないと豪語していましたが、
アサヒのスーパードライの爆発的ヒット以来、
ラガーも火入れから生になりました。
ビールは瓶から缶へ。
火入れから生へ。
苦味から辛味へ。
このような嗜好からスーパードライが天下を取りました。
サントリーはモルツに力を注ぎ、テレビCMでもモルツオンリー。
和久井映見の宣伝は覚えている人が多いでしょう。
サントリーの純生って知ってますか?
生ビール党には受けていました。
モルツは麦芽100%のビールの呼び名。
日本ではエビスビールとサントリーモルツが双璧。
サントリーモルツは2009年の今年で30年目になると思います。
エビスビールはサッポロが買収し、
恵比寿駅近くにビールガーデンプレイスをオープン。
お値段がちょっぴり高いプレミアムビールとして知名度がアップ。
サントリーモルツはこれまで数回、ラベルデザインを一新しますが、
それほど話題には上りませんでした。
しかし、サントリープレミアムモルツ。
これは誰もが知るビールだと思います。
モンドセレクション最高金賞3年連続受賞。
すっきり辛口の傾向のさかさま。
ドライ主流の中、反対のビールを造っていたのです。
芳醇。
酒業界の中でも、スーパードライの次のヒットは何か?
それがここ20年弱くらい結論が出ていません。
サントリープレミアムモルツはモンドセレクションブームの大きな波に乗れました。
モンドセレクションの金賞や最高金賞を取ってきた酒類は多いですが、
サントリーのように大々的に宣伝したケースはありませんでした。
モンドセレクションが人々に知れ渡り、しかも最高金賞という表現。
注目されないわけがありません。
サントリーの凄さは3年連続最高金賞であることです。
それだけに品質がよろしい。
それもそうかもしれません。
意外にも意外。
誰も話題にすらしていませんが、
実は4年目は出品していないのです。
普通は3年連続を詠うのであれば、4年連続も狙います。
そうしなければ、3年はよかったのに、4年目はダメだったんだと
思われかねません。
サントリーはこういうことも承知していながら、3年で出品はやめたのです。
ここが凄さ。
恐らく、4年目も5年目も最高金賞を受賞することでしょう。
しかし広告的な意味合いはどうか?
3年で大きくPRしました。
4年目、5年目。
時間が経つにつれて、インパクトは薄れます。
美味しさの保証というPRのために仕組んだ作戦。
しかも3年連続で、この目的は達成した。
スパッとモンドセレクションからは足を洗う。
サントリーがモンドセレクションを切ったのです。
できませんよ、この大転換は。
サントリープレミアムモルツは芳醇でありますが、
会社の方針はキレのより辛口でありますね。
いやいやさすがであります。
サントリーはこれまでも歴史に残りそうな宣伝を打ってきました。
「長~く愛して。」
「細~く愛して。」
名文句であります。
サントリープレミアムモルツもこれまでの社風を感じる
凄いイメージの刷り込みを成功さた凄い商品であります。
この勢いに乗り、ハイボールの復活は成せるのでしょうか?
2009年03月02日
みんな何飲んでるんだろう
若者は酒を飲むという明確な意識を持って、
酒に親しみ入ってきているのではなく、
ジュースの延長線上として缶チュウハイなどへ向く。
それは時代であり、これこれこうやって飲んでほしいなあと
呟いてみたいが、まず現状を認めなければいけない。
では、今のご時世、一体何をどのくらい飲んでいるのか?
お堅い話ですが、総務省統計局がまとめた平成20年、
年間家計調査をざっくり述べます。
数字は二人以上の世帯を対象とした、一世帯の額面であります。
20年 (19年) 20年対19年
酒類支出金額 45,071円 (44,872円) +0.7%
清酒 6,833円 (7,267円) -6%
焼酎 7,400円 (7,162円) +3.3%
ビール 16,652円 (17,218円) -3.3%
発泡酒 6,401円 (5,991円) +6.8%
ワイン 2,323円 (2,414円) -3.8%
ウイスキー 1,143円 (1,220円) -6.3%
他の酒 4,319円 (3,600円) +20%
家庭内だけの晩酌だけの数字もあります。
前年比を比べます。
清酒 -4.4%
焼酎 +1.6%
ビール -3.4%
発泡酒 +4.8%
ワイン +3%
ウイスキー -6.5%
晩酌に対して、外食は164,893円で19年とほとんど変わらず。
飲酒代は17,607円で19年をわずかに上回る。
これを見るなり、以外にもビールは健闘したと思いました。
もっと発泡酒やその他の酒類(第3のビールなど)に持っていかれるのかなあと
思っていましたが、それほどでもなかったです。
上昇率はその他の酒類(第3のビールなど)が圧倒していますから、
ビールは益々減っていくでしょう。
清酒と焼酎は調査開始以来、はじめて清酒を焼酎が抜きました。
これは金額ですから、容量やアルコールのグラム数となりますと、
焼酎はすでに清酒を抜き去っていました。
晩酌でワインが好調。
食卓にはワインが上がることが多いのですね。
ワインは価格も味わいもバラエティーに富んでいます。
選び甲斐がありそうです。
今年はウイスキーがハイボールに力を入れていて、
復活してきそうです。
21年の数字が楽しみです。
丸河屋酒店としては、酒類支出金額が上がっていることが、ほっとする材料です。
今年も同じようなお酒を飲みますか?
それともみんなとは違う我が道を開きますか?
酒に親しみ入ってきているのではなく、
ジュースの延長線上として缶チュウハイなどへ向く。
それは時代であり、これこれこうやって飲んでほしいなあと
呟いてみたいが、まず現状を認めなければいけない。
では、今のご時世、一体何をどのくらい飲んでいるのか?
お堅い話ですが、総務省統計局がまとめた平成20年、
年間家計調査をざっくり述べます。
数字は二人以上の世帯を対象とした、一世帯の額面であります。
20年 (19年) 20年対19年
酒類支出金額 45,071円 (44,872円) +0.7%
清酒 6,833円 (7,267円) -6%
焼酎 7,400円 (7,162円) +3.3%
ビール 16,652円 (17,218円) -3.3%
発泡酒 6,401円 (5,991円) +6.8%
ワイン 2,323円 (2,414円) -3.8%
ウイスキー 1,143円 (1,220円) -6.3%
他の酒 4,319円 (3,600円) +20%
家庭内だけの晩酌だけの数字もあります。
前年比を比べます。
清酒 -4.4%
焼酎 +1.6%
ビール -3.4%
発泡酒 +4.8%
ワイン +3%
ウイスキー -6.5%
晩酌に対して、外食は164,893円で19年とほとんど変わらず。
飲酒代は17,607円で19年をわずかに上回る。
これを見るなり、以外にもビールは健闘したと思いました。
もっと発泡酒やその他の酒類(第3のビールなど)に持っていかれるのかなあと
思っていましたが、それほどでもなかったです。
上昇率はその他の酒類(第3のビールなど)が圧倒していますから、
ビールは益々減っていくでしょう。
清酒と焼酎は調査開始以来、はじめて清酒を焼酎が抜きました。
これは金額ですから、容量やアルコールのグラム数となりますと、
焼酎はすでに清酒を抜き去っていました。
晩酌でワインが好調。
食卓にはワインが上がることが多いのですね。
ワインは価格も味わいもバラエティーに富んでいます。
選び甲斐がありそうです。
今年はウイスキーがハイボールに力を入れていて、
復活してきそうです。
21年の数字が楽しみです。
丸河屋酒店としては、酒類支出金額が上がっていることが、ほっとする材料です。
今年も同じようなお酒を飲みますか?
それともみんなとは違う我が道を開きますか?
タグ :丸河屋酒店
2009年02月27日
醸造アルコールの是非
お客様からも講座の受講者さんからもよく質問をいただきます。
「醸造アルコールって何?」
「醸造アルコールが入っている方がよくないでしょ?」
酒業界内でも醸造アルコールならぬ増量アルコールだと言われる方もいます。
良くも悪くも取られてしまう醸造アルコールについてですから、
表立って公表しづらい点もあります。
日本酒には醸造アルコールが添加されている本醸造系と
入っていない純米系に分かれます。
アルコール添加については江戸時代から柱焼酎の添加として始まっています。
江戸時代には冷蔵設備がなく、アルコール度の小さなお酒は雑菌などに
やられてしまいます。お酒がお酒とは思えない液体に変化してしまいます。
このために江戸時代に伝わり、造れるようになった焼酎(本格焼酎)を
出来た日本酒に混ぜて保存していました。
江戸時代のアルコール添加は腐敗防止剤の役目をする食品添加物でありました。
明治、大正、昭和となるにつれて、世の中のあらゆることが変わってきます。
戦争がありました。
日本も日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦、第二次世界大戦と参戦します。
日清・日露は酒税で戦ったと言われるほどに、酒税が高くなりました。
お酒は当時の日本になくてはならない担税物資となったわけです。
国税の1/3であります。
第二次世界大戦で日本は負けますが、負ける前後の状況はひどいもので、
食べる米すらない状態ですから、お酒にするお米などは明らかに少ない。
国としては、少ないお米からなるべく多くのお酒を造りたい。
そんな折、満州で三倍醸造法が誕生しました。
これは出来上がったお酒にアルコールを入れて、アルコールが高くなった分を
下げるための水を入れます。
水が入った分だけ味が薄くなるので、調味料で補う製法です。
出来たお酒を三倍に増やす三倍醸造であります。
戦争で物資がなかった時代の緊急避難用の酒としてであればしょうがない。
いや、優れものでありました。
ところが、戦後日本は高度成長して、豊かになります。
時代は豊かになりましたが、お酒は三倍醸造が溢れていました。
低価格酒であります。
パック酒に米、米麹、醸造アルコール、糖類、酸味料と書かれているのがあります。
満州で開発された造り方と、そんなには変わっていません。
醸造アルコールの使用量は決められています。
白米1トンあたりの原料に対して、アルコール約120リットルです。
この時のアルコールはアルコール100%の度数として計算されます。
これは出来上がったお酒のアルコール分のおよそ1/4であります。
問題視されている事柄がありますから、議論に上ります。
1.醸造アルコールとは何なのか?
2.醸造アルコールは何のために入れているのか?
ここが壺でしょう。上の答えです。
1.醸造アルコールは、酒造会社によっては、自社製造の焼酎を使っています。
一般的には純度の高い焼酎甲類です。梅酒に使うものと同等です。
醸造アルコールの原料は決められていますが、昭和の50年代くらい前
までは、その正体を配給元のアルコール生産会社が明かしてくれません
でしたから、石油からではないか、ブラジルやフィピリンのサトウキビの
くずからではないかと騒がれました。
ブラジルはバイオエタノールの先進国です。
現在使われている醸造アルコールについては心配ないと思われます。
2.醸造アルコールを入れると出来上がるお酒は多くできます。
かさ上げできるわけです。
増量アルコールと皮肉くる人もいるわけです。
蔵元は醸造的にアルコールを入れて腐敗防止をする方が安全だと言う方もいます。
では、純米酒は安全ではないのか、につながりますね。
江戸時代の柱焼酎添加と同じだと言われる蔵元もいますが、
添加の量が違いすぎます。
柱焼酎の添加量よりも、圧倒的に醸造アルコールの添加量が多いです。
そして、もろみを搾る前に醸造アルコールを添加すると、香りが良くなる。
本来、酒粕に行ってしまう芳香をアルコールによって、抽出できる。
吟醸香が強くなるからとの理由もあります。
醸造アルコールを入れて加水した分、味がすっきりして、辛口になるとの理由も言われます。
同時にその酒質を醸造アルコール抜きでするのが努力ではないかと言う方もいます。
ここで添加の意味合いから、醸造アルコール以外を見てみましょうか。
日本酒のラベル表示は酒税法で決められた基準に沿って明記しなければなりません。
純米酒は米と米麹と書かれていますが、本当にそれだけでできるのでしょうか?
酵母菌や麹菌を使っていることは問題ないでしょう。
では、使用を許されていて、明記の義務がない食品添加物についてはどうですか?
山廃造りやきもとつくり以外のお酒では、乳酸を添加しています。
乳酸はお酒では食品添加物扱いですが、一般的には薬品です。
この他、酵素補助剤も使います。
濾過のために活性炭や濾過助剤に珪藻土を使い、ろ紙にも通します。
こう考えると、醸造アルコールも一つの食品添加物のような存在に思えるでしょう。
醸造アルコールは気にして、その他の乳酸などのことはかまわないとはいかないですね。
私は次のように解釈します。
醸造アルコールを添加した本醸造系=薄口
添加していない純米系=濃い口
の2タイプを造り出している。
これが他の食品類と比較した時に、一番理解しやすい解釈ではないでしょうか?
本醸造系=本醸造、特別本醸造、吟醸、大吟醸 は辛口傾向。
純米系=純米酒、特別純米酒、純米吟醸、純米大吟醸は旨口傾向。
醸造アルコールが添加してあるお酒は体にはよくない?とも聞かれます。
私の知り合いの杜氏は、体のためを想って、純米酒は飲みません。
醸造アルコールを添加してある本醸造系統しか飲みませんという方もいます。
この杜氏さんの体にとっては、純米酒は濃すぎて、胃をやられることもあるそうです。
現状、醸造アルコール添加酒もあるし、醸造アルコールが添加してないお酒もあるし、
味わいがバラエティーに富んでいると楽天的に考えているのがいいのではないでしょうか?
それから、どうしても醸造アルコール添加が許せないとか、醸造アルコールが添加して
あるお酒は飲めないということならば、乳酸添加酒も飲めないですし、黒い炭が漬かった
濾過してあるお酒も飲めないでしょう。
その場合は、山廃造りやきもと造りの純米系の無濾過表示のお酒
をお飲みになればよろしいかと思います。
山廃無濾過純米酒、きもと純米無濾過酒など脚光が当たってほしい分野です。
これまでは、香りが良いとか、切れが良いとか重要視されてましたものね。
さて、いかがいたしましょうか?
醸造アルコールの添加やお酒自体についてのお考えが変わったかもしれません。
それから、私自身、上の文章でも書き忘れていることもある可能性があることは
御容赦くださいね。
「醸造アルコールって何?」
「醸造アルコールが入っている方がよくないでしょ?」
酒業界内でも醸造アルコールならぬ増量アルコールだと言われる方もいます。
良くも悪くも取られてしまう醸造アルコールについてですから、
表立って公表しづらい点もあります。
日本酒には醸造アルコールが添加されている本醸造系と
入っていない純米系に分かれます。
アルコール添加については江戸時代から柱焼酎の添加として始まっています。
江戸時代には冷蔵設備がなく、アルコール度の小さなお酒は雑菌などに
やられてしまいます。お酒がお酒とは思えない液体に変化してしまいます。
このために江戸時代に伝わり、造れるようになった焼酎(本格焼酎)を
出来た日本酒に混ぜて保存していました。
江戸時代のアルコール添加は腐敗防止剤の役目をする食品添加物でありました。
明治、大正、昭和となるにつれて、世の中のあらゆることが変わってきます。
戦争がありました。
日本も日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦、第二次世界大戦と参戦します。
日清・日露は酒税で戦ったと言われるほどに、酒税が高くなりました。
お酒は当時の日本になくてはならない担税物資となったわけです。
国税の1/3であります。
第二次世界大戦で日本は負けますが、負ける前後の状況はひどいもので、
食べる米すらない状態ですから、お酒にするお米などは明らかに少ない。
国としては、少ないお米からなるべく多くのお酒を造りたい。
そんな折、満州で三倍醸造法が誕生しました。
これは出来上がったお酒にアルコールを入れて、アルコールが高くなった分を
下げるための水を入れます。
水が入った分だけ味が薄くなるので、調味料で補う製法です。
出来たお酒を三倍に増やす三倍醸造であります。
戦争で物資がなかった時代の緊急避難用の酒としてであればしょうがない。
いや、優れものでありました。
ところが、戦後日本は高度成長して、豊かになります。
時代は豊かになりましたが、お酒は三倍醸造が溢れていました。
低価格酒であります。
パック酒に米、米麹、醸造アルコール、糖類、酸味料と書かれているのがあります。
満州で開発された造り方と、そんなには変わっていません。
醸造アルコールの使用量は決められています。
白米1トンあたりの原料に対して、アルコール約120リットルです。
この時のアルコールはアルコール100%の度数として計算されます。
これは出来上がったお酒のアルコール分のおよそ1/4であります。
問題視されている事柄がありますから、議論に上ります。
1.醸造アルコールとは何なのか?
2.醸造アルコールは何のために入れているのか?
ここが壺でしょう。上の答えです。
1.醸造アルコールは、酒造会社によっては、自社製造の焼酎を使っています。
一般的には純度の高い焼酎甲類です。梅酒に使うものと同等です。
醸造アルコールの原料は決められていますが、昭和の50年代くらい前
までは、その正体を配給元のアルコール生産会社が明かしてくれません
でしたから、石油からではないか、ブラジルやフィピリンのサトウキビの
くずからではないかと騒がれました。
ブラジルはバイオエタノールの先進国です。
現在使われている醸造アルコールについては心配ないと思われます。
2.醸造アルコールを入れると出来上がるお酒は多くできます。
かさ上げできるわけです。
増量アルコールと皮肉くる人もいるわけです。
蔵元は醸造的にアルコールを入れて腐敗防止をする方が安全だと言う方もいます。
では、純米酒は安全ではないのか、につながりますね。
江戸時代の柱焼酎添加と同じだと言われる蔵元もいますが、
添加の量が違いすぎます。
柱焼酎の添加量よりも、圧倒的に醸造アルコールの添加量が多いです。
そして、もろみを搾る前に醸造アルコールを添加すると、香りが良くなる。
本来、酒粕に行ってしまう芳香をアルコールによって、抽出できる。
吟醸香が強くなるからとの理由もあります。
醸造アルコールを入れて加水した分、味がすっきりして、辛口になるとの理由も言われます。
同時にその酒質を醸造アルコール抜きでするのが努力ではないかと言う方もいます。
ここで添加の意味合いから、醸造アルコール以外を見てみましょうか。
日本酒のラベル表示は酒税法で決められた基準に沿って明記しなければなりません。
純米酒は米と米麹と書かれていますが、本当にそれだけでできるのでしょうか?
酵母菌や麹菌を使っていることは問題ないでしょう。
では、使用を許されていて、明記の義務がない食品添加物についてはどうですか?
山廃造りやきもとつくり以外のお酒では、乳酸を添加しています。
乳酸はお酒では食品添加物扱いですが、一般的には薬品です。
この他、酵素補助剤も使います。
濾過のために活性炭や濾過助剤に珪藻土を使い、ろ紙にも通します。
こう考えると、醸造アルコールも一つの食品添加物のような存在に思えるでしょう。
醸造アルコールは気にして、その他の乳酸などのことはかまわないとはいかないですね。
私は次のように解釈します。
醸造アルコールを添加した本醸造系=薄口
添加していない純米系=濃い口
の2タイプを造り出している。
これが他の食品類と比較した時に、一番理解しやすい解釈ではないでしょうか?
本醸造系=本醸造、特別本醸造、吟醸、大吟醸 は辛口傾向。
純米系=純米酒、特別純米酒、純米吟醸、純米大吟醸は旨口傾向。
醸造アルコールが添加してあるお酒は体にはよくない?とも聞かれます。
私の知り合いの杜氏は、体のためを想って、純米酒は飲みません。
醸造アルコールを添加してある本醸造系統しか飲みませんという方もいます。
この杜氏さんの体にとっては、純米酒は濃すぎて、胃をやられることもあるそうです。
現状、醸造アルコール添加酒もあるし、醸造アルコールが添加してないお酒もあるし、
味わいがバラエティーに富んでいると楽天的に考えているのがいいのではないでしょうか?
それから、どうしても醸造アルコール添加が許せないとか、醸造アルコールが添加して
あるお酒は飲めないということならば、乳酸添加酒も飲めないですし、黒い炭が漬かった
濾過してあるお酒も飲めないでしょう。
その場合は、山廃造りやきもと造りの純米系の無濾過表示のお酒
をお飲みになればよろしいかと思います。
山廃無濾過純米酒、きもと純米無濾過酒など脚光が当たってほしい分野です。
これまでは、香りが良いとか、切れが良いとか重要視されてましたものね。
さて、いかがいたしましょうか?
醸造アルコールの添加やお酒自体についてのお考えが変わったかもしれません。
それから、私自身、上の文章でも書き忘れていることもある可能性があることは
御容赦くださいね。
2009年02月25日
ボディーソープ何使ってる?
ボディーソープの人気投票結果が日経MJに載ってました。
消費者の人気投票ではなく、バイヤー、売り手である
お店側の採点結果であります。
上位が発表されています。
1.ビオレu(花王)
2.ダブ(ユニリーバ・ジャパン)
3.ナイーブ(クラシエホームプロダクツ)
4.ミルキィボディーソープ(牛乳石鹸共進社)
5.ラックス(ユニリーバ・ジャパン)
6.植物物語(ライオン)
7.カウブランド(牛乳石鹸共進社)
8.BATHTOLOGY(ライオン)
9・ジョンソン・ボディーケア(ジョンソン・エンド・ジョンソン)
主な採点の評価項目は次であります。
・ブランド力
・TVCMなどの宣伝広告
・利益率
・洗浄成分、泡立ち
・リピート購入率
・香り
・スキンケア効果などの付加価値
・商品価値と価格のバランス
この中のほとんどの項目で第一位の花王ビオレuはトップでありました。
ビオレuがトップを取れなかった項目は次。
・利益率(最下位)
・洗浄成分、泡立ち(2位)
・スキンケア効果などの付加価値(2位)
また、上の「洗浄成分、泡立ち」「スキンケア効果などの付加価値」という
品質で花王ビオレuを上回っていたのは、総合2位のダブ(ユニリーバ・ジャパン)。
となりますと、花王のビオレuは利益が薄く、品質でもNO1.ではないとなります。
では、どういう理由で仕入れているのか。
仕入れの基準や、力の入れ具合はどこから来るのか?
ここが使い手である我々消費者が気になるところです。
日経MJによりますと、
1.ブランド力
2.TVCMなどの宣伝広告
3.利益率
4.洗浄成分、泡立ち
5.リピート購入率
6.取引条件
7.香り
8.スキンケア効果などの付加価値
9.商品価値と価格のバランス
10.ブランド育成力
仕入れ基準の結果から、売り手の心が見ます。
心というか、商売上はしょうがないことではあります。
一にも二にもブランド力。
単一売り場面積当たりの売上高が最重要視されています。
消費者のためにが第一に来るのではありません。
この調査は日経新聞社の小売業調査の対象になっている
スーパー150社に対して行われたそうです。
一昔前までは、街の小さな薬局があって、
近所付き合いの延長線上として、
薬や雑貨の相談をしてくれたものです。
正直者が損しているのかな。
そういう世の中ってよくありませんね。
ボディーソープだって、自分で使った感触をお客さんに伝えてほしいです。
丸河屋酒店で取り扱う銘柄の選定条件は定かではありません。
しかし、確かなことは、自分で味見して、そのお酒があった方が、
生活が楽しい、その結果、お酒のあった方が素敵な人生になる。
そのポリシーを第一に選んで、おすすめしています。
時たま、取引先の蔵元さんもおっしゃいます。
「もっとブランド力のある銘柄を販売された方がいいよ!」
いえいえ、私は商売上育ってきたブランドは軽視しています。
街の酒屋は、食卓に一番近い存在でいたいですから。
っで、我が家のボディーソープは何を使っていたっけ?
とお風呂場で確かめると、これ。

妻に購入の決め手となった要素は何か聞いてみます。
消費者の人気投票ではなく、バイヤー、売り手である
お店側の採点結果であります。
上位が発表されています。
1.ビオレu(花王)
2.ダブ(ユニリーバ・ジャパン)
3.ナイーブ(クラシエホームプロダクツ)
4.ミルキィボディーソープ(牛乳石鹸共進社)
5.ラックス(ユニリーバ・ジャパン)
6.植物物語(ライオン)
7.カウブランド(牛乳石鹸共進社)
8.BATHTOLOGY(ライオン)
9・ジョンソン・ボディーケア(ジョンソン・エンド・ジョンソン)
主な採点の評価項目は次であります。
・ブランド力
・TVCMなどの宣伝広告
・利益率
・洗浄成分、泡立ち
・リピート購入率
・香り
・スキンケア効果などの付加価値
・商品価値と価格のバランス
この中のほとんどの項目で第一位の花王ビオレuはトップでありました。
ビオレuがトップを取れなかった項目は次。
・利益率(最下位)
・洗浄成分、泡立ち(2位)
・スキンケア効果などの付加価値(2位)
また、上の「洗浄成分、泡立ち」「スキンケア効果などの付加価値」という
品質で花王ビオレuを上回っていたのは、総合2位のダブ(ユニリーバ・ジャパン)。
となりますと、花王のビオレuは利益が薄く、品質でもNO1.ではないとなります。
では、どういう理由で仕入れているのか。
仕入れの基準や、力の入れ具合はどこから来るのか?
ここが使い手である我々消費者が気になるところです。
日経MJによりますと、
1.ブランド力
2.TVCMなどの宣伝広告
3.利益率
4.洗浄成分、泡立ち
5.リピート購入率
6.取引条件
7.香り
8.スキンケア効果などの付加価値
9.商品価値と価格のバランス
10.ブランド育成力
仕入れ基準の結果から、売り手の心が見ます。
心というか、商売上はしょうがないことではあります。
一にも二にもブランド力。
単一売り場面積当たりの売上高が最重要視されています。
消費者のためにが第一に来るのではありません。
この調査は日経新聞社の小売業調査の対象になっている
スーパー150社に対して行われたそうです。
一昔前までは、街の小さな薬局があって、
近所付き合いの延長線上として、
薬や雑貨の相談をしてくれたものです。
正直者が損しているのかな。
そういう世の中ってよくありませんね。
ボディーソープだって、自分で使った感触をお客さんに伝えてほしいです。
丸河屋酒店で取り扱う銘柄の選定条件は定かではありません。
しかし、確かなことは、自分で味見して、そのお酒があった方が、
生活が楽しい、その結果、お酒のあった方が素敵な人生になる。
そのポリシーを第一に選んで、おすすめしています。
時たま、取引先の蔵元さんもおっしゃいます。
「もっとブランド力のある銘柄を販売された方がいいよ!」
いえいえ、私は商売上育ってきたブランドは軽視しています。
街の酒屋は、食卓に一番近い存在でいたいですから。
っで、我が家のボディーソープは何を使っていたっけ?
とお風呂場で確かめると、これ。
妻に購入の決め手となった要素は何か聞いてみます。
2009年02月24日
ビール券とすし券
今、ビール券はあまり見ないですよね。
メーカーさんがやめたりしてますし、
このことからも下火です。
一方で、すし券は威勢がいいです。
すし組合で力を入れているからです。
ビール券とすし券で、商品特性や人間の気持ちが見えてきます。
ビール券に大瓶2本と交換できますと書かれています。
酒税や値上げなどによって、昔のビール券だと不足が生じたりしてました。
それも風物詩ですよね。
「古い券だから、あと15円ちょうだいね。」
などと会話していたものです。
また、ビールケースと空き瓶を現金で回収していましたから、
ビールを配達して、ビール券を出されると、箱代と空瓶代を置いてくる。
結局、売りに行ったのに、逆にお金を置いてくる、
なんていうこともよくありました。
ビールの配達は常連さんですから、割りにあわないこともあっても
いいかあと、気にしなかったものです。
ビール券が姿を消していく理由はいろいろあります。
昔は定価制のようにどこでも同じ割引なしの金額でビールが販売されていましたが、
今では値段はまちまちで、昔よりは安いです。
ビール券とビールそのものの金額の格差が生じています。
ビール券の利益率はビールを売るよりも低いです。
というか、贈与税が含まれていますから、ほとんど利益なしであります。
利益のないビール券を売って、ビール券で利益のないビールを買われる。
この繰り返しでは、国税しかお金は入ってきません。
酒屋は酒販免許制となっており、免許人の義務という側面からも、
割に合わなくても使命として、ビール券の仕事をしていました。
現在は免許制度は残っていますが、距離基準と人口基準ははずされ、
実質ほとんどの希望者が免許を取得できます。
それにともなって、免許人としての義務意識も変わりましたから、
ビール券にまつわる業者は避けるのも当然であります。
ビール券は「酒販店」~「問屋」~「メーカー」だったのが、
「酒販店」~「銀行」~「メーカー」になり、
金融機関もそっぽを向いたために、酒販店は金券ショップに持ち込んだりします。
すし券は500円で買い、500円分のおすしが食べられる。
おすし屋さんで食べた場合は、食べた金額からすし券分の金額を差し引いてもらえます。
ビールがほとんど利益のない商材に対して、おすしはそれよりも利益があります。
額面通りのサービスをすれば、ほとんど現金と変わらないでしょう。
それから、ビール券とすし券の使い方の最大の違い。
ビール券を持ってこられた方は、その分しか持って帰りません。
他のものをいっしょに買うという気持ちにはならないみたいです。
すし券をおすし屋さんに持ってきて、食事した場合は、
すし券の額面よりも多く使ってくれます。
たとえ、食べた金額以上のすし券を持っていても、
全部はすし券で払わず、現金を置いていく。
では、どこくらいの確率で券以上のお金を落とすか。
ビール券の場合は、限りなく0であります。
私が酒販店勤務をして2009年で27年目に入ります。
ビール券を扱った件数は1,000以上はあるでしょう。
その中で、ビール券のビール分以外の
ついで買いをしてくれた方は・・・・たったの2名であります。
ほぼ100%の割合で、ビール券だけの使用。
ビール券 + 現金 は2名様だけです。
驚きの数字でありましょう。
お寿しの場合は、逆だそうです。
すし組合の方から言われました。
「何もビール券がもうからないからって、やめることないでしょ。」
「ビール券以外の物もついでに買っていってくれるでしょ。」
いやいやお酒とおすしでは、人間心理の働き方が違うのですね。
ビール券があった!
酒屋に行って、商品と換えてこよう。
ビール以外の商品と換えることのできるのは当たり前だ。
すし券があった!
今度おすしを食べに行ったときに使わせてもらおう。
酒屋ではビール券だけを使うのは平気。
おすし屋さんではすし券だけだと悪いよ。
おすし屋さんの場合は、その場所にごやっかいになることもあり、
おすしの現物以外のサービスもしてもらいますから、
こういう気持ちになるのでしょう。
人間は多面的な行動をします。
ビール券が消える。
それは我々が人間だからでありましょうか。
メーカーさんがやめたりしてますし、
このことからも下火です。
一方で、すし券は威勢がいいです。
すし組合で力を入れているからです。
ビール券とすし券で、商品特性や人間の気持ちが見えてきます。
ビール券に大瓶2本と交換できますと書かれています。
酒税や値上げなどによって、昔のビール券だと不足が生じたりしてました。
それも風物詩ですよね。
「古い券だから、あと15円ちょうだいね。」
などと会話していたものです。
また、ビールケースと空き瓶を現金で回収していましたから、
ビールを配達して、ビール券を出されると、箱代と空瓶代を置いてくる。
結局、売りに行ったのに、逆にお金を置いてくる、
なんていうこともよくありました。
ビールの配達は常連さんですから、割りにあわないこともあっても
いいかあと、気にしなかったものです。
ビール券が姿を消していく理由はいろいろあります。
昔は定価制のようにどこでも同じ割引なしの金額でビールが販売されていましたが、
今では値段はまちまちで、昔よりは安いです。
ビール券とビールそのものの金額の格差が生じています。
ビール券の利益率はビールを売るよりも低いです。
というか、贈与税が含まれていますから、ほとんど利益なしであります。
利益のないビール券を売って、ビール券で利益のないビールを買われる。
この繰り返しでは、国税しかお金は入ってきません。
酒屋は酒販免許制となっており、免許人の義務という側面からも、
割に合わなくても使命として、ビール券の仕事をしていました。
現在は免許制度は残っていますが、距離基準と人口基準ははずされ、
実質ほとんどの希望者が免許を取得できます。
それにともなって、免許人としての義務意識も変わりましたから、
ビール券にまつわる業者は避けるのも当然であります。
ビール券は「酒販店」~「問屋」~「メーカー」だったのが、
「酒販店」~「銀行」~「メーカー」になり、
金融機関もそっぽを向いたために、酒販店は金券ショップに持ち込んだりします。
すし券は500円で買い、500円分のおすしが食べられる。
おすし屋さんで食べた場合は、食べた金額からすし券分の金額を差し引いてもらえます。
ビールがほとんど利益のない商材に対して、おすしはそれよりも利益があります。
額面通りのサービスをすれば、ほとんど現金と変わらないでしょう。
それから、ビール券とすし券の使い方の最大の違い。
ビール券を持ってこられた方は、その分しか持って帰りません。
他のものをいっしょに買うという気持ちにはならないみたいです。
すし券をおすし屋さんに持ってきて、食事した場合は、
すし券の額面よりも多く使ってくれます。
たとえ、食べた金額以上のすし券を持っていても、
全部はすし券で払わず、現金を置いていく。
では、どこくらいの確率で券以上のお金を落とすか。
ビール券の場合は、限りなく0であります。
私が酒販店勤務をして2009年で27年目に入ります。
ビール券を扱った件数は1,000以上はあるでしょう。
その中で、ビール券のビール分以外の
ついで買いをしてくれた方は・・・・たったの2名であります。
ほぼ100%の割合で、ビール券だけの使用。
ビール券 + 現金 は2名様だけです。
驚きの数字でありましょう。
お寿しの場合は、逆だそうです。
すし組合の方から言われました。
「何もビール券がもうからないからって、やめることないでしょ。」
「ビール券以外の物もついでに買っていってくれるでしょ。」
いやいやお酒とおすしでは、人間心理の働き方が違うのですね。
ビール券があった!
酒屋に行って、商品と換えてこよう。
ビール以外の商品と換えることのできるのは当たり前だ。
すし券があった!
今度おすしを食べに行ったときに使わせてもらおう。
酒屋ではビール券だけを使うのは平気。
おすし屋さんではすし券だけだと悪いよ。
おすし屋さんの場合は、その場所にごやっかいになることもあり、
おすしの現物以外のサービスもしてもらいますから、
こういう気持ちになるのでしょう。
人間は多面的な行動をします。
ビール券が消える。
それは我々が人間だからでありましょうか。
2009年01月27日
缶ビールの最安値
毎月のように、ビールの価格を酒販店の組織が調べています。
東京と大阪にて配付されたチラシで価格をチェックしています。
大型酒販店、ディスカウント店などの安売りの末の倒産が相次いでいます。
酒類の価格はそれにかかっている酒税額よりも下回ってはいけない。
つまり、仕入れ値よりも安く売れなくなっているのであります。
倒産されると酒税まで取れなくなります。
このために酒税確保のための、最低価格は決まってきます。
酒税を円滑に納められることも、酒免許の有意義であります。
もともとは酒税は国税の1/3まであったくらいですから、
酒販免許は酒税にとっての存在の意味合いがありました。
販売価格については行政が関与しています。
不法と思われる行為は公正取引委員会に報告されます。
行政任せだけでなく、自分らで酒税法をおかしている販売をチェックしているのであります。
それが自分らのためであって、社会のためでありましょう。
11月の東京と大阪の小売価格最安値です。
東京 ビール350ml缶1本-\173、発泡酒350lm缶1本-\113。
大阪 ビール350ml缶1本-\173、発泡酒350lm缶1本-\108。
これらは10月もいっしょでしたから、ここのところはこの価格で推移しているのでしょうね。
安ければいいじゃんと思われがち。
でも思い出して下さい!
これまでの八百半やダイエーなどの大型店。
処理には税金も投入されました。
JRの運賃も上がり、たばこも値上げされました。
もう忘れちゃったかな?
倒産すると小さなお店や会社は自分だけのへこみですが、
大きくなると社会が支えなければなりません。
例えば、静岡県内の東部を中心に24店あった居酒屋チェーンの話。
生ビールの安さを売り物にしていましたが、2008年秋に倒産。
倒産直後の社長は夜逃げでつかまらない。
従業員の給料も仕入れた代金も支払われないまま。
きちんと利益を取ることも社会善であります。
取り過ぎも問題。
利益をどう使うか、還元していくかも問題なのですね。
東京と大阪にて配付されたチラシで価格をチェックしています。
大型酒販店、ディスカウント店などの安売りの末の倒産が相次いでいます。
酒類の価格はそれにかかっている酒税額よりも下回ってはいけない。
つまり、仕入れ値よりも安く売れなくなっているのであります。
倒産されると酒税まで取れなくなります。
このために酒税確保のための、最低価格は決まってきます。
酒税を円滑に納められることも、酒免許の有意義であります。
もともとは酒税は国税の1/3まであったくらいですから、
酒販免許は酒税にとっての存在の意味合いがありました。
販売価格については行政が関与しています。
不法と思われる行為は公正取引委員会に報告されます。
行政任せだけでなく、自分らで酒税法をおかしている販売をチェックしているのであります。
それが自分らのためであって、社会のためでありましょう。
11月の東京と大阪の小売価格最安値です。
東京 ビール350ml缶1本-\173、発泡酒350lm缶1本-\113。
大阪 ビール350ml缶1本-\173、発泡酒350lm缶1本-\108。
これらは10月もいっしょでしたから、ここのところはこの価格で推移しているのでしょうね。
安ければいいじゃんと思われがち。
でも思い出して下さい!
これまでの八百半やダイエーなどの大型店。
処理には税金も投入されました。
JRの運賃も上がり、たばこも値上げされました。
もう忘れちゃったかな?
倒産すると小さなお店や会社は自分だけのへこみですが、
大きくなると社会が支えなければなりません。
例えば、静岡県内の東部を中心に24店あった居酒屋チェーンの話。
生ビールの安さを売り物にしていましたが、2008年秋に倒産。
倒産直後の社長は夜逃げでつかまらない。
従業員の給料も仕入れた代金も支払われないまま。
きちんと利益を取ることも社会善であります。
取り過ぎも問題。
利益をどう使うか、還元していくかも問題なのですね。
2009年01月10日
通販は横着か?
ネットを使った通販は横着で手抜きか?
アンチ通販者からはそう見えるでしょう。
以前はお酒を造る蔵元も、このお酒は対面販売専門で、
不特定多数が買えるネット通販では売らないでほしいとよく言ったものです。
確かにお買い物かごを設置してある通販は、自動販売機のようにも見られます。
では、例えば、駅の中や商店街のお店はどうでしょう?
駅などは目まぐるしく不特定多数の人々が過ぎ去ります。
そもそも商売は不特定多数を対象として成り立っています。
タクシーもお客さんを特定して、乗車拒否できません。
丸河屋は店頭売りも、配達も、ネットやFAXでの発送もしています。
売り手として、何が大変で何が楽だと思いますか?
・店売りが一番楽です。
お客さんが足を運んでくれますから。
丸河屋でも御予約され、御来店を待つお酒は、伝票をくっつけて、
お客さんがいつ来てもわかるように、冷蔵庫に入れてあります。

・二番目は配達です。
配達は丸河屋号に荷物を載せて、お客さんの希望する時間に、
希望する商品をお届けします。
・そして最も手がかかるのが通販であります。
受注後、お客様にご注文の御確認メールを送ります。
伝票を書いて、宅急便の伝票を作成します。
クレジットの場合は、お客さんにご自身で決済のための与信をしてもらいますから、
その与信のためのメールを別途送ります。
通販の荷物は、お酒の大きさと本数により、ダンボールで作ることになります。

これは300mlを6本の場合です。
缶ビールの入っていたダンボールの底にクッションのための紙を敷き、
お酒を入れて、それが箱の中で配送中に動かないように、新聞紙で固めます。
できあがるとこのようになります。

特に冬はダンボールとの戦いで、手がやられます。
お客さんにとっても通販で買いますと、箱などの必要のないものが増えます。
リサイクルや処分する手間が増えます。
しかし、欲しい物を待つ楽しみはありますね。
欲しい物が頼んだ翌日にきちんと届く。
便利ですし、うれしですね。
梱包には愛情一杯注いで発送作業をしているのです。
結局のところ、心をしては、店売りも配達も通販も同じ。
こうしなければいけないなどのこだわりを持つこそ、商品とお客様への心がない。
そうのように映ります。
最近は製造者である蔵元もわかるようになりなったのでしょう、
通販こそ大変なんだってねえと言われるようになりました。
通販しているお店のほとんどが、来店しづらい存在地にあります。
通販していないお店は比較的好立地にあるようです。
好立地で家賃もなければ、それが恵まれた環境です。
私の立場から訴えます。
通販はきめ細かく、お客様に接しているお店が多いです。
私も見ていて、よくそこまでやるなあと思えるお店がたくさんあります。
そして、誰もが通販ができる今、逆に通販をしないで来店客さんを大事に
していこうというお店も健在しています。
アンチ通販者からはそう見えるでしょう。
以前はお酒を造る蔵元も、このお酒は対面販売専門で、
不特定多数が買えるネット通販では売らないでほしいとよく言ったものです。
確かにお買い物かごを設置してある通販は、自動販売機のようにも見られます。
では、例えば、駅の中や商店街のお店はどうでしょう?
駅などは目まぐるしく不特定多数の人々が過ぎ去ります。
そもそも商売は不特定多数を対象として成り立っています。
タクシーもお客さんを特定して、乗車拒否できません。
丸河屋は店頭売りも、配達も、ネットやFAXでの発送もしています。
売り手として、何が大変で何が楽だと思いますか?
・店売りが一番楽です。
お客さんが足を運んでくれますから。
丸河屋でも御予約され、御来店を待つお酒は、伝票をくっつけて、
お客さんがいつ来てもわかるように、冷蔵庫に入れてあります。
・二番目は配達です。
配達は丸河屋号に荷物を載せて、お客さんの希望する時間に、
希望する商品をお届けします。
・そして最も手がかかるのが通販であります。
受注後、お客様にご注文の御確認メールを送ります。
伝票を書いて、宅急便の伝票を作成します。
クレジットの場合は、お客さんにご自身で決済のための与信をしてもらいますから、
その与信のためのメールを別途送ります。
通販の荷物は、お酒の大きさと本数により、ダンボールで作ることになります。
これは300mlを6本の場合です。
缶ビールの入っていたダンボールの底にクッションのための紙を敷き、
お酒を入れて、それが箱の中で配送中に動かないように、新聞紙で固めます。
できあがるとこのようになります。
特に冬はダンボールとの戦いで、手がやられます。
お客さんにとっても通販で買いますと、箱などの必要のないものが増えます。
リサイクルや処分する手間が増えます。
しかし、欲しい物を待つ楽しみはありますね。
欲しい物が頼んだ翌日にきちんと届く。
便利ですし、うれしですね。
梱包には愛情一杯注いで発送作業をしているのです。
結局のところ、心をしては、店売りも配達も通販も同じ。
こうしなければいけないなどのこだわりを持つこそ、商品とお客様への心がない。
そうのように映ります。
最近は製造者である蔵元もわかるようになりなったのでしょう、
通販こそ大変なんだってねえと言われるようになりました。
通販しているお店のほとんどが、来店しづらい存在地にあります。
通販していないお店は比較的好立地にあるようです。
好立地で家賃もなければ、それが恵まれた環境です。
私の立場から訴えます。
通販はきめ細かく、お客様に接しているお店が多いです。
私も見ていて、よくそこまでやるなあと思えるお店がたくさんあります。
そして、誰もが通販ができる今、逆に通販をしないで来店客さんを大事に
していこうというお店も健在しています。
2008年12月13日
生ビールから瓶ビールへシフト
ビールの容器は缶が主流となり、瓶は一般家庭用としては、ほぼ消滅した感じでいました。
飲食店では、缶ではなくって、生か瓶が選べるようになっているのが一般的であります。
いまどきは、他人のグラスに継ぎ足すこともあまりしない風潮ですし、
「とりあえず生」が合言葉。一昔前は「とりあえずビール」でしたが。
だから飲食店では瓶ではなくって、生が主流。
ビールメーカーは飲食店の方々にも上手に生ビールをそそげるように、
だいぶ力を入れて指導してきました。
ここのお店は生ビールが美味しいんだよとお客さんにもわかってもらえるような
講習会の修了書のようなものも作って、飲食店のお客さんの見えるところに
飾ってあるものです。
そして、グラスもめちゃくちゃきれいにして、天子のリングが出るように指導してきました。
飲食店にしてみても、生ビールは瓶ビールよりも儲かります。
中瓶1本500円くらいが相場でしょう。
生だって一杯500円くらい、あるいは瓶よりもちょっとだけ割高な550円とか。
容量は中瓶が500ml。
中ジョッキは昔の主流は500mlで、今は435mlです。
生ビールを頼んだ場合は、ジョッキに泡が乗っているために、実質のビールの容量は
ジョッキの70%ほどであります。
生ビールのサーバーを使う場合は、別売りの炭酸ガスが必要です。
これは信じられないくらい安いですから、生ビールの価格には影響しないほどであります。
生ビールはサーバーという機械が必要で、瓶ビールは冷蔵庫が必要です。
以前は業務店ということで、メーカーが冷蔵庫を無償貸出していましたが、10年くらい
前からは、一切冷蔵庫にはかかわりを持たなくなりました。
サーバーについては今も昔も貸してくれます。
これらが飲食店で瓶ビールよりも生ビールが儲かる理由です。
儲かってもらうことは良い事です。
しかも生ビールは缶(樽)に入っていますから、光に当たりません。
生ビールサーバーは瞬間冷却が主流ですから、あらかじめ冷やしておく必要もなし。
このように生ビールは飲み手にとっても、売り手(流通以外)にとっても美味しいものでありました。
ところが2008年は変化が起こりました。
どうも生ビールから瓶ビールへシフトしてきた気配があります。
特に11月からはこの流れが顕著です。
年末にかけての宴会があるので、瓶ビールが増えますが、そのことを織り込んでも
瓶ビールが出てきました。
宴会も生で通してきたお店の方も不思議がっています。
生ビールと瓶ビールと缶ビールの中味はいっしょです。
昔はメーカーによっては違っていたこともありますが、今はいっしょ。
このことがだんだんわかってきたことも、瓶へのシフトの理由。
では、味わい的にはどうか?
味覚としてのビール選びから考えると、プレミアムビールが堅調です。
つまり味の濃い商品へとシフトしてきました。
これはビールだけに限らず、発泡酒も第三のビールなどもそうです。
味の濃さのイメージとしては、瓶が優勢でしょう。
味が濃くなるにつれて、入れ物は小さくなっていきます。
黒ビールは小瓶しかないくらいです。
日本のビールは炭酸が強いです。
冷たくして飲み、清涼感を十分に味わいたいのが飲み手。
炭酸は生ビールよりも瓶ビールの方が強く感じます。
これは注ぎ方にもよりますが、瓶ビールは王冠を抜くまでは、
炭酸が逃げていません。
私が最大の理由と思っているのは、炭酸がらみの味わい。
ここ数年は飲み放題でいくら、のお店が増えました。
こういう場合は瓶ではなく、ジョッキとか、ピッチャーでお客さんのところに持って行きます。
瓶ビールの場合は、お代わりのときに問題が発生します。
まだ瓶の中にあるにもかかわらず、追加オーダーしてしまう可能性が高いです。
ピッチャーをテーブルの上においておけば、ビールがどのくらいあるのか、わかります。
このピッチャーで飲むビールに問題があります。
ピッチャーにジャボジャボ注ぎますから、炭酸ガスが逃げていきます。
しかもピッチャーは量が多いので、すぐには空になりません。
店員さんが注ぐときに炭酸ガスが逃げて、さらにお客さんのテーブルの上でも逃げていく。
これでは炭酸の量が多くて、バランスをとっている日本のビールの美味しさは半減してしまいます。
美味しかったのか、美味しくなかったのか。
それははっきりと脳裏に刻まれていないものの、次に同じケースに遭遇したときには、
条件反射的な動きをするのではないでしょうか。
これが生ビールを頼む際の不安材料になっていると思われます。
葉茶滅茶な飲み放題サービスをしてきた店は追い込まれているところが多いです。
これらは生ビールの不信という傷跡を残して去ります。
これからも残る、心ある飲食店の生ビールは美味しいはずです。
あなたは瓶ビール派? それとも生ビール派?
私は基本的には瓶で、時に店によっては生にしています。
中味はもともといっしょ。
後は携わる人がどうかっていうところですよ。
飲食店では、缶ではなくって、生か瓶が選べるようになっているのが一般的であります。
いまどきは、他人のグラスに継ぎ足すこともあまりしない風潮ですし、
「とりあえず生」が合言葉。一昔前は「とりあえずビール」でしたが。
だから飲食店では瓶ではなくって、生が主流。
ビールメーカーは飲食店の方々にも上手に生ビールをそそげるように、
だいぶ力を入れて指導してきました。
ここのお店は生ビールが美味しいんだよとお客さんにもわかってもらえるような
講習会の修了書のようなものも作って、飲食店のお客さんの見えるところに
飾ってあるものです。
そして、グラスもめちゃくちゃきれいにして、天子のリングが出るように指導してきました。
飲食店にしてみても、生ビールは瓶ビールよりも儲かります。
中瓶1本500円くらいが相場でしょう。
生だって一杯500円くらい、あるいは瓶よりもちょっとだけ割高な550円とか。
容量は中瓶が500ml。
中ジョッキは昔の主流は500mlで、今は435mlです。
生ビールを頼んだ場合は、ジョッキに泡が乗っているために、実質のビールの容量は
ジョッキの70%ほどであります。
生ビールのサーバーを使う場合は、別売りの炭酸ガスが必要です。
これは信じられないくらい安いですから、生ビールの価格には影響しないほどであります。
生ビールはサーバーという機械が必要で、瓶ビールは冷蔵庫が必要です。
以前は業務店ということで、メーカーが冷蔵庫を無償貸出していましたが、10年くらい
前からは、一切冷蔵庫にはかかわりを持たなくなりました。
サーバーについては今も昔も貸してくれます。
これらが飲食店で瓶ビールよりも生ビールが儲かる理由です。
儲かってもらうことは良い事です。
しかも生ビールは缶(樽)に入っていますから、光に当たりません。
生ビールサーバーは瞬間冷却が主流ですから、あらかじめ冷やしておく必要もなし。
このように生ビールは飲み手にとっても、売り手(流通以外)にとっても美味しいものでありました。
ところが2008年は変化が起こりました。
どうも生ビールから瓶ビールへシフトしてきた気配があります。
特に11月からはこの流れが顕著です。
年末にかけての宴会があるので、瓶ビールが増えますが、そのことを織り込んでも
瓶ビールが出てきました。
宴会も生で通してきたお店の方も不思議がっています。
生ビールと瓶ビールと缶ビールの中味はいっしょです。
昔はメーカーによっては違っていたこともありますが、今はいっしょ。
このことがだんだんわかってきたことも、瓶へのシフトの理由。
では、味わい的にはどうか?
味覚としてのビール選びから考えると、プレミアムビールが堅調です。
つまり味の濃い商品へとシフトしてきました。
これはビールだけに限らず、発泡酒も第三のビールなどもそうです。
味の濃さのイメージとしては、瓶が優勢でしょう。
味が濃くなるにつれて、入れ物は小さくなっていきます。
黒ビールは小瓶しかないくらいです。
日本のビールは炭酸が強いです。
冷たくして飲み、清涼感を十分に味わいたいのが飲み手。
炭酸は生ビールよりも瓶ビールの方が強く感じます。
これは注ぎ方にもよりますが、瓶ビールは王冠を抜くまでは、
炭酸が逃げていません。
私が最大の理由と思っているのは、炭酸がらみの味わい。
ここ数年は飲み放題でいくら、のお店が増えました。
こういう場合は瓶ではなく、ジョッキとか、ピッチャーでお客さんのところに持って行きます。
瓶ビールの場合は、お代わりのときに問題が発生します。
まだ瓶の中にあるにもかかわらず、追加オーダーしてしまう可能性が高いです。
ピッチャーをテーブルの上においておけば、ビールがどのくらいあるのか、わかります。
このピッチャーで飲むビールに問題があります。
ピッチャーにジャボジャボ注ぎますから、炭酸ガスが逃げていきます。
しかもピッチャーは量が多いので、すぐには空になりません。
店員さんが注ぐときに炭酸ガスが逃げて、さらにお客さんのテーブルの上でも逃げていく。
これでは炭酸の量が多くて、バランスをとっている日本のビールの美味しさは半減してしまいます。
美味しかったのか、美味しくなかったのか。
それははっきりと脳裏に刻まれていないものの、次に同じケースに遭遇したときには、
条件反射的な動きをするのではないでしょうか。
これが生ビールを頼む際の不安材料になっていると思われます。
葉茶滅茶な飲み放題サービスをしてきた店は追い込まれているところが多いです。
これらは生ビールの不信という傷跡を残して去ります。
これからも残る、心ある飲食店の生ビールは美味しいはずです。
あなたは瓶ビール派? それとも生ビール派?
私は基本的には瓶で、時に店によっては生にしています。
中味はもともといっしょ。
後は携わる人がどうかっていうところですよ。
2008年12月10日
酒屋の窮状
何何屋と名がつく商売は消えつつあります。ショッピングセンターやスーパーのような集合商業施設にやられてしまっている現状です。酒屋だって同じ。
全国酒販組合中央会、酒屋の組合の発表した「酒販店転廃業・倒産等の実態調査」によりますと、平成10年3月から20年8月までに倒産あるいは転廃業した酒販店は53,997件で、自殺、失踪、行方不明は3,490件とある。
もともと酒販免許が守られていた平成の5年くらいまでの酒販店は130,000店。この内の40%強のお店がやめて、自殺、失踪、行方不明は2.6%にものぼる。
残っているのは60%弱と数字からはなるが、実際に酒販店としての機能をしているお店は10%くらいではないか。
もともとあった酒屋の10%しか生き残れず、2%の方々は自殺、失踪、行方不明である。これは厳し過ぎる数字ではないでしょうか。
酒屋は免許に守られていたから、努力を怠っていた。これも正解でしょう。ほんの十数年前までは、ビール1本を1円でも安くして売ると、税務署から厳しい視線を浴びていたといった、自由度の低い業界であるように、個性的な取り組みは、周りからは抹消されてしまう業界でありました。
おとなしく、地道に酒税を回すのが、国からみた最大の役目でした。お客さんも大事でしたが、税務署が恐く存在が大きかったです。こういうことは我々酒屋のみが知るところで、酒屋の努力不足を指摘する方々には想像もつかない世界であります。
税務署や組み合いの指示にしたがって、小さく商売してきたら、急に世の中が変わって、お役御免。
私の知り合いの酒屋さんの中には、業務店からの連鎖倒産あり、業務店からの強制的な保証人にさせられることあり、多額の債務を請負わされてしまった方も多く、また、いつの間にか消えてしまった方も数名います。
酒販年金が消えたことは有名な話。組合費も使い込んでしまっている人も何人もいます。みんな悪い人ではないのに、何らかの理由でしょうがなく、そうなってしまったことでしょう。
明日は我が身。
丸河屋が消えても近所の人も誰も困らないのでしょう。
配給制からはじまった、酒販免許。距離基準と人口基準で免許がおろされていました。免許に代わって、銘柄の取り合いをしているのが地酒専門店。大きな地域の販売免許のようなものです。その銘柄ほしさに、親分格にこびたり、蔵元の御機嫌をうかがって、田植えからいっしょにはじめたり、何かにしがみついている酒屋も多いです。
お客さんには銘柄をつきあわすのではなく、そのお酒があることの幸せをつきあわす。その代表がお酒とお料理の相性であるのではないでしょうか。だから私はダンチュウなどの雑誌に登場する銘柄は気にしませんし、第一ダンチュウなどの雑誌は見る気にもなりません。
自殺、失踪、行方不明の一人にならないように、自分のできることを自然にする。それが個性につながることでしょう。
酒屋だけが苦しいのではないです。お店っていう空間。大事にしたい。そう思って、なるべく個店のお店で買い物をするように心掛けています。
全国酒販組合中央会、酒屋の組合の発表した「酒販店転廃業・倒産等の実態調査」によりますと、平成10年3月から20年8月までに倒産あるいは転廃業した酒販店は53,997件で、自殺、失踪、行方不明は3,490件とある。
もともと酒販免許が守られていた平成の5年くらいまでの酒販店は130,000店。この内の40%強のお店がやめて、自殺、失踪、行方不明は2.6%にものぼる。
残っているのは60%弱と数字からはなるが、実際に酒販店としての機能をしているお店は10%くらいではないか。
もともとあった酒屋の10%しか生き残れず、2%の方々は自殺、失踪、行方不明である。これは厳し過ぎる数字ではないでしょうか。
酒屋は免許に守られていたから、努力を怠っていた。これも正解でしょう。ほんの十数年前までは、ビール1本を1円でも安くして売ると、税務署から厳しい視線を浴びていたといった、自由度の低い業界であるように、個性的な取り組みは、周りからは抹消されてしまう業界でありました。
おとなしく、地道に酒税を回すのが、国からみた最大の役目でした。お客さんも大事でしたが、税務署が恐く存在が大きかったです。こういうことは我々酒屋のみが知るところで、酒屋の努力不足を指摘する方々には想像もつかない世界であります。
税務署や組み合いの指示にしたがって、小さく商売してきたら、急に世の中が変わって、お役御免。
私の知り合いの酒屋さんの中には、業務店からの連鎖倒産あり、業務店からの強制的な保証人にさせられることあり、多額の債務を請負わされてしまった方も多く、また、いつの間にか消えてしまった方も数名います。
酒販年金が消えたことは有名な話。組合費も使い込んでしまっている人も何人もいます。みんな悪い人ではないのに、何らかの理由でしょうがなく、そうなってしまったことでしょう。
明日は我が身。
丸河屋が消えても近所の人も誰も困らないのでしょう。
配給制からはじまった、酒販免許。距離基準と人口基準で免許がおろされていました。免許に代わって、銘柄の取り合いをしているのが地酒専門店。大きな地域の販売免許のようなものです。その銘柄ほしさに、親分格にこびたり、蔵元の御機嫌をうかがって、田植えからいっしょにはじめたり、何かにしがみついている酒屋も多いです。
お客さんには銘柄をつきあわすのではなく、そのお酒があることの幸せをつきあわす。その代表がお酒とお料理の相性であるのではないでしょうか。だから私はダンチュウなどの雑誌に登場する銘柄は気にしませんし、第一ダンチュウなどの雑誌は見る気にもなりません。
自殺、失踪、行方不明の一人にならないように、自分のできることを自然にする。それが個性につながることでしょう。
酒屋だけが苦しいのではないです。お店っていう空間。大事にしたい。そう思って、なるべく個店のお店で買い物をするように心掛けています。