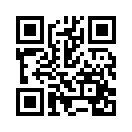2009年06月02日
きき酒テクニック4:ブレンド(合酒)
ブレンダー・・・いますね。
ウィスキーやブレンドや焼酎などの蒸留酒はブレンダーがいます。
日本酒の世界はブレンダーという役職は聞きませんね。
蔵内の人がだいたい調合はまかされますが、調合専門家はいません。
では、日本酒はブレンドしないのか?
いや、します。
一年中だいたい同じお酒の味として発売されているお酒は、
新旧のお酒をブレンドしています。
この他、例えば同じ銘柄の純米酒でも1本のタンクから瓶詰めされるものもあれば、
数本のタンクをブレンドして瓶詰めされるものもあります。
搾ってできた純米酒を全部混ぜて、瓶詰めしていけば、同じ味になります。
このように目的に応じてブレンドされることはあります。
ただ、日本酒の場合、ウィスキーなどと違うのは、いろんな原酒を混ぜて、
新しい一つの商品を作ることはまずありません。
吟醸酒と純米酒と本醸造を混ぜて、その良さを生かすといったお酒は稀です。
ないこともありませんが。
蒸留酒は品質変化が遅いですが、醸造酒は速いことが大きな理由のひとつ。
ブレンドした時点では最高でも、数ヶ月したら、最高ではなくなることもありましょう。
醸造酒は作物にあわせて、1年物としています。
前置きが長くなりました。
1年中同じ品質を保つためにブレンドされた定番酒以外、
例えば、吟醸酒の生酒などはブレンドされているかいないか?
それを見抜く方法があります。
そんなことをしている人っていないでしょうが、
きき酒して云々と言うのであれば、そういうこともわかっていなければいけません。
その方法とは!
つまみを使うとわかりやすいです。

富士宮市にあります富士高砂酒造の純米吟醸生酒。
生酒です、しかも 300ml入りですから、ブレンドされているのか?
結論から言えば、ブレンドされています。
私は見てもいないし、保証の限りではありませんが、きき酒してみて断定しちゃうのです。
人間ですから、間違っている可能性もあるとは思います。
このお酒は純米吟醸の生酒らしく、米の風味が豊かで、生酒らしい若々しい植物的な香り、
そして、フルーティーさあがあり、さらに若干熟成しているなあと思わせる干した野菜の香りがあります。
本来、香りを嗅いだ段階でブレンドしてあるとわかりますが、・・・・すすめます。
冷たい生酒に温かいおでんをあわせてみます。
おでんの温かさの影響を口中で受け、お酒の温度もあがり、ぐっといろんな要素が花開きます。
黒ハンペンとあわせます。

原料由来の米風味が強調されたかのように、黒ハンペンとあいます。
次に、黒ハンペンに辛子をつけてあわせます。

辛子と若干熟成しているなあと思わせる香りがあい、
さらにフルーティーさが顕著に現れます。
あれれ?
さっきまでは、米っぽい純吟だなあと思っていたけど、
急にフルーティーなきれいなお酒になっちゃった。
どうなってるんだあ? となるわけです。
あわせるものによって、前面に出てくるものが違ってきます。
ブレンドされた元のものの個性が出てきます。
隠し味はこういった原理を使っていますが、
ブレンドしてあるお酒も、隠し味同様に、導き出されます。
高砂純米吟醸生酒、なかなかです。
ブレンドすることによって、お料理との相性の幅が広がります。
ブレンドの妙ですね。
この他、六歌仙の吟醸(酒名)は忘れましたが、鼻で捉えた香りと、
口中で広がる香りの差が大きく、ミステリアスな逸品がありました。
これもブレンドの妙だなあと言葉を飲み込みました。
ウィスキーやブレンドや焼酎などの蒸留酒はブレンダーがいます。
日本酒の世界はブレンダーという役職は聞きませんね。
蔵内の人がだいたい調合はまかされますが、調合専門家はいません。
では、日本酒はブレンドしないのか?
いや、します。
一年中だいたい同じお酒の味として発売されているお酒は、
新旧のお酒をブレンドしています。
この他、例えば同じ銘柄の純米酒でも1本のタンクから瓶詰めされるものもあれば、
数本のタンクをブレンドして瓶詰めされるものもあります。
搾ってできた純米酒を全部混ぜて、瓶詰めしていけば、同じ味になります。
このように目的に応じてブレンドされることはあります。
ただ、日本酒の場合、ウィスキーなどと違うのは、いろんな原酒を混ぜて、
新しい一つの商品を作ることはまずありません。
吟醸酒と純米酒と本醸造を混ぜて、その良さを生かすといったお酒は稀です。
ないこともありませんが。
蒸留酒は品質変化が遅いですが、醸造酒は速いことが大きな理由のひとつ。
ブレンドした時点では最高でも、数ヶ月したら、最高ではなくなることもありましょう。
醸造酒は作物にあわせて、1年物としています。
前置きが長くなりました。
1年中同じ品質を保つためにブレンドされた定番酒以外、
例えば、吟醸酒の生酒などはブレンドされているかいないか?
それを見抜く方法があります。
そんなことをしている人っていないでしょうが、
きき酒して云々と言うのであれば、そういうこともわかっていなければいけません。
その方法とは!
つまみを使うとわかりやすいです。
富士宮市にあります富士高砂酒造の純米吟醸生酒。
生酒です、しかも 300ml入りですから、ブレンドされているのか?
結論から言えば、ブレンドされています。
私は見てもいないし、保証の限りではありませんが、きき酒してみて断定しちゃうのです。
人間ですから、間違っている可能性もあるとは思います。
このお酒は純米吟醸の生酒らしく、米の風味が豊かで、生酒らしい若々しい植物的な香り、
そして、フルーティーさあがあり、さらに若干熟成しているなあと思わせる干した野菜の香りがあります。
本来、香りを嗅いだ段階でブレンドしてあるとわかりますが、・・・・すすめます。
冷たい生酒に温かいおでんをあわせてみます。
おでんの温かさの影響を口中で受け、お酒の温度もあがり、ぐっといろんな要素が花開きます。
黒ハンペンとあわせます。
原料由来の米風味が強調されたかのように、黒ハンペンとあいます。
次に、黒ハンペンに辛子をつけてあわせます。
辛子と若干熟成しているなあと思わせる香りがあい、
さらにフルーティーさが顕著に現れます。
あれれ?
さっきまでは、米っぽい純吟だなあと思っていたけど、
急にフルーティーなきれいなお酒になっちゃった。
どうなってるんだあ? となるわけです。
あわせるものによって、前面に出てくるものが違ってきます。
ブレンドされた元のものの個性が出てきます。
隠し味はこういった原理を使っていますが、
ブレンドしてあるお酒も、隠し味同様に、導き出されます。
高砂純米吟醸生酒、なかなかです。
ブレンドすることによって、お料理との相性の幅が広がります。
ブレンドの妙ですね。

この他、六歌仙の吟醸(酒名)は忘れましたが、鼻で捉えた香りと、
口中で広がる香りの差が大きく、ミステリアスな逸品がありました。
これもブレンドの妙だなあと言葉を飲み込みました。
きき酒テクニック11:瓶香
きき酒テクニック10:グラス臭
きき酒テクニック9:瓶詰直後臭3
きき酒テクニック8:瓶詰直後臭2
きき酒テクニック7:瓶詰直後臭1.
きき酒テクニック6:生老ね(なまひね)
きき酒テクニック10:グラス臭
きき酒テクニック9:瓶詰直後臭3
きき酒テクニック8:瓶詰直後臭2
きき酒テクニック7:瓶詰直後臭1.
きき酒テクニック6:生老ね(なまひね)
Posted by 丸河屋酒店 at 20:30│Comments(0)
│きき酒テクニック