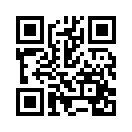2009年07月15日
きき酒テクニック11:瓶香
「この焼酎は瓶香が付いちゃったなあ」と表現されることがあります。
瓶の臭いがお酒に移ってしまったような表現です。
しかし、瓶の材質。
ガラスなどは香りがするのでしょうか?
一般的なガラスは切った断面が青っぽくなっています。
これは主成分のナトリウムの色であります。
瓶が臭うのは、材質ではなくって、他の要素であります。
洗って乾くまでに水が汚染される。
洗剤がしっかりとゆすがれていない。
つまり何か臭う物質ががくっついた臭いであります。
では、瓶香がついたと表現されるお酒は何がついているのでしょう?
それは光によって変化したお酒の香りです。
日光臭と言われますが、蛍光灯などの紫外線でもついてしまいます。
狸のおしっこや、稲の花粉にも似ています。
長期間酒販店の棚に置かれたままになっていたために、
光の影響を受けてしまったのです。
光による影響は管理の悪さを物語っています。
しかし、それをはっきりと指摘してしまうと酒販店や飲食店の立場もありません。
瓶の香とカモフラージュさせているのです。
瓶香はほとんどが日光臭であります。
瓶の臭いがお酒に移ってしまったような表現です。
しかし、瓶の材質。
ガラスなどは香りがするのでしょうか?
一般的なガラスは切った断面が青っぽくなっています。
これは主成分のナトリウムの色であります。
瓶が臭うのは、材質ではなくって、他の要素であります。
洗って乾くまでに水が汚染される。
洗剤がしっかりとゆすがれていない。
つまり何か臭う物質ががくっついた臭いであります。
では、瓶香がついたと表現されるお酒は何がついているのでしょう?
それは光によって変化したお酒の香りです。
日光臭と言われますが、蛍光灯などの紫外線でもついてしまいます。
狸のおしっこや、稲の花粉にも似ています。
長期間酒販店の棚に置かれたままになっていたために、
光の影響を受けてしまったのです。
光による影響は管理の悪さを物語っています。
しかし、それをはっきりと指摘してしまうと酒販店や飲食店の立場もありません。
瓶の香とカモフラージュさせているのです。
瓶香はほとんどが日光臭であります。
タグ :きき酒テクニック
2009年07月13日
きき酒テクニック10:グラス臭
ホテルなどの会場で着席スタイルの試飲会や試飲セミナーがあります。
各自の机の上には空のグラスが数個並べられたりしています。
講師の指示により、目の前のグラスにお酒が注がれたり、
あらかじめお酒が注がれたグラスが持ってこられます。
お酒の香りをみます。
お酒には存在していない臭いがあるときがあります。
明らかにわかる「ほこり」の臭いです。
ほこりの臭いとはっきり表現してしまいますと、
お酒を準備してくれた側の立場がなくなります。
そこでこのような場合は、「グラス臭」と表現して、
カモフラージュします。
グラスはきちんと洗ってあれば、臭いなどしません。
私はこのようなグラス臭がついてしまったお酒をコメントしなければいけない場合、
「石のような香りがあります」とか
「砂が舞う風の強い日の公園の匂い」などとしょうがなくコメントします。
あのほこりっぽい臭いはグラス臭ときき酒では表現します。
どうして臭いがついてしまうのか?
それは長期間空気に触れているからです。
ほこりと接しているからと言い換えてもいいでしょう。
各自の机の上には空のグラスが数個並べられたりしています。
講師の指示により、目の前のグラスにお酒が注がれたり、
あらかじめお酒が注がれたグラスが持ってこられます。
お酒の香りをみます。
お酒には存在していない臭いがあるときがあります。
明らかにわかる「ほこり」の臭いです。
ほこりの臭いとはっきり表現してしまいますと、
お酒を準備してくれた側の立場がなくなります。
そこでこのような場合は、「グラス臭」と表現して、
カモフラージュします。
グラスはきちんと洗ってあれば、臭いなどしません。
私はこのようなグラス臭がついてしまったお酒をコメントしなければいけない場合、
「石のような香りがあります」とか
「砂が舞う風の強い日の公園の匂い」などとしょうがなくコメントします。
あのほこりっぽい臭いはグラス臭ときき酒では表現します。
どうして臭いがついてしまうのか?
それは長期間空気に触れているからです。
ほこりと接しているからと言い換えてもいいでしょう。
タグ :きき酒テクニック
2009年07月12日
きき酒テクニック9:瓶詰直後臭3
ある蔵元に遊びに行きました。
たまたまその日に瓶詰めしたお酒がありましたので、買いました。
300mlが2本です。
その内の1本をその晩に飲みました。
何か変なんです。
お酒以外の味がするような気がしました。
その晩はおかしいなあと思っただけで、夫婦で飲んでしまいました。
翌月にもう1本を飲みましたが、今度は変な味はしません。
やっぱり、お酒の味わいはその日の体調によるなあと思いました。
それからどのくらいたったかわかりませんが、
別の蔵に遊びに行きました。
偶然なのですが、その日に瓶詰めされたお酒があるというので、
それを買わしてもらいました。
うれしくて、その晩に開けてみました。
すると、いつだったか、おぼえのある臭いと味がしました。
そこで思い出しました。
そうだ、あの時も瓶詰めしてもらったばかりのお酒だった。
でも、あの後飲んだら、変な味はしなかった。
今回のお酒も1本はすぐに飲みましたが、
2本目を開けるまでには時間をかけました。
すると、やはり変な味はしません。
美味しいお酒の味だけです。
2回も続きましたので、蔵元に相談しました。
私が変に感じていたのは、洗剤のようです。
蔵元は回収した瓶は洗ってから使います。
洗うのは機械です。
じゃあじゃあと勢いよく洗われます。
では、ゆすぎの回数はどのくらいでしょう?
私は家でグラスを洗いますが、
洗剤を落とすためのゆすぎは最低でも10回はいます。
とてもとても洗剤の臭いや味は気になります。
我が家には自動食器洗浄器もありますが、
洗剤の臭いが付いたままになって乾燥が終わるので、
私は使わず、手洗いしています。
洗剤の臭いなどは、時間がたてば、お酒という液体に溶けて、
その存在もわからなくなるでしょう。
しかし、瓶詰め直後にはこの臭いはある!
瓶につめて、その日に出荷することは稀でしょう。
しかも、それをすぐに買って飲むことも稀でしょう。
瓶もグラスと同じようなものです。
洗剤のゆすぎは気をつけて行いましょう。
たまたまその日に瓶詰めしたお酒がありましたので、買いました。
300mlが2本です。
その内の1本をその晩に飲みました。
何か変なんです。
お酒以外の味がするような気がしました。
その晩はおかしいなあと思っただけで、夫婦で飲んでしまいました。
翌月にもう1本を飲みましたが、今度は変な味はしません。
やっぱり、お酒の味わいはその日の体調によるなあと思いました。
それからどのくらいたったかわかりませんが、
別の蔵に遊びに行きました。
偶然なのですが、その日に瓶詰めされたお酒があるというので、
それを買わしてもらいました。
うれしくて、その晩に開けてみました。
すると、いつだったか、おぼえのある臭いと味がしました。
そこで思い出しました。
そうだ、あの時も瓶詰めしてもらったばかりのお酒だった。
でも、あの後飲んだら、変な味はしなかった。
今回のお酒も1本はすぐに飲みましたが、
2本目を開けるまでには時間をかけました。
すると、やはり変な味はしません。
美味しいお酒の味だけです。
2回も続きましたので、蔵元に相談しました。
私が変に感じていたのは、洗剤のようです。
蔵元は回収した瓶は洗ってから使います。
洗うのは機械です。
じゃあじゃあと勢いよく洗われます。
では、ゆすぎの回数はどのくらいでしょう?
私は家でグラスを洗いますが、
洗剤を落とすためのゆすぎは最低でも10回はいます。
とてもとても洗剤の臭いや味は気になります。
我が家には自動食器洗浄器もありますが、
洗剤の臭いが付いたままになって乾燥が終わるので、
私は使わず、手洗いしています。
洗剤の臭いなどは、時間がたてば、お酒という液体に溶けて、
その存在もわからなくなるでしょう。
しかし、瓶詰め直後にはこの臭いはある!
瓶につめて、その日に出荷することは稀でしょう。
しかも、それをすぐに買って飲むことも稀でしょう。
瓶もグラスと同じようなものです。
洗剤のゆすぎは気をつけて行いましょう。
タグ :きき酒テクニック
2009年07月09日
きき酒テクニック8:瓶詰直後臭2
静岡県清酒鑑評会のお酒をきき酒する機会が沼津でありました。
もう16年も前のこと。
1993年頃のことです。
きき酒したお酒は沼津工業技術センターの冷蔵庫にあったお酒。
鑑評会の審査のために持ち込まれたものです。
一般公開のお酒とは違っていました。
栓にラップをして栓自体が持つ香味がお酒に移らないようにしているものや、
瓶に目一杯入れてあるもの。
これは空気の入らないようにしてあるのでしょう。
やはり、勝負のお酒です。
蔵元は神経を使ってあることが、お酒をきき酒しなくとも、
瓶だけを見てもわかりました。
あるお酒の異様さに気がつきました。
まだ開封前の出品酒を開封して、瓶の上から香りを嗅ぎました。
池の臭いがしました。
グラスに注いでみても、その臭いはしばらく存在していました。
このお酒に限らず、新酒、特に鑑評会会場にてきき酒するお酒には、
この池のような臭いがあるのが目に付くことがあります。
原因として考えられるのは、瓶を洗いますと、瓶にくっ付いているの水分は
蒸発していきます。
その後、瓶は乾いて、お酒が瓶詰められます。
この乾いていく間の水分に微生物が繁殖します。
すぐ近くにあった臭いが移ることもあります。
移り香であります。
瓶が乾くと、汚染されたかどうかはわかりにくいです。
お酒という液体が瓶内に入ってきて、汚染した臭いがわかるようになったのだと思われます。
また、瓶を洗った直後から水分に対しての汚染は始まります。
洗った水気がある状態で瓶詰めしても同じことが起こります。
瓶詰めする前に、詰めるお酒でゆすぐ、つまりリンスする一手間をかけてほしいと思いました。
一般に販売されるお酒は、瓶詰めされてから直後ではないので、
このような瓶詰直後臭はなかなかないことでしょう。
更に、池のような臭いの瓶詰め直後臭の臭いのするお酒は鑑評会では賞に入りにくいでしょう。
お酒はいいのに、鑑評会では入賞しにくい蔵を「鑑評会下手」と言ったりします。
まさに、この「鑑評会下手」のお酒は池のような臭いのついていることが多いです。
次回のきき酒テクニックも瓶詰直後臭を述べます。
もう16年も前のこと。
1993年頃のことです。
きき酒したお酒は沼津工業技術センターの冷蔵庫にあったお酒。
鑑評会の審査のために持ち込まれたものです。
一般公開のお酒とは違っていました。
栓にラップをして栓自体が持つ香味がお酒に移らないようにしているものや、
瓶に目一杯入れてあるもの。
これは空気の入らないようにしてあるのでしょう。
やはり、勝負のお酒です。
蔵元は神経を使ってあることが、お酒をきき酒しなくとも、
瓶だけを見てもわかりました。
あるお酒の異様さに気がつきました。
まだ開封前の出品酒を開封して、瓶の上から香りを嗅ぎました。
池の臭いがしました。
グラスに注いでみても、その臭いはしばらく存在していました。
このお酒に限らず、新酒、特に鑑評会会場にてきき酒するお酒には、
この池のような臭いがあるのが目に付くことがあります。
原因として考えられるのは、瓶を洗いますと、瓶にくっ付いているの水分は
蒸発していきます。
その後、瓶は乾いて、お酒が瓶詰められます。
この乾いていく間の水分に微生物が繁殖します。
すぐ近くにあった臭いが移ることもあります。
移り香であります。
瓶が乾くと、汚染されたかどうかはわかりにくいです。
お酒という液体が瓶内に入ってきて、汚染した臭いがわかるようになったのだと思われます。
また、瓶を洗った直後から水分に対しての汚染は始まります。
洗った水気がある状態で瓶詰めしても同じことが起こります。
瓶詰めする前に、詰めるお酒でゆすぐ、つまりリンスする一手間をかけてほしいと思いました。
一般に販売されるお酒は、瓶詰めされてから直後ではないので、
このような瓶詰直後臭はなかなかないことでしょう。
更に、池のような臭いの瓶詰め直後臭の臭いのするお酒は鑑評会では賞に入りにくいでしょう。
お酒はいいのに、鑑評会では入賞しにくい蔵を「鑑評会下手」と言ったりします。
まさに、この「鑑評会下手」のお酒は池のような臭いのついていることが多いです。
次回のきき酒テクニックも瓶詰直後臭を述べます。
タグ :きき酒テクニック
2009年07月08日
きき酒テクニック7:瓶詰直後臭1.
何年前になりましょうか。
東京のKKRホテルにて長期熟成清酒研究会と
長期熟成清酒勉強グループの勉強会がありました。
熟成古酒とお料理との相性もみましょうと、
並々ならぬ熟成古酒を蔵元が持ち寄り、
飲食したことがありました。
私はいろんな熟成古酒を存分に味見することができました。
その中で、あれっ! と思ったお酒がありました。
北関東のとある蔵元さんの23年古酒です。
23年も熟成しているのに、華やかです。
極低温貯蔵していたからでしょう。
一同、その華やかさに驚いていました。
中には、23年古酒は偽りではないのか?
そんな疑いを持たれる蔵元さんもいました。
私は華やかですが、はじける勢いのない香りから、
これは熟成しているなあと思いました。
長期超低温熟成された果実香は落ち着きがあります。
若干輪郭がぼやけてもいます。
それと、同時に、このお酒はこの瓶に詰められて、
熟成してきたのか、との疑問を抱きました。
黒い720mlのラベルにはきちんとしたレッテルが貼ってあります。
これ自体商品であることは間違いありません。
私が疑問に思ったのは、熟成感のあるお酒の中に、
フレッシュな水のような存在があったからです。
蔵元はその席で23年くらい熟成させてきましたと説明しています。
その場で蔵元に質問はできません。
質問する代わりに、後日御蔵へうかがってよろしいでしょうかとお願いしました。
蔵元は了承してくれて、うかがうことができました。
そして、疑問に思っていたことを、勇気を出して聞いてみました。
あの時の熟成古酒はどこかに寝かせてあるものを、
勉強会のために、瓶詰めしたのではありませんか?
そうだよう。
あの前日に必要な分だけを瓶詰めしたんだよ。
やっぱりそうだったのか。
瓶を洗って、詰める前に、詰めるお酒でリンスしてくれれば、
水っぽさは出なかったのに。
瓶詰め直後は水の気配があるお酒があります。
お酒と水と出会ったばかりで、馴染んでいないからでしょう。
この蔵の場合は、水癖が出なかったからよかったです。
味わい的に感じるのに、「臭」とついています。
これは味わいであっても、「臭」とお酒の欠点を指摘する場合に使うことが多いからです。
次回のきき酒テクニックも「瓶詰め直後臭」を述べます。
東京のKKRホテルにて長期熟成清酒研究会と
長期熟成清酒勉強グループの勉強会がありました。
熟成古酒とお料理との相性もみましょうと、
並々ならぬ熟成古酒を蔵元が持ち寄り、
飲食したことがありました。
私はいろんな熟成古酒を存分に味見することができました。
その中で、あれっ! と思ったお酒がありました。
北関東のとある蔵元さんの23年古酒です。
23年も熟成しているのに、華やかです。
極低温貯蔵していたからでしょう。
一同、その華やかさに驚いていました。
中には、23年古酒は偽りではないのか?
そんな疑いを持たれる蔵元さんもいました。
私は華やかですが、はじける勢いのない香りから、
これは熟成しているなあと思いました。
長期超低温熟成された果実香は落ち着きがあります。
若干輪郭がぼやけてもいます。
それと、同時に、このお酒はこの瓶に詰められて、
熟成してきたのか、との疑問を抱きました。
黒い720mlのラベルにはきちんとしたレッテルが貼ってあります。
これ自体商品であることは間違いありません。
私が疑問に思ったのは、熟成感のあるお酒の中に、
フレッシュな水のような存在があったからです。
蔵元はその席で23年くらい熟成させてきましたと説明しています。
その場で蔵元に質問はできません。
質問する代わりに、後日御蔵へうかがってよろしいでしょうかとお願いしました。
蔵元は了承してくれて、うかがうことができました。
そして、疑問に思っていたことを、勇気を出して聞いてみました。
あの時の熟成古酒はどこかに寝かせてあるものを、
勉強会のために、瓶詰めしたのではありませんか?
そうだよう。
あの前日に必要な分だけを瓶詰めしたんだよ。
やっぱりそうだったのか。
瓶を洗って、詰める前に、詰めるお酒でリンスしてくれれば、
水っぽさは出なかったのに。
瓶詰め直後は水の気配があるお酒があります。
お酒と水と出会ったばかりで、馴染んでいないからでしょう。
この蔵の場合は、水癖が出なかったからよかったです。
味わい的に感じるのに、「臭」とついています。
これは味わいであっても、「臭」とお酒の欠点を指摘する場合に使うことが多いからです。
次回のきき酒テクニックも「瓶詰め直後臭」を述べます。
2009年07月03日
きき酒テクニック6:生老ね(なまひね)
保存管理によって、日本酒の健康状態、健全度が違ってきます。
光に当たらないように、低温で保存しておく。
新聞紙や箱に入れて、冷蔵庫の奥に立てたままの状態で置いておく。
保存管理の基礎であり、大事なことです。
しかし、このような状態でもお酒は熟成が進みます。
それは生酒でも生貯蔵酒でも生詰酒でも、二度火入れされたものでも、
すべてお酒は熟成していきます。
一度も火入れされていない生酒の熟成は面白いです。
冬に造られて、春先に出てくる生酒。
流行りは「無濾過生原酒」であります。

純米系も本醸造系もありますが、
圧倒的に純米系が多いです。
無濾過生原酒は搾った直後や発売された直後では、アルコール度が高く、
激しい感じがしたり、荒れていたりすることが多いです。
それを低温貯保存することで、落ち着いた香りと味わいになります。
夏を越え、秋も深まりますと、まったりして、枯れた感覚があります。
生酒ですから、フレッシュさもあり、時間が経ったための大人の落ち着きがあります。

平成18年ものですから、3年冷蔵保存していました。
このまったりした状態を好む方は非常に多いです。
事実、このお酒は美味しいと思います。
無濾過生原酒は活性炭濾過もせず、加水調整もしていませんから、
香味が凝縮されています。
エキス分が多いですから、時間が経つに連れて、変化していきます。
この生酒の低温保存された特有の枯れたまったり感。
きき酒用語としては、「生老ね」(なまひね)と呼びます。
生老ねと書きますと、マイナスのイメージがつきます。
これは生酒を低温保存しておけば、必ず喜ばれる香味になるとは限らないからです。
その顕著な例がカプロン酸が多く含まれているお酒です。
出来立てのカプロン酸(=へキサン酸)主体のお酒は華やかですが、
これが時間が経ちますと、飲むには耐え難い香味になるものがあります。
ドブ臭、雑巾臭などがあります。
カプはヤギ臭いことに由来しています。
ただし、カプロン酸エチルが多く、カプロン酸は微量のお酒は、
カプロン酸主体のお酒とは違って、嗜好的には好まれる、
まったりした枯れた味わいになることが多いです。
カプカプのお酒などとつぶやく方が多いですが、
カプロン酸とカプロン酸エチルの違いは押さえておきたいところです。
その上にカプリル酸エチルもあります。
カプロン酸アリルなどもあって、パイナップルの香りがして香料として使われています。
光に当たらないように、低温で保存しておく。
新聞紙や箱に入れて、冷蔵庫の奥に立てたままの状態で置いておく。
保存管理の基礎であり、大事なことです。
しかし、このような状態でもお酒は熟成が進みます。
それは生酒でも生貯蔵酒でも生詰酒でも、二度火入れされたものでも、
すべてお酒は熟成していきます。
一度も火入れされていない生酒の熟成は面白いです。
冬に造られて、春先に出てくる生酒。
流行りは「無濾過生原酒」であります。
純米系も本醸造系もありますが、
圧倒的に純米系が多いです。
無濾過生原酒は搾った直後や発売された直後では、アルコール度が高く、
激しい感じがしたり、荒れていたりすることが多いです。
それを低温貯保存することで、落ち着いた香りと味わいになります。
夏を越え、秋も深まりますと、まったりして、枯れた感覚があります。
生酒ですから、フレッシュさもあり、時間が経ったための大人の落ち着きがあります。
平成18年ものですから、3年冷蔵保存していました。
このまったりした状態を好む方は非常に多いです。
事実、このお酒は美味しいと思います。
無濾過生原酒は活性炭濾過もせず、加水調整もしていませんから、
香味が凝縮されています。
エキス分が多いですから、時間が経つに連れて、変化していきます。
この生酒の低温保存された特有の枯れたまったり感。
きき酒用語としては、「生老ね」(なまひね)と呼びます。
生老ねと書きますと、マイナスのイメージがつきます。
これは生酒を低温保存しておけば、必ず喜ばれる香味になるとは限らないからです。
その顕著な例がカプロン酸が多く含まれているお酒です。
出来立てのカプロン酸(=へキサン酸)主体のお酒は華やかですが、
これが時間が経ちますと、飲むには耐え難い香味になるものがあります。
ドブ臭、雑巾臭などがあります。
カプはヤギ臭いことに由来しています。
ただし、カプロン酸エチルが多く、カプロン酸は微量のお酒は、
カプロン酸主体のお酒とは違って、嗜好的には好まれる、
まったりした枯れた味わいになることが多いです。
カプカプのお酒などとつぶやく方が多いですが、
カプロン酸とカプロン酸エチルの違いは押さえておきたいところです。
その上にカプリル酸エチルもあります。
カプロン酸アリルなどもあって、パイナップルの香りがして香料として使われています。
タグ :きき酒テクニック
2009年06月03日
きき酒テクニック5:は桶酸化臭
お酒の瓶の中には空気が入っていたりして酸化します。
新品の場合は空気と液体の量の比から、すぐに激しく酸化することはありません。
しかしながら、瓶詰めされて、時間が少ししか経っていないのに酸化されたお酒もあります。
酸化臭があるのでわかります。
酸化による臭いの第一段階として、紙のような臭いがしてきます。
場合によっては、ひどくなりますと、ダンボールのような臭いになるのがあります。
紙のような臭いはどこでついてしまったのか?
瓶内ではないとすれば、その前であります。
その前とは貯蔵タンク内。
気の利いた蔵元は、密閉と低温でお酒を貯蔵する容器を使います。
確かに外部との接触はありませんし、低温ですから、貯蔵にはもってこいです。
でも、徐々に出荷されていくとなりますと、徐々に抜き取れらていきます。
タンク内の液体であるお酒の量は減り、空気の量は増えていきます。
ここで初期的な酸化臭がついてしまうようです。
ここから出して濾過すれば、酸化臭は取れます。
濾過をすると旨味など長所も取れてしまい、
何のためにこの重宝なタンクを使っているのか、意味がなくなってしまいます。
したがって、そのまま瓶詰めとなるわけです。
タンクの中のお酒が中途半端に入っている状態を「は桶」と呼びます。
ここから、このことが理由でついた酸化臭をは桶酸化臭(はおけさんかしゅう)と私は呼びます。
は桶酸化臭はどの本、どのサイトを見ても出てこないでしょうね。
私はズケズケ言いますが、普通は蔵元には言いにくい言葉です。
は桶酸化臭、おぼえておいてください。

新品の場合は空気と液体の量の比から、すぐに激しく酸化することはありません。
しかしながら、瓶詰めされて、時間が少ししか経っていないのに酸化されたお酒もあります。
酸化臭があるのでわかります。
酸化による臭いの第一段階として、紙のような臭いがしてきます。
場合によっては、ひどくなりますと、ダンボールのような臭いになるのがあります。
紙のような臭いはどこでついてしまったのか?
瓶内ではないとすれば、その前であります。
その前とは貯蔵タンク内。
気の利いた蔵元は、密閉と低温でお酒を貯蔵する容器を使います。
確かに外部との接触はありませんし、低温ですから、貯蔵にはもってこいです。
でも、徐々に出荷されていくとなりますと、徐々に抜き取れらていきます。
タンク内の液体であるお酒の量は減り、空気の量は増えていきます。
ここで初期的な酸化臭がついてしまうようです。
ここから出して濾過すれば、酸化臭は取れます。
濾過をすると旨味など長所も取れてしまい、
何のためにこの重宝なタンクを使っているのか、意味がなくなってしまいます。
したがって、そのまま瓶詰めとなるわけです。
タンクの中のお酒が中途半端に入っている状態を「は桶」と呼びます。
ここから、このことが理由でついた酸化臭をは桶酸化臭(はおけさんかしゅう)と私は呼びます。
は桶酸化臭はどの本、どのサイトを見ても出てこないでしょうね。
私はズケズケ言いますが、普通は蔵元には言いにくい言葉です。
は桶酸化臭、おぼえておいてください。

2009年06月02日
きき酒テクニック4:ブレンド(合酒)
ブレンダー・・・いますね。
ウィスキーやブレンドや焼酎などの蒸留酒はブレンダーがいます。
日本酒の世界はブレンダーという役職は聞きませんね。
蔵内の人がだいたい調合はまかされますが、調合専門家はいません。
では、日本酒はブレンドしないのか?
いや、します。
一年中だいたい同じお酒の味として発売されているお酒は、
新旧のお酒をブレンドしています。
この他、例えば同じ銘柄の純米酒でも1本のタンクから瓶詰めされるものもあれば、
数本のタンクをブレンドして瓶詰めされるものもあります。
搾ってできた純米酒を全部混ぜて、瓶詰めしていけば、同じ味になります。
このように目的に応じてブレンドされることはあります。
ただ、日本酒の場合、ウィスキーなどと違うのは、いろんな原酒を混ぜて、
新しい一つの商品を作ることはまずありません。
吟醸酒と純米酒と本醸造を混ぜて、その良さを生かすといったお酒は稀です。
ないこともありませんが。
蒸留酒は品質変化が遅いですが、醸造酒は速いことが大きな理由のひとつ。
ブレンドした時点では最高でも、数ヶ月したら、最高ではなくなることもありましょう。
醸造酒は作物にあわせて、1年物としています。
前置きが長くなりました。
1年中同じ品質を保つためにブレンドされた定番酒以外、
例えば、吟醸酒の生酒などはブレンドされているかいないか?
それを見抜く方法があります。
そんなことをしている人っていないでしょうが、
きき酒して云々と言うのであれば、そういうこともわかっていなければいけません。
その方法とは!
つまみを使うとわかりやすいです。

富士宮市にあります富士高砂酒造の純米吟醸生酒。
生酒です、しかも 300ml入りですから、ブレンドされているのか?
結論から言えば、ブレンドされています。
私は見てもいないし、保証の限りではありませんが、きき酒してみて断定しちゃうのです。
人間ですから、間違っている可能性もあるとは思います。
このお酒は純米吟醸の生酒らしく、米の風味が豊かで、生酒らしい若々しい植物的な香り、
そして、フルーティーさあがあり、さらに若干熟成しているなあと思わせる干した野菜の香りがあります。
本来、香りを嗅いだ段階でブレンドしてあるとわかりますが、・・・・すすめます。
冷たい生酒に温かいおでんをあわせてみます。
おでんの温かさの影響を口中で受け、お酒の温度もあがり、ぐっといろんな要素が花開きます。
黒ハンペンとあわせます。

原料由来の米風味が強調されたかのように、黒ハンペンとあいます。
次に、黒ハンペンに辛子をつけてあわせます。

辛子と若干熟成しているなあと思わせる香りがあい、
さらにフルーティーさが顕著に現れます。
あれれ?
さっきまでは、米っぽい純吟だなあと思っていたけど、
急にフルーティーなきれいなお酒になっちゃった。
どうなってるんだあ? となるわけです。
あわせるものによって、前面に出てくるものが違ってきます。
ブレンドされた元のものの個性が出てきます。
隠し味はこういった原理を使っていますが、
ブレンドしてあるお酒も、隠し味同様に、導き出されます。
高砂純米吟醸生酒、なかなかです。
ブレンドすることによって、お料理との相性の幅が広がります。
ブレンドの妙ですね。
この他、六歌仙の吟醸(酒名)は忘れましたが、鼻で捉えた香りと、
口中で広がる香りの差が大きく、ミステリアスな逸品がありました。
これもブレンドの妙だなあと言葉を飲み込みました。
ウィスキーやブレンドや焼酎などの蒸留酒はブレンダーがいます。
日本酒の世界はブレンダーという役職は聞きませんね。
蔵内の人がだいたい調合はまかされますが、調合専門家はいません。
では、日本酒はブレンドしないのか?
いや、します。
一年中だいたい同じお酒の味として発売されているお酒は、
新旧のお酒をブレンドしています。
この他、例えば同じ銘柄の純米酒でも1本のタンクから瓶詰めされるものもあれば、
数本のタンクをブレンドして瓶詰めされるものもあります。
搾ってできた純米酒を全部混ぜて、瓶詰めしていけば、同じ味になります。
このように目的に応じてブレンドされることはあります。
ただ、日本酒の場合、ウィスキーなどと違うのは、いろんな原酒を混ぜて、
新しい一つの商品を作ることはまずありません。
吟醸酒と純米酒と本醸造を混ぜて、その良さを生かすといったお酒は稀です。
ないこともありませんが。
蒸留酒は品質変化が遅いですが、醸造酒は速いことが大きな理由のひとつ。
ブレンドした時点では最高でも、数ヶ月したら、最高ではなくなることもありましょう。
醸造酒は作物にあわせて、1年物としています。
前置きが長くなりました。
1年中同じ品質を保つためにブレンドされた定番酒以外、
例えば、吟醸酒の生酒などはブレンドされているかいないか?
それを見抜く方法があります。
そんなことをしている人っていないでしょうが、
きき酒して云々と言うのであれば、そういうこともわかっていなければいけません。
その方法とは!
つまみを使うとわかりやすいです。
富士宮市にあります富士高砂酒造の純米吟醸生酒。
生酒です、しかも 300ml入りですから、ブレンドされているのか?
結論から言えば、ブレンドされています。
私は見てもいないし、保証の限りではありませんが、きき酒してみて断定しちゃうのです。
人間ですから、間違っている可能性もあるとは思います。
このお酒は純米吟醸の生酒らしく、米の風味が豊かで、生酒らしい若々しい植物的な香り、
そして、フルーティーさあがあり、さらに若干熟成しているなあと思わせる干した野菜の香りがあります。
本来、香りを嗅いだ段階でブレンドしてあるとわかりますが、・・・・すすめます。
冷たい生酒に温かいおでんをあわせてみます。
おでんの温かさの影響を口中で受け、お酒の温度もあがり、ぐっといろんな要素が花開きます。
黒ハンペンとあわせます。
原料由来の米風味が強調されたかのように、黒ハンペンとあいます。
次に、黒ハンペンに辛子をつけてあわせます。
辛子と若干熟成しているなあと思わせる香りがあい、
さらにフルーティーさが顕著に現れます。
あれれ?
さっきまでは、米っぽい純吟だなあと思っていたけど、
急にフルーティーなきれいなお酒になっちゃった。
どうなってるんだあ? となるわけです。
あわせるものによって、前面に出てくるものが違ってきます。
ブレンドされた元のものの個性が出てきます。
隠し味はこういった原理を使っていますが、
ブレンドしてあるお酒も、隠し味同様に、導き出されます。
高砂純米吟醸生酒、なかなかです。
ブレンドすることによって、お料理との相性の幅が広がります。
ブレンドの妙ですね。

この他、六歌仙の吟醸(酒名)は忘れましたが、鼻で捉えた香りと、
口中で広がる香りの差が大きく、ミステリアスな逸品がありました。
これもブレンドの妙だなあと言葉を飲み込みました。
2009年06月01日
きき酒テクニック3:しぼり癖
お客様から質問されました。
「お酒が赤いのですが、何ででしょう?」
「丸河屋さんで買ったのではなく、T屋さんで買ったSSの特別純米酒なんですが。」
「丸河屋さんで買った本きき猪口を使ったら、その色に気づきました。」
「透明なグラスだったら、わからなかったかもしれません。」
御来店いただき、そのお酒を持ってきてくれました。
その場で判断してあげたかったのですが、まだ営業中でしたので、
店のシャッターをしめてからきき酒しました。
透明なグラスに注いでみました。

写真ではわかりにくいですが、何となく赤みを帯びているようであります。
先入観なく、飲んでしまえば、気が付かないくらいの色具合です。
きき猪口に注いでみました。
本きき猪口ではない方ので確認してみました。

これも写真ではわかりにくいですが、肉眼では、
赤く色がついているなあとはっきりわかります。
きき酒してみました。
香りは生の赤い果実を思わせます。
お客様もイチゴのような香りがするとおっしゃっていました。
口に含みました。
一瞬で判明しました。
これは典型的な「しぼり癖」であります。
「袋香」(ふくろか)とも呼びます。
発酵が済んだもろみは搾られます。
袋に入れて、重力や加圧によって搾り出される方法や、
アコーディオンやじゃばらのようなやり方で、大きな機械で両横から圧力を加えて
しぼり出される方法が一般的であります。
この時使う袋状の物や板状の物に雑菌が付いていると、搾るお酒に影響します。
口の中であきらかにわかる異常な味わい。
ビリビリッと電気が走りながら、渋味を感じます。
飲むには不適格であり、私は口から吐き出してしまいました。
搾る時の癖がつくことはよくありますが、癖を取るために、
活性炭などを使って濾過します。
この蔵は、生産量と作業量との差があるために、
せっかくうまく発酵させても、最後の搾りで台無しにしてしまったようです。
ちなみに、赤みがかる理由はいくつかあります。
今回は雑菌のいたずらであるわけです。
そして、このしぼり癖を好む方もいらっしゃいます。
嗜好性の問題ですから、仕方ありません。
「お酒が赤いのですが、何ででしょう?」
「丸河屋さんで買ったのではなく、T屋さんで買ったSSの特別純米酒なんですが。」
「丸河屋さんで買った本きき猪口を使ったら、その色に気づきました。」
「透明なグラスだったら、わからなかったかもしれません。」
御来店いただき、そのお酒を持ってきてくれました。
その場で判断してあげたかったのですが、まだ営業中でしたので、
店のシャッターをしめてからきき酒しました。
透明なグラスに注いでみました。
写真ではわかりにくいですが、何となく赤みを帯びているようであります。
先入観なく、飲んでしまえば、気が付かないくらいの色具合です。
きき猪口に注いでみました。
本きき猪口ではない方ので確認してみました。
これも写真ではわかりにくいですが、肉眼では、
赤く色がついているなあとはっきりわかります。
きき酒してみました。
香りは生の赤い果実を思わせます。
お客様もイチゴのような香りがするとおっしゃっていました。
口に含みました。
一瞬で判明しました。
これは典型的な「しぼり癖」であります。
「袋香」(ふくろか)とも呼びます。
発酵が済んだもろみは搾られます。
袋に入れて、重力や加圧によって搾り出される方法や、
アコーディオンやじゃばらのようなやり方で、大きな機械で両横から圧力を加えて
しぼり出される方法が一般的であります。
この時使う袋状の物や板状の物に雑菌が付いていると、搾るお酒に影響します。
口の中であきらかにわかる異常な味わい。
ビリビリッと電気が走りながら、渋味を感じます。
飲むには不適格であり、私は口から吐き出してしまいました。
搾る時の癖がつくことはよくありますが、癖を取るために、
活性炭などを使って濾過します。
この蔵は、生産量と作業量との差があるために、
せっかくうまく発酵させても、最後の搾りで台無しにしてしまったようです。
ちなみに、赤みがかる理由はいくつかあります。
今回は雑菌のいたずらであるわけです。
そして、このしぼり癖を好む方もいらっしゃいます。
嗜好性の問題ですから、仕方ありません。
2009年05月19日
きき酒テクニック2:粉雪(淡雪)のような
お酒をわかりやすい言葉でシンプルに表現する。
格好いいですね。
きき酒テクニックと称してはじめました。
第一弾が「雪解け水のような」お酒でした。
今回は「粉雪のような」です。
「淡雪のような」とも表現してよいでしょう。

用意したのは、新潟県は小千谷市にある高の井酒造の越の初梅本醸造であります。
一度火入れした生貯蔵酒であります。
前回の雪解け水のようなと表現するお酒も新潟県産酒でありました。
雪をイメージさせるお酒は新潟とか秋田などの豪雪地域のお酒が似合います。
では、きき酒してまいりましょうか。
香り
ほのかに、ほんわかともやもやと立ち上がってきます。
マシュマロのようでもあります。
白い花、牡丹でしょうか、こんな花の様な香りも感じます。

前回の雪解け水のようなお酒で使った越後路と香りのタイプは似ています。
味
口に含みます。
口当たり、アタックは優しいです。
淡いです。
甘味を持った粉っぽさを感じます。
飲み込みましても、この甘いような粉っぽさはずっと続きます。
「雪解け水のようなお酒」と「粉雪のようなお酒」はここが違います。
ここがポイントであります!!
「雪解け水のような」お酒は柔らかさから爽快感を伴って切れていきます。
雪が溶けたかのような清涼感があります。
「粉雪のような」お酒は柔らかさから爽快感へと移らずに、
柔らかさを持ってそのまま切れていきます。
雪解け水のような(越後路)の方が切れのよい辛口に感じます。
粉雪のような(越の初梅)の方が柔らかさのある辛口に感じます。
おさらいしましょう。
もやもやっとして優しい香り。
よくこなれた米粉が舌の上にある。
終始柔らかである。
「粉雪のような」と表現するお酒の三拍子です。
今回の「粉雪のような」お酒と前回の「雪解け水のような」お酒からは
新潟県産酒特有の持ち味を感じます。
精米歩合が60%くらいの本醸造や特別本醸造に多く、
そのほとんどが生貯蔵などの一度火入れのお酒です。
越の初梅本醸造も典型的な1本であります。
格好いいですね。
きき酒テクニックと称してはじめました。
第一弾が「雪解け水のような」お酒でした。
今回は「粉雪のような」です。

「淡雪のような」とも表現してよいでしょう。
用意したのは、新潟県は小千谷市にある高の井酒造の越の初梅本醸造であります。
一度火入れした生貯蔵酒であります。
前回の雪解け水のようなと表現するお酒も新潟県産酒でありました。
雪をイメージさせるお酒は新潟とか秋田などの豪雪地域のお酒が似合います。
では、きき酒してまいりましょうか。
香り
ほのかに、ほんわかともやもやと立ち上がってきます。
マシュマロのようでもあります。
白い花、牡丹でしょうか、こんな花の様な香りも感じます。
前回の雪解け水のようなお酒で使った越後路と香りのタイプは似ています。
味
口に含みます。
口当たり、アタックは優しいです。
淡いです。
甘味を持った粉っぽさを感じます。
飲み込みましても、この甘いような粉っぽさはずっと続きます。
「雪解け水のようなお酒」と「粉雪のようなお酒」はここが違います。

ここがポイントであります!!
「雪解け水のような」お酒は柔らかさから爽快感を伴って切れていきます。
雪が溶けたかのような清涼感があります。
「粉雪のような」お酒は柔らかさから爽快感へと移らずに、
柔らかさを持ってそのまま切れていきます。
雪解け水のような(越後路)の方が切れのよい辛口に感じます。
粉雪のような(越の初梅)の方が柔らかさのある辛口に感じます。
おさらいしましょう。
もやもやっとして優しい香り。
よくこなれた米粉が舌の上にある。
終始柔らかである。
「粉雪のような」と表現するお酒の三拍子です。
今回の「粉雪のような」お酒と前回の「雪解け水のような」お酒からは
新潟県産酒特有の持ち味を感じます。
精米歩合が60%くらいの本醸造や特別本醸造に多く、
そのほとんどが生貯蔵などの一度火入れのお酒です。
越の初梅本醸造も典型的な1本であります。
2009年05月18日
きき酒テクニック1:雪解け水のような
2時間前に予告しました通りに、きき酒テクニックをはじめます。
礼 (ペコ)
きき酒テクニックは日本酒に限らず、他の酒類についても行う予定です。
気楽にやります。(ギャラをもらっているわけでもないですし)
今回のきき酒テクニックは「雪解け水のような」であります。
きれいでしょ?
格好いいでしょ?
こんな表現したいですよね。

用意されたお酒は新潟の越越後です。
美の川酒造の本醸造の生貯蔵です。
香り
ほのかに優しい感じよい香りがします。
吟醸酒のようにはっきりとしたフルーツなどが想像できる香りではありません。
何となく、いい感じが漂う。そのくらいの強さです。
優しいイメージを作っている上新粉や大福などの白い物の香りがします。
ライチやイチゴなどのフルーティーさも若干あります。
味
口に含んでみます。
口当たりは瑞々しいです。
きれいでまったく汚れのないタッチがします。
そして、米の粒子をすごく砕いた感触が舌を優しく包み込みます。
ここまでの香りと味わいで「雪」を連想させてくれます。
ここからです。
口中での出来事です。
すっきりとしていて、瑞々しく、味わいの伸びを感じます。
シャープに切れていく、アルコールらしさの清涼感があります。
ここが「水」を感じる所以です。
「雪」と「水」をあわせますと「雪水」になります。
「雪水」とするよりは「雪解け水のような」にする方がきれいでしょ。
もう一度解説しましょう。
もやもやっとして優しい香り。
よくこなれた米粉が舌の上にある。
すっきりと切れる。
「雪解け水のような」と表現するお酒の三拍子です。
「雪解け水のような」お酒は新潟や秋田などの日本海側の雪国に多いです。
しかも「本醸造」や「純米酒」に多く、その中でも「生貯蔵」に多いです。
もうひとつ加えますと、「原酒」ではありません。
原酒は搾ってから加水調整してないお酒で、アルコールが強く、
雪をイメージする感覚ではないです。
アルコール13度から16度までに多いです。
どうぞどうぞ、ご遠慮せずにお使いください。
「雪解け水のような」お酒。
お酒ではないですが、サントリー南アルプスの天然水。

その裏には、

「雪どけの味がする」とあります。
次回は「こな雪のような」のお酒の登場です。
礼 (ペコ)
きき酒テクニックは日本酒に限らず、他の酒類についても行う予定です。
気楽にやります。(ギャラをもらっているわけでもないですし)
今回のきき酒テクニックは「雪解け水のような」であります。

きれいでしょ?

格好いいでしょ?
こんな表現したいですよね。
用意されたお酒は新潟の越越後です。
美の川酒造の本醸造の生貯蔵です。
香り
ほのかに優しい感じよい香りがします。
吟醸酒のようにはっきりとしたフルーツなどが想像できる香りではありません。
何となく、いい感じが漂う。そのくらいの強さです。
優しいイメージを作っている上新粉や大福などの白い物の香りがします。
ライチやイチゴなどのフルーティーさも若干あります。
味
口に含んでみます。
口当たりは瑞々しいです。
きれいでまったく汚れのないタッチがします。
そして、米の粒子をすごく砕いた感触が舌を優しく包み込みます。
ここまでの香りと味わいで「雪」を連想させてくれます。
ここからです。
口中での出来事です。
すっきりとしていて、瑞々しく、味わいの伸びを感じます。
シャープに切れていく、アルコールらしさの清涼感があります。
ここが「水」を感じる所以です。
「雪」と「水」をあわせますと「雪水」になります。
「雪水」とするよりは「雪解け水のような」にする方がきれいでしょ。
もう一度解説しましょう。
もやもやっとして優しい香り。
よくこなれた米粉が舌の上にある。
すっきりと切れる。
「雪解け水のような」と表現するお酒の三拍子です。
「雪解け水のような」お酒は新潟や秋田などの日本海側の雪国に多いです。
しかも「本醸造」や「純米酒」に多く、その中でも「生貯蔵」に多いです。
もうひとつ加えますと、「原酒」ではありません。
原酒は搾ってから加水調整してないお酒で、アルコールが強く、
雪をイメージする感覚ではないです。
アルコール13度から16度までに多いです。
どうぞどうぞ、ご遠慮せずにお使いください。
「雪解け水のような」お酒。
お酒ではないですが、サントリー南アルプスの天然水。
その裏には、
「雪どけの味がする」とあります。
次回は「こな雪のような」のお酒の登場です。
2009年05月18日
きき酒テクニック:はじまります
お酒を飲んで、このお酒はこれこれのようでありますと、
コメントできると格好いいですね。
ただただ「美味しい」とか「辛い」とか「フルーティー」とかではつまらない。
かといって、その本人にしかわからないような形容の仕方も×。
誰もがわかる言葉で、センス良く的確に表現する。
楽なようで難しいですし、難しく考えても、ひらめきません。
まずは、よくきき酒師などが使う一般的な表現と、
その表現されるお酒を実際にきき酒するのが近道であります。
こういった教科書などはないですしね。
お酒の勉強自体、そんなに深くまで突っ込んでいるプロもいない。
知ったかぶりや、講釈師、酒通が多い中、きちんと襟を正した飲み方。
それが理想です。
きちんと襟をただせば、講釈も言わないし、人に優しい。
人に優しく、お酒にも優しいのであります。
よく、こういうこと聞きませんか?
「生酒は燗をしちゃあもったいない」
「高いお酒は燗をするともったいない」
じゃあさあ、やってみたの? って言いたくなります。
上のようになったら、なかなか人に気使いはできませんよね。
そうならないためにも、ポイントだけ押さえましょう。
そうですねえ、今から2時間後の午後8時30分に第一回目をアップします。
コメントできると格好いいですね。
ただただ「美味しい」とか「辛い」とか「フルーティー」とかではつまらない。
かといって、その本人にしかわからないような形容の仕方も×。
誰もがわかる言葉で、センス良く的確に表現する。
楽なようで難しいですし、難しく考えても、ひらめきません。
まずは、よくきき酒師などが使う一般的な表現と、
その表現されるお酒を実際にきき酒するのが近道であります。
こういった教科書などはないですしね。
お酒の勉強自体、そんなに深くまで突っ込んでいるプロもいない。
知ったかぶりや、講釈師、酒通が多い中、きちんと襟を正した飲み方。
それが理想です。
きちんと襟をただせば、講釈も言わないし、人に優しい。
人に優しく、お酒にも優しいのであります。
よく、こういうこと聞きませんか?
「生酒は燗をしちゃあもったいない」
「高いお酒は燗をするともったいない」
じゃあさあ、やってみたの? って言いたくなります。
上のようになったら、なかなか人に気使いはできませんよね。
そうならないためにも、ポイントだけ押さえましょう。
そうですねえ、今から2時間後の午後8時30分に第一回目をアップします。