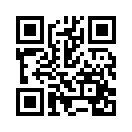2009年08月03日
カクテルの原理
お酒とお料理の相性だけでなく、飲食全般の基礎としてカクテルの原理があります。
Aという物とBという物との相性は良くないとします。
A + B = △~×
そこでAとBをあわせたい場合はどうしたらいいのでしょう?
AともBとも相性の良いCを探します。
CはAだけではなく、Bとも相性がよくなければいけません。
A + C = ○
B + C = ○
このCに仲を取り持ってもらいます。
A + C + B = ○
こうして2つだけでは相性の良くない場合、第三者に仲を取り持ってもらうことを
カクテルの法則と呼びます。
元々カクテルはこうした原理を元に作られています。
手短な誰もが経験する代表がごはんとお刺身です。
ごはんとお刺身の間にワサビ醤油が入ってもらえば、美味しいわけですね。
ワサビ醤油はワインとお刺身の仲も取り持ってくれます。


ちょっと冒険して、お刺身とスパークリングワインのロゼとあわせてみました。
鯛と赤身と高畠嘉スパークリングロゼです。
実際にあわせる前に、まずチェックです。
高畠嘉スパークリングロゼ + 醤油 = ○
高畠嘉スパークリングロゼ + ワサビ = ○
高畠嘉スパークリングロゼ + 醤油 + ワサビ = ○
高畠嘉スパークリングロゼ + 鯛・マグロの赤身のお刺身 = △
高畠嘉スパークリングロゼ + 醤油 + ワサビ + 鯛・マグロの赤身のお刺身 = ○
このように言われてみれば、あたりまえじゃん。 でしょ?
それが基礎なんですね。
Aという物とBという物との相性は良くないとします。
A + B = △~×
そこでAとBをあわせたい場合はどうしたらいいのでしょう?
AともBとも相性の良いCを探します。
CはAだけではなく、Bとも相性がよくなければいけません。
A + C = ○
B + C = ○
このCに仲を取り持ってもらいます。
A + C + B = ○
こうして2つだけでは相性の良くない場合、第三者に仲を取り持ってもらうことを
カクテルの法則と呼びます。
元々カクテルはこうした原理を元に作られています。
手短な誰もが経験する代表がごはんとお刺身です。
ごはんとお刺身の間にワサビ醤油が入ってもらえば、美味しいわけですね。
ワサビ醤油はワインとお刺身の仲も取り持ってくれます。
ちょっと冒険して、お刺身とスパークリングワインのロゼとあわせてみました。
鯛と赤身と高畠嘉スパークリングロゼです。
実際にあわせる前に、まずチェックです。
高畠嘉スパークリングロゼ + 醤油 = ○
高畠嘉スパークリングロゼ + ワサビ = ○
高畠嘉スパークリングロゼ + 醤油 + ワサビ = ○
高畠嘉スパークリングロゼ + 鯛・マグロの赤身のお刺身 = △
高畠嘉スパークリングロゼ + 醤油 + ワサビ + 鯛・マグロの赤身のお刺身 = ○
このように言われてみれば、あたりまえじゃん。 でしょ?
それが基礎なんですね。
タグ :お酒とお料理の相性
2009年08月01日
うなぎの白焼にあう日本酒
うなぎとお酒の相性研究はこれまで3度やりました。
うなぎの蒲焼にあう日本酒 うなぎの蒲焼にあうワイン うなぎの蒲焼と梅酒
うなぎは蒲焼ばかりではなく、白焼もあります。
今日はうなぎの白焼と日本酒あわせてみます。
白焼きは、うなぎを素焼きしたものです。
だから素材の良し悪しで美味しさが決まります。
うなぎを蒸してから焼いた場合はわさびを使い、
蒸さずに焼いた場合は生姜を使うと良いと思います。
これは脂分の量によりますが、いずれも焦げ目がついて、香ばしくて美味しいです。
今日のうなぎの白焼は生きているうなぎを調理しました。
うなぎ屋さんの水槽で泳いでいたうなぎであります。

うなぎの蒲焼と対比するように、脂分を蒸して落としてあります。
わさびでいただく方です。
うなぎの蒲焼とまったく違ったお料理ですね。
脂分もなく、うなぎ独特の匂いもかなり落ちています。
蒸すことと、多くのうなぎに接してきたタレではないことが理由です。
タレは新品なうす味を使ってあります。
醤油を甘くしたようであります。
同じうなぎでもうなぎの蒲焼とは違ったお酒が要求されます。
そして、幅広い日本酒とあうことでしょう。
ですから、一般的な日本酒でもかまわないのですが、
よりうなぎの白焼をうなぎの白焼らしく味わえる日本酒。
それが樽酒であります。
樽酒の杉の香りがうなぎ特有の匂いやタレにピッタリ。
ワサビがうなぎとも樽酒ともあい、すっきりさせてくれます。
後味もさわやかでうなぎも進みます。
これは他のお酒では出せない見事な調和であります。
うなぎの白焼 + 樽酒 = ◎
琺瑯タンクがなかった江戸時代はすべて樽酒のようなお酒でした。
江戸前の語源は江戸城周辺の川から獲れるうなぎのこと。
うなぎと樽酒は江戸時代を思わせてくれるノスタルジーな相性です。
うなぎと樽酒は日本を代表するカップルです。
うなぎの蒲焼にあう日本酒 うなぎの蒲焼にあうワイン うなぎの蒲焼と梅酒
うなぎは蒲焼ばかりではなく、白焼もあります。
今日はうなぎの白焼と日本酒あわせてみます。
白焼きは、うなぎを素焼きしたものです。
だから素材の良し悪しで美味しさが決まります。
うなぎを蒸してから焼いた場合はわさびを使い、
蒸さずに焼いた場合は生姜を使うと良いと思います。
これは脂分の量によりますが、いずれも焦げ目がついて、香ばしくて美味しいです。
今日のうなぎの白焼は生きているうなぎを調理しました。
うなぎ屋さんの水槽で泳いでいたうなぎであります。
うなぎの蒲焼と対比するように、脂分を蒸して落としてあります。
わさびでいただく方です。
うなぎの蒲焼とまったく違ったお料理ですね。
脂分もなく、うなぎ独特の匂いもかなり落ちています。
蒸すことと、多くのうなぎに接してきたタレではないことが理由です。
タレは新品なうす味を使ってあります。
醤油を甘くしたようであります。
同じうなぎでもうなぎの蒲焼とは違ったお酒が要求されます。
そして、幅広い日本酒とあうことでしょう。
ですから、一般的な日本酒でもかまわないのですが、
よりうなぎの白焼をうなぎの白焼らしく味わえる日本酒。
それが樽酒であります。
樽酒の杉の香りがうなぎ特有の匂いやタレにピッタリ。
ワサビがうなぎとも樽酒ともあい、すっきりさせてくれます。
後味もさわやかでうなぎも進みます。
これは他のお酒では出せない見事な調和であります。
うなぎの白焼 + 樽酒 = ◎
琺瑯タンクがなかった江戸時代はすべて樽酒のようなお酒でした。
江戸前の語源は江戸城周辺の川から獲れるうなぎのこと。
うなぎと樽酒は江戸時代を思わせてくれるノスタルジーな相性です。
うなぎと樽酒は日本を代表するカップルです。
2009年07月31日
うなぎの蒲焼と梅酒の相性
31日の今日は土用の二の丑の日ですが、
二の足を踏むでしまいそうなのが、
うなぎの蒲焼と梅酒の相性であります。
土用の丑の日に「う」の付く食べ物を食べるのがよいということもあって、
食べているうなぎ。
うなぎと梅は食べ合わせなどとも言われています。
この場合の梅は生の果実、青梅のことでしょうか。
梅干だったら、食べ合わせはおきません。
うなぎと梅は滅多に食べれない高級同士であったための戒めかもしれません。
まあまあ、そんなことも考えながら、うなぎの蒲焼と梅酒をあわせてみます。
梅酒は甘酸っぱくて、熟成感のあるお酒です。
・梅酒の「酸味」はお料理の油分に作用します。
・梅酒の「熟成感」は香ばしさ、スパイシーさによくあいます。
・梅酒の「甘味」はお料理の刺激を和らげてくれます。
したがって、梅酒にあうお料理は、油分の多い、焼いたり炒めたり蒸したりした刺激的なもの。
一方のうなぎの蒲焼は、
うなぎ由来:川の水や土と暮らす川魚類独特の匂いと風味+油っこさ+白身魚に肉の旨味
蒲焼由来:醤油主体のたれの旨味・甘味+香ばしさ
山椒由来:スパイシーさ
つまり、うなぎの蒲焼は、独特の香りと香ばしさを持った、油っぽい濃醇な味わいであります。
これらのことから、うなぎの蒲焼と梅酒は容易にあうのではと思っていました。

相性研究のために3つのタイプの梅酒を用意。
左から、黒糖梅酒、焼酎ベース梅酒、日本酒梅酒です。
まずはうなぎの蒲焼のタレと梅酒の相性をみます。
黒糖梅酒 + タレ = △〜×
甘さ + 甘さ = くどい 〜 あとから酸味が強くなる。
これだけでは辛い組み合わせです。
焼酎ベース梅酒 + タレ = ○
梅の酸とタレの甘味のバランスよし。
これは日本酒梅酒も同じです。
日本酒梅酒 + タレ = ○
次は山椒と梅酒を合わせてみます。
黒糖梅酒 + 山椒 = ○
まるで山椒は黒糖梅酒を旨くするスパイスのようであるくらいです。
焼酎ベース梅酒 + 山椒 = △〜○
いてもいなくてもいいような間柄。
いいこともしないが、悪さをすることもないです。
これは日本酒梅酒も同様です。
日本酒梅酒 + 山椒 = △〜○
うなぎの蒲焼にタレと山椒をかけて食べて、梅酒をあわせます。
黒糖梅酒 + うなぎの蒲焼 = △〜×
黒糖梅酒の存在が大きすぎて強すぎます。
ただし、黒糖梅酒の量を少なくすると、うまくまとまります。
黒糖梅酒(少量) + うなぎの蒲焼 = ◎
焼酎ベース梅酒 + うなぎの蒲焼 = ○
梅酒の程よい酸味がうなぎの蒲焼を美味しくしてくれます。
無難な相性であります。
日本酒梅酒 + うなぎの蒲焼 = △
日本酒梅酒の独特の酸味が終始リードして、それが浮いてしまう。
あわせないのが無難であります。
このようなある程度の結果がでましたが、しっくりしません。
一般的な焼酎ベースの梅酒とは無難にあうが、
これぞって感じではあうわけではない。
◎がついたのは、少量の場合の黒糖梅酒だけ。
少量ではないとしたいです。
少量は気を使って食事する必要があります。
そこで考えたのが、水割りなどです。
ロックでは氷が溶けるまでの時間が必要です。


黒糖梅酒に水割りか氷を入れた水割りなら、うなぎの蒲焼と相性がいいと思います。
二の足を踏むでしまいそうなのが、
うなぎの蒲焼と梅酒の相性であります。
土用の丑の日に「う」の付く食べ物を食べるのがよいということもあって、
食べているうなぎ。
うなぎと梅は食べ合わせなどとも言われています。
この場合の梅は生の果実、青梅のことでしょうか。
梅干だったら、食べ合わせはおきません。
うなぎと梅は滅多に食べれない高級同士であったための戒めかもしれません。
まあまあ、そんなことも考えながら、うなぎの蒲焼と梅酒をあわせてみます。
梅酒は甘酸っぱくて、熟成感のあるお酒です。
・梅酒の「酸味」はお料理の油分に作用します。
・梅酒の「熟成感」は香ばしさ、スパイシーさによくあいます。
・梅酒の「甘味」はお料理の刺激を和らげてくれます。
したがって、梅酒にあうお料理は、油分の多い、焼いたり炒めたり蒸したりした刺激的なもの。
一方のうなぎの蒲焼は、
うなぎ由来:川の水や土と暮らす川魚類独特の匂いと風味+油っこさ+白身魚に肉の旨味
蒲焼由来:醤油主体のたれの旨味・甘味+香ばしさ
山椒由来:スパイシーさ
つまり、うなぎの蒲焼は、独特の香りと香ばしさを持った、油っぽい濃醇な味わいであります。
これらのことから、うなぎの蒲焼と梅酒は容易にあうのではと思っていました。
相性研究のために3つのタイプの梅酒を用意。
左から、黒糖梅酒、焼酎ベース梅酒、日本酒梅酒です。
まずはうなぎの蒲焼のタレと梅酒の相性をみます。
黒糖梅酒 + タレ = △〜×
甘さ + 甘さ = くどい 〜 あとから酸味が強くなる。
これだけでは辛い組み合わせです。
焼酎ベース梅酒 + タレ = ○
梅の酸とタレの甘味のバランスよし。
これは日本酒梅酒も同じです。
日本酒梅酒 + タレ = ○
次は山椒と梅酒を合わせてみます。
黒糖梅酒 + 山椒 = ○
まるで山椒は黒糖梅酒を旨くするスパイスのようであるくらいです。
焼酎ベース梅酒 + 山椒 = △〜○
いてもいなくてもいいような間柄。
いいこともしないが、悪さをすることもないです。
これは日本酒梅酒も同様です。
日本酒梅酒 + 山椒 = △〜○
うなぎの蒲焼にタレと山椒をかけて食べて、梅酒をあわせます。
黒糖梅酒 + うなぎの蒲焼 = △〜×
黒糖梅酒の存在が大きすぎて強すぎます。
ただし、黒糖梅酒の量を少なくすると、うまくまとまります。
黒糖梅酒(少量) + うなぎの蒲焼 = ◎
焼酎ベース梅酒 + うなぎの蒲焼 = ○
梅酒の程よい酸味がうなぎの蒲焼を美味しくしてくれます。
無難な相性であります。
日本酒梅酒 + うなぎの蒲焼 = △
日本酒梅酒の独特の酸味が終始リードして、それが浮いてしまう。
あわせないのが無難であります。
このようなある程度の結果がでましたが、しっくりしません。
一般的な焼酎ベースの梅酒とは無難にあうが、
これぞって感じではあうわけではない。
◎がついたのは、少量の場合の黒糖梅酒だけ。
少量ではないとしたいです。
少量は気を使って食事する必要があります。
そこで考えたのが、水割りなどです。
ロックでは氷が溶けるまでの時間が必要です。
黒糖梅酒に水割りか氷を入れた水割りなら、うなぎの蒲焼と相性がいいと思います。
2009年07月27日
蜂の子にあう日本酒
我が家には2つの蜂の巣がある。
毎日観察して、自由研究のように様子を見ている。

今日は蜂の巣の様子がおかしいのである。
幼虫の蜂の子を巣から出して、ポイッと捨てている。

植木鉢の中に落ちていたりしている。

他の巣の蜂がそこの巣の蜂に成り済まして、
蜂の子を巣から出してしまっているのか?
蜂も生きていくのが大変なのだなあと思ってみていた。
ポイッと捨てられた蜂の子を拾ってみた。

どうやら生きてはいない。
そうかあ。
このところの雨で蜂の子も死んでしまったのか。
死んだ蜂の子を巣の中に入れておくと、
巣全体が腐る可能性もある。
あきらめよく捨てていたのであろう。
この3匹の蜂の子をどうすべきか?
子供らに見せたら、
女の子は「気持ち悪い」、
男の子は「かわいい」との感想。
蜂の子は食材としても珍味であって、高栄養価である。
塩をかるく振って、焼いてみた。

ははあ~ん。
食べてみる。
これで何回目か忘れましたが、蜂の子は美味しい。
火をかけましたから、ナッツのような香味があります。
そして苦味もあります。
大人の苦味です。
鮎のほろ苦味とほぼいっしょ。
鮎の黒っぽい部分が由来でしょう。
サンマの黒い身の部分とも似ています。
蜂の子は香ばしいナッツのような香ばしい味と魚のほろ苦味がします。
せっかくなので、お酒とあわせてみることに。
ナッツのような香ばしさからは日本酒の古酒を選びたい気にさせてくれます。
しかし、ほろ苦さを考えると、古酒以外にしたいところ。
山廃純米無濾過生原酒あたりもいいでしょう。
それも夏を越えた経験のあるもの。
つまり1年くらい低温熟成しているもの。
そして、樽酒にあうことでしょう。
今日は樽酒とあわせてみました。

富士錦の樽酒純米酒です。
木のような味わいが特徴の樽酒。
蜂の子のナッツのような味わいとほろ苦さが、
お酒の木のような味わいとバッチリあいます。
そもそも塩味とも樽酒はあいますし。
蜂の子を油で炒めたり、揚げたりしますと、
もっとナッツのようになります。
その場合にも樽酒があうことでしょう。
樽酒はお料理との相性からみても、
面白いお酒であります。
毎日観察して、自由研究のように様子を見ている。
今日は蜂の巣の様子がおかしいのである。
幼虫の蜂の子を巣から出して、ポイッと捨てている。
植木鉢の中に落ちていたりしている。
他の巣の蜂がそこの巣の蜂に成り済まして、
蜂の子を巣から出してしまっているのか?
蜂も生きていくのが大変なのだなあと思ってみていた。
ポイッと捨てられた蜂の子を拾ってみた。
どうやら生きてはいない。
そうかあ。
このところの雨で蜂の子も死んでしまったのか。
死んだ蜂の子を巣の中に入れておくと、
巣全体が腐る可能性もある。
あきらめよく捨てていたのであろう。
この3匹の蜂の子をどうすべきか?
子供らに見せたら、
女の子は「気持ち悪い」、
男の子は「かわいい」との感想。
蜂の子は食材としても珍味であって、高栄養価である。
塩をかるく振って、焼いてみた。
ははあ~ん。
食べてみる。
これで何回目か忘れましたが、蜂の子は美味しい。
火をかけましたから、ナッツのような香味があります。
そして苦味もあります。
大人の苦味です。
鮎のほろ苦味とほぼいっしょ。
鮎の黒っぽい部分が由来でしょう。
サンマの黒い身の部分とも似ています。
蜂の子は香ばしいナッツのような香ばしい味と魚のほろ苦味がします。
せっかくなので、お酒とあわせてみることに。
ナッツのような香ばしさからは日本酒の古酒を選びたい気にさせてくれます。
しかし、ほろ苦さを考えると、古酒以外にしたいところ。
山廃純米無濾過生原酒あたりもいいでしょう。
それも夏を越えた経験のあるもの。
つまり1年くらい低温熟成しているもの。
そして、樽酒にあうことでしょう。
今日は樽酒とあわせてみました。
富士錦の樽酒純米酒です。
木のような味わいが特徴の樽酒。
蜂の子のナッツのような味わいとほろ苦さが、
お酒の木のような味わいとバッチリあいます。
そもそも塩味とも樽酒はあいますし。
蜂の子を油で炒めたり、揚げたりしますと、
もっとナッツのようになります。
その場合にも樽酒があうことでしょう。
樽酒はお料理との相性からみても、
面白いお酒であります。
タグ :樽酒
2009年07月25日
甘口ワインにあわないお料理
おたるにあります北海道ワインの北海道ケルナースパークリングワイン。
お料理との相性の幅広さを書きました。
では、どんなものにでもあうのか?
確かに幅広いものの、すべての食べ物に対してではありません。
甘口スパークリングワインと出会わせてはいけないものは?
それは甘味が顕著なお料理です。
例えば、これ。

金目鯛の煮付けです。
醤油とみりんや砂糖などの糖分があります。
これらが魚の旨味に混じり合って美味しい一品です。
決め手は甘味と旨味。
このようなお料理とあいますと、ワインの甘味はお料理の甘味で隠れます。
そして、ワインの酸味が顕著に感じられるようになります。
金目鯛の煮付けに果実系の酸味が加わったらどうでしょう?
酸っぱさが邪魔になります。
酸っぱい金目鯛の煮付けを食べているようになります。
甘口ワインは甘味が酸味に勝っているものです。
甘いから酸味がわかりにくいですが、
必ず、酸の下支えがあります。
甘口ワインで酸の下支えがないものは、薄っぺらで、
薄い砂糖水のようです。
甘口ワインと甘いお料理はあわせてはいけません。
隠れていて丁度よい酸味が突出してしまいます。
お料理との相性の幅広さを書きました。
では、どんなものにでもあうのか?
確かに幅広いものの、すべての食べ物に対してではありません。
甘口スパークリングワインと出会わせてはいけないものは?
それは甘味が顕著なお料理です。
例えば、これ。
金目鯛の煮付けです。
醤油とみりんや砂糖などの糖分があります。
これらが魚の旨味に混じり合って美味しい一品です。
決め手は甘味と旨味。
このようなお料理とあいますと、ワインの甘味はお料理の甘味で隠れます。
そして、ワインの酸味が顕著に感じられるようになります。
金目鯛の煮付けに果実系の酸味が加わったらどうでしょう?
酸っぱさが邪魔になります。
酸っぱい金目鯛の煮付けを食べているようになります。
甘口ワインは甘味が酸味に勝っているものです。
甘いから酸味がわかりにくいですが、
必ず、酸の下支えがあります。
甘口ワインで酸の下支えがないものは、薄っぺらで、
薄い砂糖水のようです。
甘口ワインと甘いお料理はあわせてはいけません。
隠れていて丁度よい酸味が突出してしまいます。
タグ :スパークリングワイン北海道ワイン
2009年07月24日
酸っぱい白ワインにあわせるお料理
ワインに目覚めますと、飲みやすいやや甘口白ワインから入り、辛口白ワインへ。
そして、軽い赤ワインに入り、渋さのあるフルボディーな赤ワインに入っていきます。
辛口白ワインには2通りあります。
1つはシャープな酸味のあるタイプ。
これはソーヴィニオンブランなどのブドウから作られるタイプです。
もう1つはコクがあって、酸味とアルコールもあるフルボディタイプ。
これはシャルドネなどから作られるタイプです。
日本人の嗜好を見てみますと、シャルドネなどのブドウから作られる
タイプの辛口の方が人気があるようです。
シャルドネから作られたワインと日本酒と共通した点を感じるようです。
そして、「うっ!こらゃ酸っぱいわ。」と声が出るワインは苦手な方もいます。
でもですよ、この酸っぱさがとってもあうお料理があります。

焼魚です。
それも塩を多めに振ってあるものです。
ワインの酸っぱさが塩と中和するようにあうのです。
日本酒も塩とはあいますが、あまりに大量の塩では喉が渇いてきます。
ワインの酸っぱさは塩っぱさとつりあう。
そして、軽い赤ワインに入り、渋さのあるフルボディーな赤ワインに入っていきます。
辛口白ワインには2通りあります。
1つはシャープな酸味のあるタイプ。
これはソーヴィニオンブランなどのブドウから作られるタイプです。
もう1つはコクがあって、酸味とアルコールもあるフルボディタイプ。
これはシャルドネなどから作られるタイプです。
日本人の嗜好を見てみますと、シャルドネなどのブドウから作られる
タイプの辛口の方が人気があるようです。
シャルドネから作られたワインと日本酒と共通した点を感じるようです。
そして、「うっ!こらゃ酸っぱいわ。」と声が出るワインは苦手な方もいます。
でもですよ、この酸っぱさがとってもあうお料理があります。
焼魚です。
それも塩を多めに振ってあるものです。
ワインの酸っぱさが塩と中和するようにあうのです。
日本酒も塩とはあいますが、あまりに大量の塩では喉が渇いてきます。
ワインの酸っぱさは塩っぱさとつりあう。
2009年07月18日
うなぎの蒲焼にあうワイン
いよいよ明日は土用の丑の日です。
土用の丑の日くらいはうなぎを食べる方も多いでしょう。
昨晩はうなぎの蒲焼にあうお酒として、日本酒をあわせてみました。
今晩は、ワインであります。
うなぎの蒲焼を分解すると。
うなぎ由来:川の水や土と暮らす川魚類独特の匂いと風味+油っこさ+白身魚に肉の旨味
蒲焼由来:醤油主体のたれの旨味・甘味+香ばしさ
山椒由来:スパイシーさ
つまり、うなぎの蒲焼は、独特の香りと香ばしさを持った、油っぽい濃醇な味わいであります。
これに山椒が加わります。
香りが複雑になり、味はさっぱりさせてくれる方向に引っ張られます。
さて、ワイン。
うなぎの蒲焼にような油分の多くて、味が濃く、スパイシーなお料理には赤ワインを選びたいところ。
軽めの赤ワインよりも、渋味も十分なフルボディーであって、スパイシーな赤ワイン。
となりますと、カベルネソーヴィニオンやシラーなどのブドウから造ってあるワイン。
そう思って、それらの赤ワインとあわせました。
うなぎのたれ + カベルネソーヴィニオンやシラー = ◎
ワインのスパイシーさと山椒ともあいます。
山椒 + カベルネソーヴィニオンやシラー = ◎
これでうなぎの蒲焼はスパイシーさのあるフルボディーな赤ワインで決まりと思っていました。
そして、うなぎのたれと山椒のついたうなぎを食べてあわせてみたのです。
予想外にも、答えは ○ではありません。
うなぎが持つ独特の香味とあわないのです。
うなぎの味だけが孤立してしまいました。
うなぎの蒲焼(たれ・山椒) + カベルネソーヴィニオンやシラー = △
そこで、赤ワインの中でカベルネソーヴィニオンやシラーよりも渋味の少ないのを選ぼう。
そうだ! ピノノワールでいってみよう。!

ピンクや黄色みがかっていて、深い濃さの色合いではありません。
色合いからも渋味はカベルネソーヴィニオンやシラーより少ないと思えます。
うなぎのたれとあわせました。
うなぎのたれの甘味とワインの酸味が丁度バランスが取れて、甘酸っぱく美味しいです。
うなぎのたれ + ピノノワール = ◎
山椒のスパイシーさも邪魔になりません。
山椒 + ピノノワール = ○
うなぎの蒲焼とあわせました。
うなぎ自身とも違和感なくあいます。
調和していますね。
うなぎ、たれ、山椒、ワインがそれぞれの長所を持ち合って共鳴しています。
ハーモニーを奏でています。
四味一体でありますよ。
うなぎの蒲焼(たれ・山椒) + ピノノワール = ◎
これはかなりおすすめの相性です。
!今日の格言!
うなぎの蒲焼だってワインで美味しいぞ。決め手はピノノワールだ!
土用の丑の日くらいはうなぎを食べる方も多いでしょう。
昨晩はうなぎの蒲焼にあうお酒として、日本酒をあわせてみました。
今晩は、ワインであります。
うなぎの蒲焼を分解すると。
うなぎ由来:川の水や土と暮らす川魚類独特の匂いと風味+油っこさ+白身魚に肉の旨味
蒲焼由来:醤油主体のたれの旨味・甘味+香ばしさ
山椒由来:スパイシーさ
つまり、うなぎの蒲焼は、独特の香りと香ばしさを持った、油っぽい濃醇な味わいであります。
これに山椒が加わります。
香りが複雑になり、味はさっぱりさせてくれる方向に引っ張られます。
さて、ワイン。
うなぎの蒲焼にような油分の多くて、味が濃く、スパイシーなお料理には赤ワインを選びたいところ。
軽めの赤ワインよりも、渋味も十分なフルボディーであって、スパイシーな赤ワイン。
となりますと、カベルネソーヴィニオンやシラーなどのブドウから造ってあるワイン。
そう思って、それらの赤ワインとあわせました。
うなぎのたれ + カベルネソーヴィニオンやシラー = ◎
ワインのスパイシーさと山椒ともあいます。
山椒 + カベルネソーヴィニオンやシラー = ◎
これでうなぎの蒲焼はスパイシーさのあるフルボディーな赤ワインで決まりと思っていました。
そして、うなぎのたれと山椒のついたうなぎを食べてあわせてみたのです。
予想外にも、答えは ○ではありません。
うなぎが持つ独特の香味とあわないのです。
うなぎの味だけが孤立してしまいました。
うなぎの蒲焼(たれ・山椒) + カベルネソーヴィニオンやシラー = △
そこで、赤ワインの中でカベルネソーヴィニオンやシラーよりも渋味の少ないのを選ぼう。
そうだ! ピノノワールでいってみよう。!
ピンクや黄色みがかっていて、深い濃さの色合いではありません。
色合いからも渋味はカベルネソーヴィニオンやシラーより少ないと思えます。
うなぎのたれとあわせました。
うなぎのたれの甘味とワインの酸味が丁度バランスが取れて、甘酸っぱく美味しいです。
うなぎのたれ + ピノノワール = ◎
山椒のスパイシーさも邪魔になりません。
山椒 + ピノノワール = ○
うなぎの蒲焼とあわせました。
うなぎ自身とも違和感なくあいます。
調和していますね。
うなぎ、たれ、山椒、ワインがそれぞれの長所を持ち合って共鳴しています。
ハーモニーを奏でています。
四味一体でありますよ。
うなぎの蒲焼(たれ・山椒) + ピノノワール = ◎
これはかなりおすすめの相性です。
!今日の格言!
うなぎの蒲焼だってワインで美味しいぞ。決め手はピノノワールだ!
タグ :うなぎの蒲焼
2009年07月17日
うなぎの蒲焼にあう日本酒1.
うなぎったら、夏の食べ物。
そう思いがちであります。
冬は油が乗って美味しい季節らしいですよ。
好きなものはいつ食べたって美味しいものであります。
でも明後日は土用の丑の日。
さて、このうなぎの蒲焼。

お酒をあわせるのでしたら、いかがいたしましょう?

丸河屋酒店として、私はこちらをおすすめしますね。
古酒でございます。
日本酒の長期熟成酒でございます。
どうしてか?
うなぎの蒲焼を分解すると。
うなぎ由来:川の水や土と暮らす川魚類独特の匂いと風味+油っこさ+白身魚に肉の旨味
蒲焼由来:醤油主体のたれの旨味・甘味+香ばしさ
山椒由来:スパイシーさ
つまり、うなぎの蒲焼は、独特の香りと香ばしさを持った、油っぽい濃醇な味わいであります。
これに山椒が加わります。
香りが複雑になり、味はさっぱりさせてくれる方向に引っ張られます。
古酒はうなぎのたれや山椒と似ている要素が多いです。
古酒の特性は、
・まったりした濃醇な味。
・醤油を薄めた香り。
・たれのような甘味。
・香ばしい香り。
・八角などのスパーシーさ。
このように見ていきますと、うなぎの蒲焼と古酒は似たもの同士。
醤油が甘く煮詰まったタレに同じような古酒が共鳴。
タレをより複雑に美味しく演出してくれます。
香りの要素も近いものがありますから、口中でもまったく違和感がありません。
お酒とお料理のあわせ方の基本の一つに、同系をあわせるということがあります。
似たもの同士は共鳴するということです。
色からも濃い色同士であります。
古酒は醤油が甘く煮詰まったものにバッチリあう。
うなぎの油っぽい旨味が加われば、向かうところ敵なし。
うなぎの蒲焼とお酒は、まず古酒路線からスタートだ。
ただし1点だけご注意を。
うなぎの蒲焼のように濃い食べ物と古酒のように濃い飲み物を繰り返していますと、
どんどん濃くなっていきます。
古酒でも、本醸造タイプの薄口系がよいと思います。
また、おひたしのような瑞々しいものを添えながら食べることもよいですね。
!今日の格言!
うなぎの蒲焼だってお酒にあうぞ。軽快な熟成古酒でお見事。!
明日はうなぎの蒲焼とワインとあわせてみます。
そう思いがちであります。
冬は油が乗って美味しい季節らしいですよ。
好きなものはいつ食べたって美味しいものであります。
でも明後日は土用の丑の日。
さて、このうなぎの蒲焼。
お酒をあわせるのでしたら、いかがいたしましょう?
丸河屋酒店として、私はこちらをおすすめしますね。
古酒でございます。
日本酒の長期熟成酒でございます。
どうしてか?
うなぎの蒲焼を分解すると。
うなぎ由来:川の水や土と暮らす川魚類独特の匂いと風味+油っこさ+白身魚に肉の旨味
蒲焼由来:醤油主体のたれの旨味・甘味+香ばしさ
山椒由来:スパイシーさ
つまり、うなぎの蒲焼は、独特の香りと香ばしさを持った、油っぽい濃醇な味わいであります。
これに山椒が加わります。
香りが複雑になり、味はさっぱりさせてくれる方向に引っ張られます。
古酒はうなぎのたれや山椒と似ている要素が多いです。
古酒の特性は、
・まったりした濃醇な味。
・醤油を薄めた香り。
・たれのような甘味。
・香ばしい香り。
・八角などのスパーシーさ。
このように見ていきますと、うなぎの蒲焼と古酒は似たもの同士。
醤油が甘く煮詰まったタレに同じような古酒が共鳴。
タレをより複雑に美味しく演出してくれます。
香りの要素も近いものがありますから、口中でもまったく違和感がありません。
お酒とお料理のあわせ方の基本の一つに、同系をあわせるということがあります。
似たもの同士は共鳴するということです。
色からも濃い色同士であります。
古酒は醤油が甘く煮詰まったものにバッチリあう。
うなぎの油っぽい旨味が加われば、向かうところ敵なし。
うなぎの蒲焼とお酒は、まず古酒路線からスタートだ。
ただし1点だけご注意を。
うなぎの蒲焼のように濃い食べ物と古酒のように濃い飲み物を繰り返していますと、
どんどん濃くなっていきます。
古酒でも、本醸造タイプの薄口系がよいと思います。
また、おひたしのような瑞々しいものを添えながら食べることもよいですね。
!今日の格言!
うなぎの蒲焼だってお酒にあうぞ。軽快な熟成古酒でお見事。!
明日はうなぎの蒲焼とワインとあわせてみます。
2009年06月21日
梅酒とお料理の相性:ピザ
ピザは宅配でも届けてもらえますし、スーパーでも売られています。
極一般食になりました。
食卓に上ることも多いでしょう。
私もピザは大好きです。
中学1年生の時に、静岡の谷島屋書店隣にあった、
チックタックというお店で食べたのが最初。
この時の感動が今でも忘れられないくらいです。
これはスーパーから買ってきたピザであります。

オーブンで温めなおしたので、ジュージューと油分も音を立てています。
油分は下の生地が吸収しますが、けっこうな油分です。
ピザの油分は美味しさに通じてはいますが、しつこいくらいですと飽きてきます。
重くなってきます。
そういった油分を流したり、まとめたりするには、ビールやワインが合います。
他のお酒ではどうでしょう?
私は日本酒贔屓ですが、極一般的なピザで使われている香辛料とは合いません。
そこで梅酒とはどうか?
梅酒も数種類をチョイスして試しました。
結果、この上等梅酒が一番相性がいいですねえ。

それもはっきりとよさがわかるくらいの違いがつきました。
点数をつければダブルスコアーくらいまでいくでしょうね。
上等梅酒は焼酎甲類を基調として、ブランデーを加え、更にハチミツの甘さもあります。
焼酎甲類使った場合は、実際に飲むときのアルコール度は下げます。
アルコール度といっしょにすべての要素も薄まります。
梅の酸味、糖分の甘味も下がり、すっきりとしてきます。
ここが焼酎甲類で漬けた時の特徴であります。
上等梅酒の酸味がピザの油分に作用し、
上等梅酒のすっきり感が、ピザを食べ飽きさせません。
梅酒(焼酎甲類 + ブランデー隠し味) + ピザ = ◎
そして、上等梅酒の隠し味とピザのハーブや香辛料が共鳴してハーモニィーを奏でます。
この感覚って、ほんと実感してもらいたいですよ。
考えていたってわかりませんからねえ。
これからはピザにも上等梅酒が手放せないくらいです。
上等梅酒は丸河屋酒店には定番として、いつもあります。
極一般食になりました。
食卓に上ることも多いでしょう。
私もピザは大好きです。
中学1年生の時に、静岡の谷島屋書店隣にあった、
チックタックというお店で食べたのが最初。
この時の感動が今でも忘れられないくらいです。
これはスーパーから買ってきたピザであります。
オーブンで温めなおしたので、ジュージューと油分も音を立てています。
油分は下の生地が吸収しますが、けっこうな油分です。
ピザの油分は美味しさに通じてはいますが、しつこいくらいですと飽きてきます。
重くなってきます。
そういった油分を流したり、まとめたりするには、ビールやワインが合います。
他のお酒ではどうでしょう?
私は日本酒贔屓ですが、極一般的なピザで使われている香辛料とは合いません。
そこで梅酒とはどうか?
梅酒も数種類をチョイスして試しました。
結果、この上等梅酒が一番相性がいいですねえ。

それもはっきりとよさがわかるくらいの違いがつきました。
点数をつければダブルスコアーくらいまでいくでしょうね。
上等梅酒は焼酎甲類を基調として、ブランデーを加え、更にハチミツの甘さもあります。
焼酎甲類使った場合は、実際に飲むときのアルコール度は下げます。
アルコール度といっしょにすべての要素も薄まります。
梅の酸味、糖分の甘味も下がり、すっきりとしてきます。
ここが焼酎甲類で漬けた時の特徴であります。
上等梅酒の酸味がピザの油分に作用し、
上等梅酒のすっきり感が、ピザを食べ飽きさせません。
梅酒(焼酎甲類 + ブランデー隠し味) + ピザ = ◎
そして、上等梅酒の隠し味とピザのハーブや香辛料が共鳴してハーモニィーを奏でます。
この感覚って、ほんと実感してもらいたいですよ。
考えていたってわかりませんからねえ。
これからはピザにも上等梅酒が手放せないくらいです。
上等梅酒は丸河屋酒店には定番として、いつもあります。
2009年06月19日
梅酒とお料理の相性:野菜サラダ
梅酒は甘酸っぱくて、熟成感のあるお酒です。
・梅酒の「酸味」はお料理の油分に作用します。
・梅酒の「熟成感」は香ばしさ、スパイシーさによくあいます。
・梅酒の「甘味」はお料理の刺激を和らげてくれます。
したがって、梅酒にあうお料理は、油分の多い、焼いたり炒めたり蒸したりした刺激的なもの。
典型的なお料理は中華料理・中国料理となるわけです。と書きました。
これは梅酒が美味しくさせるお料理、
あるいは梅酒とお料理があってこそ美味しい組み合わせです。
これとは別にこういった考え方もできます。
梅酒を美味しくさせてくれるお料理は!
そんなテーマで選んだ一品。

それが野菜サラダであります。
シーザーサラダドレッシングをかけてみました。
甘酸っぱく濃い梅酒が瑞々しく薄まります。
甘味が気になる場合は、サラダによって、梅酒が飲みやすくなります。
梅酒 + 野菜サラダ = ◎
サラダはドレッシング選びが重要です。
果実が加わってもいけるなあと思うドレッシングなら、大丈夫でしょう。
今回使った梅酒は日本酒梅酒です。

梅酒用日本酒 360ml
氷砂糖 100g
梅 210g
通常ですと、
梅酒用日本酒 1.8L
氷砂糖 500g
梅 1キロ
梅酒としてはバランスよくできています。
ただ、お料理とあわせると甘く、濃く感じます。
まあ、それが梅酒だから、いいのですが。
梅酒用日本酒は丸河屋酒店で売っています。
・梅酒の「酸味」はお料理の油分に作用します。
・梅酒の「熟成感」は香ばしさ、スパイシーさによくあいます。
・梅酒の「甘味」はお料理の刺激を和らげてくれます。
したがって、梅酒にあうお料理は、油分の多い、焼いたり炒めたり蒸したりした刺激的なもの。
典型的なお料理は中華料理・中国料理となるわけです。と書きました。
これは梅酒が美味しくさせるお料理、
あるいは梅酒とお料理があってこそ美味しい組み合わせです。
これとは別にこういった考え方もできます。
梅酒を美味しくさせてくれるお料理は!
そんなテーマで選んだ一品。
それが野菜サラダであります。
シーザーサラダドレッシングをかけてみました。
甘酸っぱく濃い梅酒が瑞々しく薄まります。
甘味が気になる場合は、サラダによって、梅酒が飲みやすくなります。
梅酒 + 野菜サラダ = ◎
サラダはドレッシング選びが重要です。
果実が加わってもいけるなあと思うドレッシングなら、大丈夫でしょう。
今回使った梅酒は日本酒梅酒です。
梅酒用日本酒 360ml
氷砂糖 100g
梅 210g
通常ですと、
梅酒用日本酒 1.8L
氷砂糖 500g
梅 1キロ
梅酒としてはバランスよくできています。
ただ、お料理とあわせると甘く、濃く感じます。
まあ、それが梅酒だから、いいのですが。
梅酒用日本酒は丸河屋酒店で売っています。
2009年06月18日
梅酒とお料理の相性:シュウマイ
昨晩は梅酒とお料理の合わせ方の基本を書きました。
今夜は実践していきます。
2007年に仕込んだ日本酒梅酒があります。

梅酒用日本酒 360ml
果糖 72g
梅 210g
日本酒仕込みですから、和食にあうだろう。
色からしてもあいそうな、大根の煮物。

あわせてみます。
梅酒は日本のお酒ですし、大根の煮物だって・・・。
両者日本らしさがありますよね。
色からしてもあいそうです。
しかし、梅酒の酸味が浮いてしまいます。
梅酒の酸味が作用するものが大根の煮物にはないからです。
梅酒 + 大根の煮物 = ×
昨日書きました基本。
中華料理・中国料理とあわせます。
選んだのはシュウマイ。

油分が多く、焼いたり炒めたり蒸したりしています。

辛子やお醤油をつけますから、刺激的な食べ物でもあります。
辛子の刺激的さが押さえられ、辛子と梅酒の果実っぽさがあいます。
肉汁の脂っこさに、梅酒の酸味が作用してくれて、ひつっこくないです。
お醤油と梅酒の両者の熟成感が一致してきます。
梅酒 + シュウマイ(辛子・お醤油) = ◎
大変満足な組み合わせであります。
今夜は実践していきます。
2007年に仕込んだ日本酒梅酒があります。
梅酒用日本酒 360ml
果糖 72g
梅 210g
日本酒仕込みですから、和食にあうだろう。
色からしてもあいそうな、大根の煮物。
あわせてみます。
梅酒は日本のお酒ですし、大根の煮物だって・・・。
両者日本らしさがありますよね。
色からしてもあいそうです。
しかし、梅酒の酸味が浮いてしまいます。
梅酒の酸味が作用するものが大根の煮物にはないからです。
梅酒 + 大根の煮物 = ×
昨日書きました基本。
中華料理・中国料理とあわせます。
選んだのはシュウマイ。
油分が多く、焼いたり炒めたり蒸したりしています。
辛子やお醤油をつけますから、刺激的な食べ物でもあります。
辛子の刺激的さが押さえられ、辛子と梅酒の果実っぽさがあいます。
肉汁の脂っこさに、梅酒の酸味が作用してくれて、ひつっこくないです。
お醤油と梅酒の両者の熟成感が一致してきます。
梅酒 + シュウマイ(辛子・お醤油) = ◎
大変満足な組み合わせであります。
タグ :梅酒とお料理の相性
2009年06月17日
梅酒とお料理の相性
梅酒とお料理の相性、つまり梅酒にあわせるお料理をみていきましょう。
梅酒は食前酒にもいいですし、食後酒にもいいですよね。
甘味と酸っぱさから食事中には向いていないのでは?
とお考えの方もいらっしゃるでしょう。
そんな???のことをやってみるのが、私であります。
梅酒にはどんなお料理がお似合いなんでしょう。
ポイントです。
梅酒は甘酸っぱくて、熟成感のあるお酒です。
・梅酒の「酸味」はお料理の油分に作用します。
・梅酒の「熟成感」は香ばしさ、スパイシーさによくあいます。
・梅酒の「甘味」はお料理の刺激を和らげてくれます。
したがって、梅酒にあうお料理は、油分の多い、焼いたり炒めたり蒸したりした刺激的なもの。
となりますと、典型的なお料理は中華料理・中国料理となるわけです。
中華料理・中国料理全般に幅広く相性の良い梅酒であります。
ここが基本線でありますが、中華料理・中国料理以外では、
ピザ、サンマのホイル焼き。餃子にもバッチリです。
この他、梅酒の濃さを弱くするサラダのような瑞々しいものともあいます。
梅酒は食前酒にもいいですし、食後酒にもいいですよね。
甘味と酸っぱさから食事中には向いていないのでは?
とお考えの方もいらっしゃるでしょう。
そんな???のことをやってみるのが、私であります。
梅酒にはどんなお料理がお似合いなんでしょう。
ポイントです。

梅酒は甘酸っぱくて、熟成感のあるお酒です。
・梅酒の「酸味」はお料理の油分に作用します。
・梅酒の「熟成感」は香ばしさ、スパイシーさによくあいます。
・梅酒の「甘味」はお料理の刺激を和らげてくれます。
したがって、梅酒にあうお料理は、油分の多い、焼いたり炒めたり蒸したりした刺激的なもの。
となりますと、典型的なお料理は中華料理・中国料理となるわけです。
中華料理・中国料理全般に幅広く相性の良い梅酒であります。
ここが基本線でありますが、中華料理・中国料理以外では、
ピザ、サンマのホイル焼き。餃子にもバッチリです。
この他、梅酒の濃さを弱くするサラダのような瑞々しいものともあいます。
タグ :梅酒とお料理の相性
2009年05月09日
日本酒を必要としない食物
今夜もおぼえておくと便利なひとつを。
お酒とお料理の相性についてです。
日本酒こそが世界中のお酒で一番幅広くお料理と相性が良いです。
日本酒はお料理に対しては、八方美人であります。
そんな日本酒でもあわせない方がよい食物として、
日本酒を破壊する食物について昨晩書きました。
おさらい。
5つの基本味は「甘味」、「酸味」、「塩(辛)味」、「苦味」、「旨味」です。
日本酒はこの5つの内の中で、もっとも特徴的なのは「甘味」と「旨味」です。
食物の中には、この2つの「甘味」と「旨味」を味覚上破壊するものや、
この2つの味覚が必要としていないものがある。
今夜は日本酒の特徴である「甘味」と「旨味」を必要としない食物の話です。

かぼちゃのチーズ焼きです。
茹でたかぼちゃにチーズが包むように焼き、パン粉を振りました。
もう、甘味と旨味がびっしり詰まった、美味しい一品であります。
かぼちゃのチーズ焼きを食べて、日本酒を飲むとどうなるのか?
重苦しくなります。
濃すぎます。
かぼちゃだけでも甘味と旨味がたっぷりあるのに、その上に日本酒の甘味と旨味が加わります。
日本酒の甘味はかぼちゃの甘味で消される効果はありますが、
旨味は打ち消しあうのではなく、重なってきます。
かぼちゃのチーズ焼き + 日本酒 = ×
旨味がいくつもに重なると、重苦しくなります。
濃厚すぎる旨味のある美味しい食物と日本酒はあわせない方がいいでしょう。
ここでご注意を!
かぼちゃが日本酒にあわないということはないです。
調理法によって様々であります。
かぼちゃの煮っ転がしは酸味も感じられ、ごはんを食べたくなります。
ごはんを食べたくなるお料理は日本酒にあいます。
そして、一手間かけただけで、日本酒にあうようにも工夫できます。

かぼちゃを裏ごしして、プルーンとあえました。
これだけで、やや果実香がする日本酒とはばっちりな相性になりました。
昨晩は日本酒を破壊する食べものについてお伝えしました。
一昨晩は日本酒とお料理のあわせ方王道をお伝えしました。

お酒とお料理の相性についてです。
日本酒こそが世界中のお酒で一番幅広くお料理と相性が良いです。
日本酒はお料理に対しては、八方美人であります。
そんな日本酒でもあわせない方がよい食物として、
日本酒を破壊する食物について昨晩書きました。
おさらい。
5つの基本味は「甘味」、「酸味」、「塩(辛)味」、「苦味」、「旨味」です。
日本酒はこの5つの内の中で、もっとも特徴的なのは「甘味」と「旨味」です。
食物の中には、この2つの「甘味」と「旨味」を味覚上破壊するものや、
この2つの味覚が必要としていないものがある。
今夜は日本酒の特徴である「甘味」と「旨味」を必要としない食物の話です。
かぼちゃのチーズ焼きです。
茹でたかぼちゃにチーズが包むように焼き、パン粉を振りました。
もう、甘味と旨味がびっしり詰まった、美味しい一品であります。
かぼちゃのチーズ焼きを食べて、日本酒を飲むとどうなるのか?
重苦しくなります。
濃すぎます。
かぼちゃだけでも甘味と旨味がたっぷりあるのに、その上に日本酒の甘味と旨味が加わります。
日本酒の甘味はかぼちゃの甘味で消される効果はありますが、
旨味は打ち消しあうのではなく、重なってきます。
かぼちゃのチーズ焼き + 日本酒 = ×
旨味がいくつもに重なると、重苦しくなります。
濃厚すぎる旨味のある美味しい食物と日本酒はあわせない方がいいでしょう。
ここでご注意を!

かぼちゃが日本酒にあわないということはないです。
調理法によって様々であります。
かぼちゃの煮っ転がしは酸味も感じられ、ごはんを食べたくなります。
ごはんを食べたくなるお料理は日本酒にあいます。
そして、一手間かけただけで、日本酒にあうようにも工夫できます。
かぼちゃを裏ごしして、プルーンとあえました。
これだけで、やや果実香がする日本酒とはばっちりな相性になりました。
昨晩は日本酒を破壊する食べものについてお伝えしました。
一昨晩は日本酒とお料理のあわせ方王道をお伝えしました。
2009年05月08日
日本酒を破壊する食物
昨晩に引き続き、今夜もこの時間にお伝えします。
お酒とお料理の相性についてです。
これもおぼえておくと便利なひとつです。
お料理との相性のよい日本酒。
世界中のお酒で一番幅広くお料理との相性は良いのです。
幅が狭いほど、決定的にあうのがあります。
日本酒はお料理に対しては、八方美人であります。
そんな重宝な日本酒ではありますが、
あわない食物、あわせない方がよい食物があります。
5つの基本味は「甘味」、「酸味」、「塩(辛)味」、「苦味」、「旨味」です。
日本酒はこの5つの内の中で、もっとも特徴的なのは「甘味」と「旨味」です。
食物の中には、この2つの「甘味」と「旨味」を味覚上破壊するものや、
この2つの味覚が必要としていないものがあります。
まず、甘味を破壊してしまう組み合わせです。

牡丹餅・おはぎであります。
小豆の甘さが特徴です。
牡丹餅・おはぎを食べてから日本酒を飲みますとどうなるのか?
日本酒が酸っぱくなります。
美味しいお酒なのにもったいない。
痛んだお酒と勘違いされそうです。
これは、最初に口にした牡丹餅・おはぎの甘さの存在があまりに大きく、
日本酒を口にしても、日本酒の持ち味の甘味は認識されません。
日本酒から甘味を引いた味が感じられます。
日本酒の甘味が牡丹餅・おはぎの甘味に破壊されているような味覚になります。
どんな味か・・・・酸っぱいです。
酸っぱさを演出する酸味とアミノ酸味が浮いてしまいます。
日本酒 + 牡丹餅・おはぎ = ×
甘味の多い食物と日本酒はあわせない方がいいですね。
昨晩は日本酒とお料理のあわせ方王道をお伝えしました。
お酒とお料理の相性についてです。
これもおぼえておくと便利なひとつです。

お料理との相性のよい日本酒。
世界中のお酒で一番幅広くお料理との相性は良いのです。
幅が狭いほど、決定的にあうのがあります。
日本酒はお料理に対しては、八方美人であります。
そんな重宝な日本酒ではありますが、
あわない食物、あわせない方がよい食物があります。
5つの基本味は「甘味」、「酸味」、「塩(辛)味」、「苦味」、「旨味」です。
日本酒はこの5つの内の中で、もっとも特徴的なのは「甘味」と「旨味」です。
食物の中には、この2つの「甘味」と「旨味」を味覚上破壊するものや、
この2つの味覚が必要としていないものがあります。
まず、甘味を破壊してしまう組み合わせです。
牡丹餅・おはぎであります。
小豆の甘さが特徴です。
牡丹餅・おはぎを食べてから日本酒を飲みますとどうなるのか?
日本酒が酸っぱくなります。
美味しいお酒なのにもったいない。
痛んだお酒と勘違いされそうです。
これは、最初に口にした牡丹餅・おはぎの甘さの存在があまりに大きく、
日本酒を口にしても、日本酒の持ち味の甘味は認識されません。
日本酒から甘味を引いた味が感じられます。
日本酒の甘味が牡丹餅・おはぎの甘味に破壊されているような味覚になります。
どんな味か・・・・酸っぱいです。
酸っぱさを演出する酸味とアミノ酸味が浮いてしまいます。
日本酒 + 牡丹餅・おはぎ = ×
甘味の多い食物と日本酒はあわせない方がいいですね。
昨晩は日本酒とお料理のあわせ方王道をお伝えしました。
2009年05月07日
日本酒とお料理のあわせ方:王道
これを知っておくと便利です。
三日連続でこの時間にお伝えしてみます。
お酒とお料理の相性研究です。
その第一話は日本酒とお料理のあわせ方の王道。
日本酒ってお酒類の中でも料理との相性はすこぶる良いとされています。
どうしてでしょう?
それは日本酒がごはんのような存在であるからです。
ごはんとあわないお料理も珍しいですしね。
お料理にあうから主食としての地位を確立しているのです。
日本酒はごはんのような存在。
詳しく説明していきましょう。
「おむすび」ってたいがい温かくはないですよね。
冷たくても美味しいです。
「おむすび」といっしょに食べたいお料理。
あるいは、「おむすび」の中に入れて食べれるものは、
日本酒の冷やにあいます。
温かいごはんの上に乗っけて食べたいものは、
燗酒と相性がいいです。
そうなんですよ!
冷たいおむすび = 冷や
温かいごはん = 燗
これは基本中の基本でありますから、
飲まない方もおぼえてほしいことであります。

三日連続でこの時間にお伝えしてみます。
お酒とお料理の相性研究です。
その第一話は日本酒とお料理のあわせ方の王道。
日本酒ってお酒類の中でも料理との相性はすこぶる良いとされています。
どうしてでしょう?
それは日本酒がごはんのような存在であるからです。
ごはんとあわないお料理も珍しいですしね。
お料理にあうから主食としての地位を確立しているのです。
日本酒はごはんのような存在。
詳しく説明していきましょう。
「おむすび」ってたいがい温かくはないですよね。
冷たくても美味しいです。
「おむすび」といっしょに食べたいお料理。
あるいは、「おむすび」の中に入れて食べれるものは、
日本酒の冷やにあいます。
温かいごはんの上に乗っけて食べたいものは、
燗酒と相性がいいです。
そうなんですよ!
冷たいおむすび = 冷や
温かいごはん = 燗
これは基本中の基本でありますから、
飲まない方もおぼえてほしいことであります。
2009年04月28日
ポテトチップの恋人
酒屋が企画して作ったポテトチップ。
酒屋でしか売っていない美味しいポテトチップ。
鈴代商店さんがリーダーとなっている遠州夢倶楽部の製品です。

美味しさの秘密は「浜名湖産ののり」「焼津海洋深層水の塩」「化学調味料無添加」と
何と言っても「三方原男爵ポテト」を使っていることでしょう。
ジャガイモって北海道を連想しますが、
三方原は料理の世界ではすこぶる良質だと有名であります。
日本一と評する方も多いようです。
このポテトチップも三方原のジャガイモを有名にした恩人であります。
恩芋ですね。

さあ、3時のおやつに食べましょう。
ザザッとお皿に出して、ポロポリポリ。

表示に偽りなし。
のりがたくさん使ってありますね。
塩とのりは相性がいいです。
海の仲間ですものね。
さてさて、この美味しいポテトチップに限らず、ポテトチップを食べる時には、
何が恋しくなりますか?
水でしょうか、コーラでしょうか、お茶もいいでしょう。
私の場合はこれです。

ミルク、牛乳でありますよ。
適度な塩加減の乾き物には牛乳があうと思います。
カルビーのかっぱえびせんもしかり。
しょっぱさと油っぽさが水分をほしがりますね。
牛乳もほどよい塩で美味しくなります。
ポテトチップの塩味も油分も牛乳によって、まろやかになります。
塩の刺激が丁度良いタイミングで消えます。
ポテトチップ + 牛乳 = ◎
水分が欲しくなるポテトチップが牛乳でまろやかに潤い、
牛乳がポテトチップの塩分で美味しくなります。
ポテトチップ、牛乳、ポテトチップ、牛乳とどこまでも続きます。
ポテトチップと牛乳は相思相愛なのですね。
私の脳は本能的にほしがるようです。
コーラも油分や塩分を流してくれますから、すっきりしてあうとは思います。
しかし、炭酸が塩分を誇張し、少し塩辛く刺激的になることと、
ポテトチップの塩分と油分がコーラの甘さを引き出し、
後味が甘くなることもあります。
後味が甘いから、また塩分のあるポテトチップへといくわけですね。
コーラの甘さが気にならない方にとっては、
ポテトチップ + コーラ = ◎
コーラの甘さが気になるなあという方には、
ポテトチップ + コーラ = ○
いかがでしょうか?
あなたのお気に入りも教えてほしいなあと思います。
酒屋でしか売っていない美味しいポテトチップ。
鈴代商店さんがリーダーとなっている遠州夢倶楽部の製品です。
美味しさの秘密は「浜名湖産ののり」「焼津海洋深層水の塩」「化学調味料無添加」と
何と言っても「三方原男爵ポテト」を使っていることでしょう。
ジャガイモって北海道を連想しますが、
三方原は料理の世界ではすこぶる良質だと有名であります。
日本一と評する方も多いようです。
このポテトチップも三方原のジャガイモを有名にした恩人であります。
恩芋ですね。
さあ、3時のおやつに食べましょう。
ザザッとお皿に出して、ポロポリポリ。
表示に偽りなし。
のりがたくさん使ってありますね。
塩とのりは相性がいいです。
海の仲間ですものね。
さてさて、この美味しいポテトチップに限らず、ポテトチップを食べる時には、
何が恋しくなりますか?
水でしょうか、コーラでしょうか、お茶もいいでしょう。
私の場合はこれです。
ミルク、牛乳でありますよ。
適度な塩加減の乾き物には牛乳があうと思います。
カルビーのかっぱえびせんもしかり。
しょっぱさと油っぽさが水分をほしがりますね。
牛乳もほどよい塩で美味しくなります。
ポテトチップの塩味も油分も牛乳によって、まろやかになります。
塩の刺激が丁度良いタイミングで消えます。
ポテトチップ + 牛乳 = ◎
水分が欲しくなるポテトチップが牛乳でまろやかに潤い、
牛乳がポテトチップの塩分で美味しくなります。
ポテトチップ、牛乳、ポテトチップ、牛乳とどこまでも続きます。
ポテトチップと牛乳は相思相愛なのですね。
私の脳は本能的にほしがるようです。
コーラも油分や塩分を流してくれますから、すっきりしてあうとは思います。
しかし、炭酸が塩分を誇張し、少し塩辛く刺激的になることと、
ポテトチップの塩分と油分がコーラの甘さを引き出し、
後味が甘くなることもあります。
後味が甘いから、また塩分のあるポテトチップへといくわけですね。
コーラの甘さが気にならない方にとっては、
ポテトチップ + コーラ = ◎
コーラの甘さが気になるなあという方には、
ポテトチップ + コーラ = ○
いかがでしょうか?
あなたのお気に入りも教えてほしいなあと思います。
2009年03月12日
春野菜にあわせるお酒
春の旬な食べ物は苦味を感じます。
まだまだ食物は少ない時期、
甘い香りなどをさせたら、
動物や昆虫の注目の的。
苦味成分を多くして、自分自身を守っているかのようです。
しかしながら、人間は普段適度に食べて生きているもの。
食料がなければ、少々のものでもチャレンジして、
食べ物に換えてしまいます。
そういった流れとしても、春の旬は受け継がれているような気がします。
また、苦味は体の毒消しなのかもしれません。
体も冬型から夏型への移行。
その間に春の食材があります。
苦味がキーポイントの食べ物は、子供の頃は苦手でした。
ところが、経験なのか、老化なのか、わかりませんが、
40代に入ったら、苦味が苦手ではなくなってきました。
ふきのとうも慣れてきて、美味しく感じている一つです。
春野菜の代表として、ふきのとうを使ったおつまみです。

さっと茹でて、辛子酢味噌をつけて、海苔で巻きました。

これは茹でて、マヨネーズをつけ、海苔で巻き、山掛けに載せました。
ポン酢をかけたら、とっても美味しいおつまみになりました。
これらはどのようなお酒にあうのか?
旬な食材に旬なお酒。
しぼりたて生ですよ。
はつしぼり、あらばしり、しぼりたての表示があるお酒です。


君盃の初しぼりは本醸造をしぼったまんま。
君盃のあらばしりは純米酒をしぼったまんま。
しぼって間もない生酒には、後から抜けていく味わいがまだあります。
抜けるとまろやかになると言われます。
若さゆえに若干荒々しいところが感じられる。
勢いがあって、力強さと感じられます。
荒々しさには苦味が伴います。
口の中に入ってから、飲み込んだ後の後味まで苦味は存在感があります。
このフレッシュさゆえの荒々しい苦味が、春の旬な食材にあうわけですよ。
!今日の格言!
春野菜 苦味も旨味に 春の酒。
まだまだ食物は少ない時期、
甘い香りなどをさせたら、
動物や昆虫の注目の的。
苦味成分を多くして、自分自身を守っているかのようです。
しかしながら、人間は普段適度に食べて生きているもの。
食料がなければ、少々のものでもチャレンジして、
食べ物に換えてしまいます。
そういった流れとしても、春の旬は受け継がれているような気がします。
また、苦味は体の毒消しなのかもしれません。
体も冬型から夏型への移行。
その間に春の食材があります。
苦味がキーポイントの食べ物は、子供の頃は苦手でした。
ところが、経験なのか、老化なのか、わかりませんが、
40代に入ったら、苦味が苦手ではなくなってきました。
ふきのとうも慣れてきて、美味しく感じている一つです。
春野菜の代表として、ふきのとうを使ったおつまみです。
さっと茹でて、辛子酢味噌をつけて、海苔で巻きました。
これは茹でて、マヨネーズをつけ、海苔で巻き、山掛けに載せました。
ポン酢をかけたら、とっても美味しいおつまみになりました。
これらはどのようなお酒にあうのか?
旬な食材に旬なお酒。
しぼりたて生ですよ。
はつしぼり、あらばしり、しぼりたての表示があるお酒です。


君盃の初しぼりは本醸造をしぼったまんま。
君盃のあらばしりは純米酒をしぼったまんま。
しぼって間もない生酒には、後から抜けていく味わいがまだあります。
抜けるとまろやかになると言われます。
若さゆえに若干荒々しいところが感じられる。
勢いがあって、力強さと感じられます。
荒々しさには苦味が伴います。
口の中に入ってから、飲み込んだ後の後味まで苦味は存在感があります。
このフレッシュさゆえの荒々しい苦味が、春の旬な食材にあうわけですよ。
!今日の格言!
春野菜 苦味も旨味に 春の酒。
2009年03月03日
ポン酢と白ワインの相性
酢はワインとは相性の悪い調味料であります。
ワイン酢の代表格として、ワインにわりとあうバルサミコ酢がありますが、
これは酢(酢酸)ではなく、その他のものも混ぜてある調味料であります。
商品名の酢ではなく、純粋な酢はワインにあわないものです。
酸味がえぐくなります。
バルサミコ酢と同様に、酢に何かが加わりますと、ワインと相性がよくなります。
日本の調味料の代表格の醤油。
醤油も酢とワインとの相性を良くしてくれます。
不思議で重宝な調味料。
神様からの贈り物のようです。
酢と醤油があわさった調味料としてポン酢があります。
たいていのポン酢は柑橘系の果実の果汁も入っております。
ミツカンのポン酢である味ぽん。

ラベルからも何でもよしの万能調味料と記されています。
一般的という理由からミツカン味ぽんを使ってワインとあわせます。
あわせるワインは日本を代表する勝沼のルバイヤート。
ルバイヤート甲州シュールリーであります。
春巻きとあわせます。

春巻きに味ぽんをつけます。

シャキシャキした春巻きの中味はチーズとシソであります。
何かを付けないと脂っこいですね。
いくらシソが入っていても、そうそうは食べれないですよ。
春巻きがポン酢で爽やかになり、ワインの登場でより爽やかに旨味がパワーアップ。
ワインとチーズがあいます。
白ワインはシソとも共鳴し、一段と爽やかにさせてくれます。
白ワイン + 酢 = ×
酸味と苦味が強く出て、耐えられない。
白ワイン + 醤油 = △
ワインの酸味が浮き、醤油と交じり合わない。
白ワイン + ポン酢(酢+醤油) = ◎
さわやかに明るくなる好相性。
この特性が生きているので、美味しいなあとなります。
魚介類の生ものもポン酢で白ワインともあいます。

!今日の格言!
ポン酢は万能調味料。白ワインにもポン酢です。!
ワイン酢の代表格として、ワインにわりとあうバルサミコ酢がありますが、
これは酢(酢酸)ではなく、その他のものも混ぜてある調味料であります。
商品名の酢ではなく、純粋な酢はワインにあわないものです。
酸味がえぐくなります。
バルサミコ酢と同様に、酢に何かが加わりますと、ワインと相性がよくなります。
日本の調味料の代表格の醤油。
醤油も酢とワインとの相性を良くしてくれます。
不思議で重宝な調味料。
神様からの贈り物のようです。
酢と醤油があわさった調味料としてポン酢があります。
たいていのポン酢は柑橘系の果実の果汁も入っております。
ミツカンのポン酢である味ぽん。
ラベルからも何でもよしの万能調味料と記されています。
一般的という理由からミツカン味ぽんを使ってワインとあわせます。
あわせるワインは日本を代表する勝沼のルバイヤート。
ルバイヤート甲州シュールリーであります。
春巻きとあわせます。
春巻きに味ぽんをつけます。
シャキシャキした春巻きの中味はチーズとシソであります。
何かを付けないと脂っこいですね。
いくらシソが入っていても、そうそうは食べれないですよ。
春巻きがポン酢で爽やかになり、ワインの登場でより爽やかに旨味がパワーアップ。
ワインとチーズがあいます。
白ワインはシソとも共鳴し、一段と爽やかにさせてくれます。
白ワイン + 酢 = ×
酸味と苦味が強く出て、耐えられない。
白ワイン + 醤油 = △
ワインの酸味が浮き、醤油と交じり合わない。
白ワイン + ポン酢(酢+醤油) = ◎
さわやかに明るくなる好相性。
この特性が生きているので、美味しいなあとなります。
魚介類の生ものもポン酢で白ワインともあいます。
!今日の格言!
ポン酢は万能調味料。白ワインにもポン酢です。!
2009年02月26日
からし蓮根には焼酎を
熊本土産のからし蓮根。
からし蓮根ったら熊本。
熊本ったらからし蓮根。
熊本名物元祖森からし蓮根であります。

平五郎さんが麦味噌と和からしを混ぜて蓮根の穴に詰め、
麦粉と空豆粉と卵黄を混ぜた衣を着せて、菜種油で揚げて作ったのがはじまり。
明治維新まで門外不出の藩の珍味栄養食。
ありがたくいただきます。
そのままいただいても美味しいです。
辛子が効いていて、辛いです。
そのままいただいた後は、辛子と相性が良いマヨネーズと醤油をつけていただきした。

マヨネーズの油が辛子にも蓮根にもまとわりつき、
まろやかにしてくれます。
そこに醤油があるわけですよ。
辛子と醤油もバッチリ。
マヨネーズと醤油もバッチリ。
辛子 + マヨネーズ = ○
辛子 + 醤油 = ○
醤油 + マヨネーズ = ○
辛子 + マヨネーズ + 醤油 = ◎
辛子とマヨネーズと醤油のハーモニーは素敵です。
ユニゾンではなく、ハモっています。
2つのハーモニーより3つのハーモニーの方が聞こえが良いことからも、
辛子とマヨネーズと醤油の相性はいいわけです。
そこに揚げた蓮根が加わっているのですから、美味しいに決まってますよ。
蓮根(揚げる) + 辛子 + マヨネーズ + 醤油 = ◎
からし蓮根にまろやかさと少々の甘酸っぱさと香ばしさが加わり、旨味が増大。
旨い旨いってなります。
ごはんのおかずにもよいとは思いますが、
これはお酒のおつまみの方がよいと勝手に決めました。
さて、せっかくのからし蓮根です。
球磨焼酎とあわせるのがセオリー。
長期熟成の桜の里とあわせました。

見るからに古い焼酎でしょ。
からし蓮根とあわせるお酒としては、焼酎ならば、たいていはいいでしょう。
日本酒は不向きです。
辛さが極まって、食べにくくなります。
桜の里はピリピリッと香辛料的な刺激があります。
アルコールの刺激ではありません。
あくまで香辛料のようであります。
唐辛子のように、胡椒のように、しょうがのように、ピリッピリッ。
口中ではじけちゃってます。
忙しいって感じですよ。
口の中では焼酎が、からし蓮根の旨味と合体。
飲み込みますと、辛さまで飲み込まれた感じに気持ちよいリセット効果。
もう一口、もう一杯とすすんでいくわけでありますよ。
焼酎の中でも球磨焼酎にすると雰囲気も出ます。
!今日の格言!
風土はフード。熊本のからし蓮根には球磨焼酎です。!
からし蓮根ったら熊本。
熊本ったらからし蓮根。
熊本名物元祖森からし蓮根であります。

平五郎さんが麦味噌と和からしを混ぜて蓮根の穴に詰め、
麦粉と空豆粉と卵黄を混ぜた衣を着せて、菜種油で揚げて作ったのがはじまり。
明治維新まで門外不出の藩の珍味栄養食。
ありがたくいただきます。
そのままいただいても美味しいです。
辛子が効いていて、辛いです。
そのままいただいた後は、辛子と相性が良いマヨネーズと醤油をつけていただきした。
マヨネーズの油が辛子にも蓮根にもまとわりつき、
まろやかにしてくれます。
そこに醤油があるわけですよ。
辛子と醤油もバッチリ。
マヨネーズと醤油もバッチリ。
辛子 + マヨネーズ = ○
辛子 + 醤油 = ○
醤油 + マヨネーズ = ○
辛子 + マヨネーズ + 醤油 = ◎
辛子とマヨネーズと醤油のハーモニーは素敵です。
ユニゾンではなく、ハモっています。
2つのハーモニーより3つのハーモニーの方が聞こえが良いことからも、
辛子とマヨネーズと醤油の相性はいいわけです。
そこに揚げた蓮根が加わっているのですから、美味しいに決まってますよ。
蓮根(揚げる) + 辛子 + マヨネーズ + 醤油 = ◎
からし蓮根にまろやかさと少々の甘酸っぱさと香ばしさが加わり、旨味が増大。
旨い旨いってなります。
ごはんのおかずにもよいとは思いますが、
これはお酒のおつまみの方がよいと勝手に決めました。
さて、せっかくのからし蓮根です。
球磨焼酎とあわせるのがセオリー。
長期熟成の桜の里とあわせました。
見るからに古い焼酎でしょ。
からし蓮根とあわせるお酒としては、焼酎ならば、たいていはいいでしょう。
日本酒は不向きです。
辛さが極まって、食べにくくなります。
桜の里はピリピリッと香辛料的な刺激があります。
アルコールの刺激ではありません。
あくまで香辛料のようであります。
唐辛子のように、胡椒のように、しょうがのように、ピリッピリッ。
口中ではじけちゃってます。
忙しいって感じですよ。
口の中では焼酎が、からし蓮根の旨味と合体。
飲み込みますと、辛さまで飲み込まれた感じに気持ちよいリセット効果。
もう一口、もう一杯とすすんでいくわけでありますよ。
焼酎の中でも球磨焼酎にすると雰囲気も出ます。
!今日の格言!
風土はフード。熊本のからし蓮根には球磨焼酎です。!
2009年02月24日
古酒とチーズ
押入れにしまい忘れた古酒といろんなおつまみをあわせています。
いまやチーズと日本酒の相性は、本家本元のワインをしのぐと騒がれております。
いずれは世界的な流れになるかと思われます。
押入れにしまい忘れた古酒。
寂しく14年が経過し、姿もめっきり変わりました。
大人になったのです。
古酒もチーズとの相性の良さでも、注目度上昇中です。
世界料理サミット2009でいただいたイタリアのチーズとあわせました。

Taleggio タレッジョ
ロンバルディア産の牛乳から作ったウォッシュタイプ。
タレッジョ渓谷由来であります。
古酒との相性です。
日本酒の古酒 + タレッジョ = △
両者がそれぞれ違った方向を向いてしまって、話ができないようです。
口の中で仲良くならずに、そのうちに喧嘩にでもなりそう。
飲食は無理することもありませんから、ここは遠慮しておきましょう。
もう一つのチーズともあわせました。

Grana Padano グラナ パダーノ
エミリア・ロマーナ産の牛乳から作られたハードタイプ。
キッチンのハズバンドの愛称を持つ、お料理に重宝されるチーズです。
古酒との相性です。
日本酒の古酒 + グラナ パダーノ = ◎
古酒が硬いグラナパダーノをほどよく柔らかに溶かしてくれるかのようです。
グラナパダーノは乳製品らしい香りがたくさん溢れています。
味わいについては硬いので、濃いかなあと思われがちですが、淡白ですね。
余韻を感じてもそのように思えます。
ここがキッチンのハズバンド。
補助的に有効に働くチーズなんですね。
文句ひとつ言わずにワイフのためにこつこつ作業をこなすハズバンド。
そんなハズであります。
お酒も美味しくしてくれるし、そのお酒がチーズを美味しくするとなりますと、
いっそうハズバンドらしく、お酒を美味しくしだす。
口の中でチーズと古酒の性格がわかるようです。
この古酒とチーズは人間には聞こえない、会話をしているのでしょうか?
会話は耳からは聞こえませんが、口から鼻から喉に脳裏に響き渡ってきました。
この感動、あなたにも伝えたい。
あなたにも味わってほしいです。
丸河屋酒店ではお酒類はありますが、チーズは売ってはいません。
いまやチーズと日本酒の相性は、本家本元のワインをしのぐと騒がれております。
いずれは世界的な流れになるかと思われます。
押入れにしまい忘れた古酒。
寂しく14年が経過し、姿もめっきり変わりました。
大人になったのです。
古酒もチーズとの相性の良さでも、注目度上昇中です。
世界料理サミット2009でいただいたイタリアのチーズとあわせました。
Taleggio タレッジョ
ロンバルディア産の牛乳から作ったウォッシュタイプ。
タレッジョ渓谷由来であります。
古酒との相性です。
日本酒の古酒 + タレッジョ = △
両者がそれぞれ違った方向を向いてしまって、話ができないようです。
口の中で仲良くならずに、そのうちに喧嘩にでもなりそう。
飲食は無理することもありませんから、ここは遠慮しておきましょう。
もう一つのチーズともあわせました。
Grana Padano グラナ パダーノ
エミリア・ロマーナ産の牛乳から作られたハードタイプ。
キッチンのハズバンドの愛称を持つ、お料理に重宝されるチーズです。
古酒との相性です。
日本酒の古酒 + グラナ パダーノ = ◎
古酒が硬いグラナパダーノをほどよく柔らかに溶かしてくれるかのようです。
グラナパダーノは乳製品らしい香りがたくさん溢れています。
味わいについては硬いので、濃いかなあと思われがちですが、淡白ですね。
余韻を感じてもそのように思えます。
ここがキッチンのハズバンド。
補助的に有効に働くチーズなんですね。
文句ひとつ言わずにワイフのためにこつこつ作業をこなすハズバンド。
そんなハズであります。
お酒も美味しくしてくれるし、そのお酒がチーズを美味しくするとなりますと、
いっそうハズバンドらしく、お酒を美味しくしだす。
口の中でチーズと古酒の性格がわかるようです。
この古酒とチーズは人間には聞こえない、会話をしているのでしょうか?
会話は耳からは聞こえませんが、口から鼻から喉に脳裏に響き渡ってきました。
この感動、あなたにも伝えたい。
あなたにも味わってほしいです。
丸河屋酒店ではお酒類はありますが、チーズは売ってはいません。