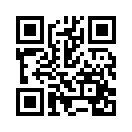2012年02月15日
「静岡酒、この名役者、この名演技」 第14章
しずおか地酒研究会の鈴木真弓さんのWEB酒場静岡吟醸伝に寄稿しています。
「静岡酒、この名役者、この名演技」の第14章です。
第十四章「歴史に残したい静岡の名酒たち その4.」
今や吟醸酒王国とも呼ばるようになった静岡県。
実は吟醸酒ばかりが優秀であるのではありません。
普通酒(一般酒)から本醸造、純米においてもレベルの高さは
日本最高ランクであります。
今回はそんな静岡の本醸造と純米についてであります。
静岡県産酒の本醸造(特別本醸造を含む)と純米(特別純米酒を含む)と
その上のクラスである吟醸酒(大吟醸を含む)や純米吟醸酒(純米大吟醸を含む)
と比べますと、その酒質の差は他県の差よりも少ないです。
吟醸酒も吟醸酒以外も同様に丁寧に造られているからです。
これは生産量がそれほど多くないことも物理的な理由としてありますが、
その前に精神論的なことがあるのです。
静岡県が清酒の名産地と呼ばれるようになったのは、大吟醸を主体とした
全国新酒鑑評会での成績の高さからです。
大吟醸などの出品酒類だけを丁寧に上質に造っていればいいのか?
例えば大吟醸だけを造って販売した場合、経営はうまくいくのか?
それはNOであります。
生産量、作業量、人件費などもろもろの要素を考えますと、
大吟醸だけではなく、その他の特定名称酒も造って販売する必要があります。
大吟醸だけで、鑑評会の成績だけで引っ張っていくのではなく、
お客様が口にされやすい本醸造や純米酒も高品質にする。
そうでなければ駄目なんだ、の精神論があります。
これは主が口が酸っぱくなるくらいに蔵元達に伝えていたこと。
主の指導に沿い、大吟醸と本醸造の差を少なくしてきたことが、
静岡県を清酒の名産地と認知させたのです。
では、実際にどんな取り組みがあったのでしょうか?
特別本醸造は精米歩合が60%以下と決められています。
他県の蔵元が精米歩合が60%で特別本醸造としているなら、
うちは55%でいこう。
いやいや、うちは50%でも特別本醸造でいく、みたいな。
これは「開運 特吟」であります。
また、精米歩合55%は純米吟醸酒でも通るが、
うちはその下の特別純米酒でもなく、ただの純米酒でいくさ、みたいな。
2001年くらいまで造られ、美味しんぼにも登場した「喜久醉 純米55」。
この他にもこのような流れに乗った蔵元がありました。
「開運 特吟」は今でも製造販売されている特別本醸造です。
今回はこの手のお酒を代表し、歴史に残したい静岡の名酒として、
「開運 特吟」を挙げたいと思います。
香り高く、喉越しがスマートな辛口。
香りでバランスを取っているような吟醸酒よりもはるかに
レベルの高い特別本醸造。
静岡の本醸造系の高さを証明しているかのような名酒です。
米を磨き、技を磨いてレベルアップした静岡酒の歴史がこのお酒に宿っています。
「開運の特吟」、歴史に残したい静岡の名酒であります。
開運のラインナップの中では地味な存在ですが、
じっくり味わってほしい一本であります。
次回は原料米でレベルアップについて書きます。
「静岡酒、この名役者、この名演技」の第14章です。
第十四章「歴史に残したい静岡の名酒たち その4.」
今や吟醸酒王国とも呼ばるようになった静岡県。
実は吟醸酒ばかりが優秀であるのではありません。
普通酒(一般酒)から本醸造、純米においてもレベルの高さは
日本最高ランクであります。
今回はそんな静岡の本醸造と純米についてであります。
静岡県産酒の本醸造(特別本醸造を含む)と純米(特別純米酒を含む)と
その上のクラスである吟醸酒(大吟醸を含む)や純米吟醸酒(純米大吟醸を含む)
と比べますと、その酒質の差は他県の差よりも少ないです。
吟醸酒も吟醸酒以外も同様に丁寧に造られているからです。
これは生産量がそれほど多くないことも物理的な理由としてありますが、
その前に精神論的なことがあるのです。
静岡県が清酒の名産地と呼ばれるようになったのは、大吟醸を主体とした
全国新酒鑑評会での成績の高さからです。
大吟醸などの出品酒類だけを丁寧に上質に造っていればいいのか?
例えば大吟醸だけを造って販売した場合、経営はうまくいくのか?
それはNOであります。
生産量、作業量、人件費などもろもろの要素を考えますと、
大吟醸だけではなく、その他の特定名称酒も造って販売する必要があります。
大吟醸だけで、鑑評会の成績だけで引っ張っていくのではなく、
お客様が口にされやすい本醸造や純米酒も高品質にする。
そうでなければ駄目なんだ、の精神論があります。
これは主が口が酸っぱくなるくらいに蔵元達に伝えていたこと。
主の指導に沿い、大吟醸と本醸造の差を少なくしてきたことが、
静岡県を清酒の名産地と認知させたのです。
では、実際にどんな取り組みがあったのでしょうか?
特別本醸造は精米歩合が60%以下と決められています。
他県の蔵元が精米歩合が60%で特別本醸造としているなら、
うちは55%でいこう。
いやいや、うちは50%でも特別本醸造でいく、みたいな。
これは「開運 特吟」であります。
また、精米歩合55%は純米吟醸酒でも通るが、
うちはその下の特別純米酒でもなく、ただの純米酒でいくさ、みたいな。
2001年くらいまで造られ、美味しんぼにも登場した「喜久醉 純米55」。
この他にもこのような流れに乗った蔵元がありました。
「開運 特吟」は今でも製造販売されている特別本醸造です。
今回はこの手のお酒を代表し、歴史に残したい静岡の名酒として、
「開運 特吟」を挙げたいと思います。
香り高く、喉越しがスマートな辛口。
香りでバランスを取っているような吟醸酒よりもはるかに
レベルの高い特別本醸造。
静岡の本醸造系の高さを証明しているかのような名酒です。
米を磨き、技を磨いてレベルアップした静岡酒の歴史がこのお酒に宿っています。
「開運の特吟」、歴史に残したい静岡の名酒であります。
開運のラインナップの中では地味な存在ですが、
じっくり味わってほしい一本であります。
次回は原料米でレベルアップについて書きます。
タグ :開運
2012年02月04日
「静岡酒、この名役者、この名演技」 第13章
しずおか地酒研究会の鈴木真弓さんのWEB酒場静岡吟醸伝に寄稿しています。
「静岡酒、この名役者、この名演技」の第13章です。
第十三章「歴史に残したい静岡の名酒たち その3.」
平成の吟醸酒ブームは全国の名酒掘り出しの役目をしました。
静岡県も地酒の名醸地になるきっかけにもなりました。
吟醸酒ブームの中で目立っていたのは、もちろん吟醸酒です。
その影では吟醸酒以外の普通酒や本醸造や純米も、
それなりの話題を持って語られて飲まれていました。
今回はその中においての普通酒についてのお話です。
普通酒という言葉自体、わけがわからないことでしょう。
普通は・・・であります。
日本酒の普通酒と呼ばれているのは一般酒のことで・・・
そんな言い方をするともっとわからなくなるかも。
普通酒(一般酒)は特定名称を持たない日本酒のことです。
特定名称は本醸造とか純米とか、吟醸とか純米大吟醸などの名称。
これは精米歩合(原料であるお米の磨き具合)や
醸造アルコールの添加の有無により分類されています。
つまり、簡単に言ってしまえば、あまり磨いていない原料で造り、
醸造アルコールを本醸造よりも多めに入れているタイプであります。
と、書きますと、あんまり良いイメージではないかもしれません。
私は普通酒においても肯定派であります。
支持して飲んでいる方々のことを思うと、
その方々の生活にも関係してくることで、
普通酒を否定することは、普通酒を飲んでいる人をも否定しかねません。
選択の余地ということからもあった方が幸せ。
ということもよし。
一方、造り手側に立ってみますと、普通酒にも力を入れている蔵ってあるのか?
級別制度が終わり、良い品質へと流れた酒業界。
普通酒は置いてけぼりになっているとも思われます。
言葉からして、普通が駄目なら他も駄目。
お酒を飲まない方からすれば、それも正解かもしれません。
普通酒を大事に。
普通酒を飲まれる方を大事に。
そんな姿勢の蔵元があります。
その蔵元の普通酒は日本一と呼ばれています。
酒呑みに対して心ある蔵元であります。
・
・
・
日本一の普通酒を造っているのが、藤枝の青島酒造であります。
喜久醉であります。
黙って飲めば、普通酒かとはわからないでしょう。
喜久醉の普通酒は日本一の普通酒。
普通酒でこのレベルなんです。
他のお酒だって日本一のクラスであります。
喜久醉の普通酒、歴史に残したい静岡の名酒であります。
次号は吟醸酒ブームの影にあった本醸造と純米について書きます。
「静岡酒、この名役者、この名演技」の第13章です。
第十三章「歴史に残したい静岡の名酒たち その3.」
平成の吟醸酒ブームは全国の名酒掘り出しの役目をしました。
静岡県も地酒の名醸地になるきっかけにもなりました。
吟醸酒ブームの中で目立っていたのは、もちろん吟醸酒です。
その影では吟醸酒以外の普通酒や本醸造や純米も、
それなりの話題を持って語られて飲まれていました。
今回はその中においての普通酒についてのお話です。
普通酒という言葉自体、わけがわからないことでしょう。
普通は・・・であります。
日本酒の普通酒と呼ばれているのは一般酒のことで・・・
そんな言い方をするともっとわからなくなるかも。
普通酒(一般酒)は特定名称を持たない日本酒のことです。
特定名称は本醸造とか純米とか、吟醸とか純米大吟醸などの名称。
これは精米歩合(原料であるお米の磨き具合)や
醸造アルコールの添加の有無により分類されています。
つまり、簡単に言ってしまえば、あまり磨いていない原料で造り、
醸造アルコールを本醸造よりも多めに入れているタイプであります。
と、書きますと、あんまり良いイメージではないかもしれません。
私は普通酒においても肯定派であります。
支持して飲んでいる方々のことを思うと、
その方々の生活にも関係してくることで、
普通酒を否定することは、普通酒を飲んでいる人をも否定しかねません。
選択の余地ということからもあった方が幸せ。
ということもよし。
一方、造り手側に立ってみますと、普通酒にも力を入れている蔵ってあるのか?
級別制度が終わり、良い品質へと流れた酒業界。
普通酒は置いてけぼりになっているとも思われます。
言葉からして、普通が駄目なら他も駄目。
お酒を飲まない方からすれば、それも正解かもしれません。
普通酒を大事に。
普通酒を飲まれる方を大事に。
そんな姿勢の蔵元があります。
その蔵元の普通酒は日本一と呼ばれています。
酒呑みに対して心ある蔵元であります。
・
・
・
日本一の普通酒を造っているのが、藤枝の青島酒造であります。
喜久醉であります。
黙って飲めば、普通酒かとはわからないでしょう。
喜久醉の普通酒は日本一の普通酒。
普通酒でこのレベルなんです。
他のお酒だって日本一のクラスであります。
喜久醉の普通酒、歴史に残したい静岡の名酒であります。
次号は吟醸酒ブームの影にあった本醸造と純米について書きます。
タグ :喜久醉
2012年01月21日
エグザイル風?
赤薔薇タキシードの次はモダンなエグザイル風。
リクエストがありました。
「エグザイルとマイケルジャクソンをあわせたような雰囲気にして」
いやいやしばらく考え込んでいました。
どうしたらそうなれるのか。
「赤薔薇タキシードはほのぼのしていて、それはそれでいいけど、
河原崎さんらしいスポーティーさや男らしさが出せない」
リクエストの理由でありました。
赤薔薇タキシードはかなり気に入っている衣装。
でも、それもそうだなあ。
危険な香りがする男河原崎を出してみよう。
それがこの衣装。
シャツやスカーフをいくつかアレンジすればいいなあと思っています。

リクエストがありました。
「エグザイルとマイケルジャクソンをあわせたような雰囲気にして」
いやいやしばらく考え込んでいました。
どうしたらそうなれるのか。
「赤薔薇タキシードはほのぼのしていて、それはそれでいいけど、
河原崎さんらしいスポーティーさや男らしさが出せない」
リクエストの理由でありました。
赤薔薇タキシードはかなり気に入っている衣装。
でも、それもそうだなあ。
危険な香りがする男河原崎を出してみよう。
それがこの衣装。
シャツやスカーフをいくつかアレンジすればいいなあと思っています。
2012年01月13日
東海大学短期大学部にて講演 2012.3.9
静岡市葵区柚木にあります東海大学短期大学部にて講演します。
酒屋の親父がちょびちょびすいません。
フードサイエンス 食の扉シリーズの第三弾。
その最終章として私が日本酒の話をします。
内容は「華麗なる吟醸酒」。
吟醸酒の歴史
吟醸酒の正体
吟醸酒の香りのペンタゴン
吟醸酒の美学
1時間30分ですので、どのへんまでつっこんで話せるのかはわかりませんが、
ポイントはしっかり捉えてもらえるようにします。
日時:2012年3月9日 19時から20時30分
会場:東海大学短期大学部 5号館 4階
静岡市葵区宮前町101
054-261-6321
会費:無料
参加方法:直接会場までお越しください。
事前のお申し込みは必要ありません。
2011年は9月9日にお話させていただきました。
約50名ほどの聴講者にお越しいただきました。
3月もみなさんのご参加をお待ちしています。
酒屋の親父がちょびちょびすいません。
フードサイエンス 食の扉シリーズの第三弾。
その最終章として私が日本酒の話をします。
内容は「華麗なる吟醸酒」。
吟醸酒の歴史
吟醸酒の正体
吟醸酒の香りのペンタゴン
吟醸酒の美学
1時間30分ですので、どのへんまでつっこんで話せるのかはわかりませんが、
ポイントはしっかり捉えてもらえるようにします。
日時:2012年3月9日 19時から20時30分
会場:東海大学短期大学部 5号館 4階
静岡市葵区宮前町101
054-261-6321
会費:無料
参加方法:直接会場までお越しください。
事前のお申し込みは必要ありません。
2011年は9月9日にお話させていただきました。
約50名ほどの聴講者にお越しいただきました。
3月もみなさんのご参加をお待ちしています。
タグ :日本酒
2011年12月18日
いいんでない会 米糠・酒粕
いいんでない会に呼ばれました。
12月11日、静岡市葵区アイセル21にて。
9月4日に続いて2回目となりました。

健康などをテーマに集まっているグループの方々。
私はどんな話をしたらよいのか。
迷いました。
お酒の話はお酒を飲まれる方などのお酒に興味ある方はいいのですが、
お酒を必要としていない方などには、どうでもよいような話でしょう。
お酒を飲む場所でもない会場。
私はお酒にまつわって、お酒ではない、米糠と酒粕についてやりました。
米糠には白糠と赤糠があります。
白糠は肌糠とも言われ、美人糠として商品にもなっています。
米糠は静岡市葵区の片山米店さんに御協力をいただきました。

白糠と赤糠の両方をお持ちして比べてもらい、
白糠を使ったパックをすることにしました。

手につけて触っていますと手の中に吸い込まれます。
10分もしない間に水分や脂分が吸収されていきました。

日本盛さんから「米ぬか美人」シリーズの商品が出ています。
いち早く米糠の長所を取り入れています。
ちなみに私の母も日本盛の「米ぬか美人シャンプー」を使っています。
私が日本酒の蔵人をしていた頃の手がきれいになる時間帯についてもお話しました。
「杜氏さんの手・・・」の宣伝の真意もお話させてもらいました。
米糠の次は酒粕の登場。
三日前に搾って出た酒粕をお持ちしました。
やはり香りはいいものです。
今朝は2時間くらいにわたって、母と私で酒粕汁を造りました。

砂糖を使ってしまった点はよくないとの指摘でしたが、
味的にはgoodだとの評価をいただきました。
お酒と粕汁とどっちが美味しいのか?
粕でもここまで美味しいのだから、お酒だったらもっと美味しいのでは?
そう思ってくれた方っていたかなあ。
いたら、その方はお酒飲みかなあ。
こちらの立場の感想であります。
最後に玄米食のお弁当を食べました。
腹持ちがよく、6時間くらいお腹が減りませんでした。

酒屋がお酒の話題抜きで話をするのは、ほとほと大変です。
今回はそれでもまあまあの出来ではなかったと自負しております。
12月11日、静岡市葵区アイセル21にて。
9月4日に続いて2回目となりました。
健康などをテーマに集まっているグループの方々。
私はどんな話をしたらよいのか。
迷いました。
お酒の話はお酒を飲まれる方などのお酒に興味ある方はいいのですが、
お酒を必要としていない方などには、どうでもよいような話でしょう。
お酒を飲む場所でもない会場。
私はお酒にまつわって、お酒ではない、米糠と酒粕についてやりました。
米糠には白糠と赤糠があります。
白糠は肌糠とも言われ、美人糠として商品にもなっています。
米糠は静岡市葵区の片山米店さんに御協力をいただきました。
白糠と赤糠の両方をお持ちして比べてもらい、
白糠を使ったパックをすることにしました。
手につけて触っていますと手の中に吸い込まれます。
10分もしない間に水分や脂分が吸収されていきました。
日本盛さんから「米ぬか美人」シリーズの商品が出ています。
いち早く米糠の長所を取り入れています。
ちなみに私の母も日本盛の「米ぬか美人シャンプー」を使っています。
私が日本酒の蔵人をしていた頃の手がきれいになる時間帯についてもお話しました。
「杜氏さんの手・・・」の宣伝の真意もお話させてもらいました。
米糠の次は酒粕の登場。
三日前に搾って出た酒粕をお持ちしました。
やはり香りはいいものです。
今朝は2時間くらいにわたって、母と私で酒粕汁を造りました。
砂糖を使ってしまった点はよくないとの指摘でしたが、
味的にはgoodだとの評価をいただきました。
お酒と粕汁とどっちが美味しいのか?
粕でもここまで美味しいのだから、お酒だったらもっと美味しいのでは?
そう思ってくれた方っていたかなあ。
いたら、その方はお酒飲みかなあ。
こちらの立場の感想であります。
最後に玄米食のお弁当を食べました。
腹持ちがよく、6時間くらいお腹が減りませんでした。
酒屋がお酒の話題抜きで話をするのは、ほとほと大変です。
今回はそれでもまあまあの出来ではなかったと自負しております。
タグ :酒粕
2011年12月05日
三井生命様にて講演 2011年11月
東京駅に近い大手町と千葉の柏にて講演を行ってきました。
行き先は三井生命様であります。
大手町では300名様くらい、柏では250名様くらいにご参加いただきました。


今回のご依頼内容は「東北のお酒で盛り上げてほしい」でありました。
私の持ち時間は両方とも45分。
きき酒や酒類全般に渡って聞いてほしいことを喋らせてもらいました。
あらかじめどんな場面かは想像でしかわかりません。
何をしたらいいのか。
何をするべきなのか。
よくわからないところもあっての壇上。
自分への評価の心配をしつつ、笑顔でお酒の魅力を語った、
いやいや騒いだのでありました。
また、お酒の普及活動の意味合いもありましたが、
みなさんの方からお酒に近寄ってくれて、
まだまだ日本酒もやり方次第では人気があるのだなと実感いたしました。
みなさんを見ていて、「男飲み」と「女飲み」とがあるのだなあと気がつき、
どうも我々酒業界は「男飲み」ばかり意識してきた傾向があるとも思いました。
幸せそうな「女飲み」の実践も普及の一つになりそうです。
呼んでもらえたことの感謝。
そしてまたみなさんとお会いしたいなあと思います。
行き先は三井生命様であります。
大手町では300名様くらい、柏では250名様くらいにご参加いただきました。
今回のご依頼内容は「東北のお酒で盛り上げてほしい」でありました。
私の持ち時間は両方とも45分。
きき酒や酒類全般に渡って聞いてほしいことを喋らせてもらいました。
あらかじめどんな場面かは想像でしかわかりません。
何をしたらいいのか。
何をするべきなのか。
よくわからないところもあっての壇上。
自分への評価の心配をしつつ、笑顔でお酒の魅力を語った、
いやいや騒いだのでありました。
また、お酒の普及活動の意味合いもありましたが、
みなさんの方からお酒に近寄ってくれて、
まだまだ日本酒もやり方次第では人気があるのだなと実感いたしました。
みなさんを見ていて、「男飲み」と「女飲み」とがあるのだなあと気がつき、
どうも我々酒業界は「男飲み」ばかり意識してきた傾向があるとも思いました。
幸せそうな「女飲み」の実践も普及の一つになりそうです。
呼んでもらえたことの感謝。
そしてまたみなさんとお会いしたいなあと思います。
2011年11月11日
静岡酒、この名役者、この名演技 第12章
しずおか地酒研究会の鈴木真弓さんのWEB酒場静岡吟醸伝に寄稿しています。
「静岡酒、この名役者、この名演技」の第12章です。
「歴史に残したい静岡の名酒たち その2.」
ブームには必ず立役者がいる。
静岡吟醸ブームの立役者について第十一章で書きました。
歴史に残したい名酒があるからこそ、ブームもあるわけです。
そんな歴史に残したい静岡の名酒としてまず開運の大吟醸を書きました。
今回はその2.です。
静岡酵母という宝を得た静岡酒。
まさに打ち出の小槌。
静岡酵母を使ったお酒をいち早く販売チャンネルに浸透させる。
そこが勝負の分かれ目であったような気がしています。
先手必勝、先発隊断然優位でした。
蔵元ではなく銘柄、まさにブランドが一人歩きした「おんな泣かせ」、
そして首都圏の業務用を席巻した「磯自慢本醸造」。
これらは間違いなく歴史に残したい静岡酒ですが、
この2つのお酒についてはこれまで書いてきましたので、
そこを参照してくださればと思います。
「おんな泣かせ」は第2章「連戦連勝 その第一歩」。
「磯自慢本醸造」は第3章「連戦連勝 首都制圧」。
全国的な吟醸酒ブームは平成とともにやってきた感があります。
この頃の酒米は五百万石が主流で生産量も一番でした。
山田錦は高嶺の花であり、高価でしかも静岡では栽培しにくかったです。
主産地の兵庫からは、こちらの希望数量は回してもらえなかったこともありました。
総合的に五百万石に人気が集中し、北陸から県全体で数量を
まとめるなどして仕入れていました。
したがって、平成がはじまってまもない吟醸酒ブームの時代、
静岡酒は五百万石が主流で一般的であり、
山田錦は酒母や麹米として使われていました。
静岡酵母 + 五百万石 = 静岡吟醸
果たしてどんなお酒を想像できるのでしょう?
どんな銘柄が思い当たりますか?
私はこのお酒を飲んだ瞬間に、平成の吟醸酒ブーム真っ只中の
静岡吟醸を思い出さずにはいられませんでした。
まさにあの頃の主流の味。
みんなが恋した静岡らしい吟醸香。
静岡酵母と五百万石が奏でるハーモニーであります。
そのお酒とは ・・・
・・・ 緑の英君であります。
「緑の英君って何だ?」
と思いながら口をつけた瞬間。
忘れもしません。
ほろっときそうになりました。
「ああ、これだよ。これなんだよ。」
「この道、静岡酒のこの道を通ったんだ。」
「この香り、この味わい。この余韻。」
これは後世に伝えなくてはいけない酒質。
平成23年、2011年の今では滅多に見かけないタイプ。
いまでのこの酒質を維持し、製造している英君さんに感謝。
そんな思いで、軽やかな静岡酒ですが、重い一杯を飲みました。
私がこのタイプの英君をはじめて飲んだのは1990年(平成2年)の冬。
静岡市葵区にあった本多和洋酒で買った「ごせっぽい」でした。
土産っぽいネーミングだから大したことないなと思いつつ、
ギフト箱を開けますと、ぷ~んと湧き上がる吟醸香にビックリ。
作り立てなのかなと思いましたが、箱からの匂いは酸化臭が伴うのが普通。
しかし「ごせっぽい」が入ったその箱からは、
酸化臭も感じさせないくらい静岡吟醸香が立っていました。
箱からの香りすらこれほどのものです。
お酒は”昇る朝日の静岡酒”の勢いを持った明るい光沢を持った吟醸酒。
甘辛ピン!の三拍子に深みのある旨味。
第一印象もいいですし、飲み飽きしない酒通好み。
静岡のお酒ってこんなに美味しくなったんだなあと
惚れ惚れしたことを鮮明におぼえています。
「ごせっぽい」は当時2級酒でした。
蔵元さんの話ですと、720mlで1,500円。
福井県産の五百万石(精米歩合55%)を使用。
吟醸酒でありました。
現在はこの銘柄は造られていないそうです。
私の脳裏にはっきりと「ごせっぽい」の印象が残っていましたので、
緑の英君を飲んだ瞬間に「ごせっぽい」が蘇りました。
「緑の英君」はこれまで通ってきた静岡吟醸の生き証人のようなお酒。
歴史に残したい静岡の名酒であります。
「静岡酒、この名役者、この名演技」の第12章です。
「歴史に残したい静岡の名酒たち その2.」
ブームには必ず立役者がいる。
静岡吟醸ブームの立役者について第十一章で書きました。
歴史に残したい名酒があるからこそ、ブームもあるわけです。
そんな歴史に残したい静岡の名酒としてまず開運の大吟醸を書きました。
今回はその2.です。
静岡酵母という宝を得た静岡酒。
まさに打ち出の小槌。
静岡酵母を使ったお酒をいち早く販売チャンネルに浸透させる。
そこが勝負の分かれ目であったような気がしています。
先手必勝、先発隊断然優位でした。
蔵元ではなく銘柄、まさにブランドが一人歩きした「おんな泣かせ」、
そして首都圏の業務用を席巻した「磯自慢本醸造」。
これらは間違いなく歴史に残したい静岡酒ですが、
この2つのお酒についてはこれまで書いてきましたので、
そこを参照してくださればと思います。
「おんな泣かせ」は第2章「連戦連勝 その第一歩」。
「磯自慢本醸造」は第3章「連戦連勝 首都制圧」。
全国的な吟醸酒ブームは平成とともにやってきた感があります。
この頃の酒米は五百万石が主流で生産量も一番でした。
山田錦は高嶺の花であり、高価でしかも静岡では栽培しにくかったです。
主産地の兵庫からは、こちらの希望数量は回してもらえなかったこともありました。
総合的に五百万石に人気が集中し、北陸から県全体で数量を
まとめるなどして仕入れていました。
したがって、平成がはじまってまもない吟醸酒ブームの時代、
静岡酒は五百万石が主流で一般的であり、
山田錦は酒母や麹米として使われていました。
静岡酵母 + 五百万石 = 静岡吟醸
果たしてどんなお酒を想像できるのでしょう?
どんな銘柄が思い当たりますか?
私はこのお酒を飲んだ瞬間に、平成の吟醸酒ブーム真っ只中の
静岡吟醸を思い出さずにはいられませんでした。
まさにあの頃の主流の味。
みんなが恋した静岡らしい吟醸香。
静岡酵母と五百万石が奏でるハーモニーであります。
そのお酒とは ・・・
・・・ 緑の英君であります。
「緑の英君って何だ?」
と思いながら口をつけた瞬間。
忘れもしません。
ほろっときそうになりました。
「ああ、これだよ。これなんだよ。」
「この道、静岡酒のこの道を通ったんだ。」
「この香り、この味わい。この余韻。」
これは後世に伝えなくてはいけない酒質。
平成23年、2011年の今では滅多に見かけないタイプ。
いまでのこの酒質を維持し、製造している英君さんに感謝。
そんな思いで、軽やかな静岡酒ですが、重い一杯を飲みました。
私がこのタイプの英君をはじめて飲んだのは1990年(平成2年)の冬。
静岡市葵区にあった本多和洋酒で買った「ごせっぽい」でした。
土産っぽいネーミングだから大したことないなと思いつつ、
ギフト箱を開けますと、ぷ~んと湧き上がる吟醸香にビックリ。
作り立てなのかなと思いましたが、箱からの匂いは酸化臭が伴うのが普通。
しかし「ごせっぽい」が入ったその箱からは、
酸化臭も感じさせないくらい静岡吟醸香が立っていました。
箱からの香りすらこれほどのものです。
お酒は”昇る朝日の静岡酒”の勢いを持った明るい光沢を持った吟醸酒。
甘辛ピン!の三拍子に深みのある旨味。
第一印象もいいですし、飲み飽きしない酒通好み。
静岡のお酒ってこんなに美味しくなったんだなあと
惚れ惚れしたことを鮮明におぼえています。
「ごせっぽい」は当時2級酒でした。
蔵元さんの話ですと、720mlで1,500円。
福井県産の五百万石(精米歩合55%)を使用。
吟醸酒でありました。
現在はこの銘柄は造られていないそうです。
私の脳裏にはっきりと「ごせっぽい」の印象が残っていましたので、
緑の英君を飲んだ瞬間に「ごせっぽい」が蘇りました。
「緑の英君」はこれまで通ってきた静岡吟醸の生き証人のようなお酒。
歴史に残したい静岡の名酒であります。
2011年10月23日
静岡酒、この名役者、この名演技 11.
しずおか地酒研究会の鈴木真弓さんのWEB酒場静岡吟醸伝に寄稿しています。
「静岡酒、この名役者、この名演技」の第11章です。
「歴史に残したい静岡の名酒たち その1.」
私が酒業界に従事し始めたのが、昭和57年。
平成23年は昭和に換算すると昭和86年。
ですから今年で30年目になるわけです。
30年の中で口にしたお酒の数はいくつか?
それは数え切れないくらいですし、耳で聞いただけ、
目で見ただけのお酒だってどのくらいあることか。
こんな星の数ほどのお酒の中から、
歴史に残したい静岡の名酒を選んでみます。
日本酒の消費量が最大だったのは、高度成長時代の昭和48年。
私が従事し始めた57年も日本酒は今から考えれば、
嘘のようにたくさん飲まれていました。
昭和の時代は級別制度があり、2級が普通で1級が上等、
特級は正月くらいしか飲めない代物で金粉入りもありました。
残念ながら、静岡酒での金粉入りはおぼえがありません。
当時は私の父も2級を晩酌しつつも、「旨いお酒はYK35だぞ」とか、
「灘の宮水がお酒にとっては名水」と語っていたことを思い出します。
昭和40年代以前は灘の「剣菱」が幻のお酒として騒がれました。
その後は佐々木久子さんや深夜番組イレブンPMなどで
散々「越の三梅」を取り上げたこともあり、「越乃寒梅」がブレイク。
昭和50年代から60年代は「剣菱」にとって代わり、
「越乃寒梅」が幻のお酒として一世風靡しました。
この頃の静岡酒は消費者にとっては目立ったことはありませんでしたが、
「満寿一」と「開運」は鑑評会に出品し続け、吟醸つくりに磨きをかけていました。
そういった努力が功を奏し、静岡酵母からの名酒の誕生となったわけです。
静岡のお酒が静岡らしく輝き続ける限り、忘れてはいけない原点の名酒は
「開運 大吟醸」でありましょう。
開運のお酒を置いてある酒屋はおおけれど、開運大吟醸を買える店となると、
旧静岡市内では山崎酒店(現 ヴィノスヤマザキ)だけでありました。
これには大きな訳があったわけで、静岡の大吟醸が大ブレイクしたのは、
「開運」「静岡酵母」「山崎酒店」の夢見る努力があったからであります。
満寿一とともに吟醸酒造りを一生懸命やってきた開運が河村先生に応えるべく、
もろみを提供し、静岡酵母HD-1の誕生。
静岡のお酒は灘や伏見の下請け酒屋で、美味しくないとの評判に逆行した山崎巽氏。
「俺が一生懸命売っていくから、静岡酵母でやってみよう」と何蔵もの姿勢を変えた
原動力のひとつになっていたようです。
その裏には故静岡県酒造組合専務理事の栗田覚一郎氏の存在がありました。
栗田さんと山崎さんは同級生であり、これは栗田さんから直接何度もお聞きした、
あるときの酒造組合での場面です。
山崎氏「全国には旨い地酒がたくさんあるのに、静岡にはないな。」
「だから静岡のお酒を売っていないんだよ。」
栗田氏「おいおい、これからは違うぞ。」
「県の技師が必死になっていてなあ、土井君のところで良い種が見つかったようで、
それが熊本のよりもいいらしいんだよ。」
元々全国の地酒専門店であった山崎氏はこの情報をいち早くキャッチし、
静岡県内の蔵元訪問に出たというわけです。
当時は酒販店が蔵元に出向いて仕入れるということは滅多にないことでありました。
問屋が力を持っていたからです。
山崎氏は自分を信じ、静岡の蔵元を信じて、静岡吟醸の拡販に成功しました。
「蔵元」「県」「酒販店」の三つ巴があったからこそ、今の静岡酒があると思います。
静岡酒を語る上で忘れてはいけない、ここがスタート。
原動力の名酒が開運の大吟醸であります。
自社酵母を県にも譲ってライバル会社(同業者)のために一肌脱いだ
開運の土井酒造場 の懐の深さを味わってほしいと思います。
「静岡酒、この名役者、この名演技」の第11章です。
「歴史に残したい静岡の名酒たち その1.」
私が酒業界に従事し始めたのが、昭和57年。
平成23年は昭和に換算すると昭和86年。
ですから今年で30年目になるわけです。
30年の中で口にしたお酒の数はいくつか?
それは数え切れないくらいですし、耳で聞いただけ、
目で見ただけのお酒だってどのくらいあることか。
こんな星の数ほどのお酒の中から、
歴史に残したい静岡の名酒を選んでみます。
日本酒の消費量が最大だったのは、高度成長時代の昭和48年。
私が従事し始めた57年も日本酒は今から考えれば、
嘘のようにたくさん飲まれていました。
昭和の時代は級別制度があり、2級が普通で1級が上等、
特級は正月くらいしか飲めない代物で金粉入りもありました。
残念ながら、静岡酒での金粉入りはおぼえがありません。
当時は私の父も2級を晩酌しつつも、「旨いお酒はYK35だぞ」とか、
「灘の宮水がお酒にとっては名水」と語っていたことを思い出します。
昭和40年代以前は灘の「剣菱」が幻のお酒として騒がれました。
その後は佐々木久子さんや深夜番組イレブンPMなどで
散々「越の三梅」を取り上げたこともあり、「越乃寒梅」がブレイク。
昭和50年代から60年代は「剣菱」にとって代わり、
「越乃寒梅」が幻のお酒として一世風靡しました。
この頃の静岡酒は消費者にとっては目立ったことはありませんでしたが、
「満寿一」と「開運」は鑑評会に出品し続け、吟醸つくりに磨きをかけていました。
そういった努力が功を奏し、静岡酵母からの名酒の誕生となったわけです。
静岡のお酒が静岡らしく輝き続ける限り、忘れてはいけない原点の名酒は
「開運 大吟醸」でありましょう。
開運のお酒を置いてある酒屋はおおけれど、開運大吟醸を買える店となると、
旧静岡市内では山崎酒店(現 ヴィノスヤマザキ)だけでありました。
これには大きな訳があったわけで、静岡の大吟醸が大ブレイクしたのは、
「開運」「静岡酵母」「山崎酒店」の夢見る努力があったからであります。
満寿一とともに吟醸酒造りを一生懸命やってきた開運が河村先生に応えるべく、
もろみを提供し、静岡酵母HD-1の誕生。
静岡のお酒は灘や伏見の下請け酒屋で、美味しくないとの評判に逆行した山崎巽氏。
「俺が一生懸命売っていくから、静岡酵母でやってみよう」と何蔵もの姿勢を変えた
原動力のひとつになっていたようです。
その裏には故静岡県酒造組合専務理事の栗田覚一郎氏の存在がありました。
栗田さんと山崎さんは同級生であり、これは栗田さんから直接何度もお聞きした、
あるときの酒造組合での場面です。
山崎氏「全国には旨い地酒がたくさんあるのに、静岡にはないな。」
「だから静岡のお酒を売っていないんだよ。」
栗田氏「おいおい、これからは違うぞ。」
「県の技師が必死になっていてなあ、土井君のところで良い種が見つかったようで、
それが熊本のよりもいいらしいんだよ。」
元々全国の地酒専門店であった山崎氏はこの情報をいち早くキャッチし、
静岡県内の蔵元訪問に出たというわけです。
当時は酒販店が蔵元に出向いて仕入れるということは滅多にないことでありました。
問屋が力を持っていたからです。
山崎氏は自分を信じ、静岡の蔵元を信じて、静岡吟醸の拡販に成功しました。
「蔵元」「県」「酒販店」の三つ巴があったからこそ、今の静岡酒があると思います。
静岡酒を語る上で忘れてはいけない、ここがスタート。
原動力の名酒が開運の大吟醸であります。
自社酵母を県にも譲ってライバル会社(同業者)のために一肌脱いだ
開運の土井酒造場 の懐の深さを味わってほしいと思います。
2011年10月22日
静岡酒、この名役者、この名演技 10.
しずおか地酒研究会の鈴木真弓さんのWEB酒場静岡吟醸伝に寄稿しています。
「静岡酒、この名役者、この名演技」の第10章です。
「私の静岡酒三十年史後期」
仕事とは言いながら、酒一筋に没頭してきた私にお酒の講師をしないかと
頼まれたのが30代半ば。
依頼主はSBS学苑パルシェ校でありました。
日本酒講座を企画しているが、講師はまだ決まらない。
SBS学苑は鈴木真弓さんとすでに日本酒講座を開始しているSBS学苑浜松校の寺田さん
に相談し、私が抜擢されたというわけであります。
「私は先生と呼ばれたいほどの馬鹿はいない」と
故静岡県酒造組合専務理事栗田覚一郎さんから言われたこともあり、
当初は低頭にお断りしていましたが、当時の部長の酒講座開講への熱意に打たれ、
謹んでお引き受けした次第であります。
私は日本酒に対しては自信がありました。
酒販店であり、蔵人経験もあり、日本酒については精通した専門家であると自負していたのです。
ところがいざ開講してみますと、講座のテーマや内容に苦労しました。
ようするにネタ探しであります。
6回くらいならどうにもできますが、エンドレスで続くとなりますと、相当な数のネタが必要です。
4年間は重ならないようにネタも60本以上持ち合わせることができ、今も増え続けています。
悩みながら時間が過ぎていました。
それからきき酒。
これ自信がありましたが、教えるとなると別問題。
私は教えることからの脱却をはじめました。
教えますと、私と同じようなきき酒でなければ駄目と意識付けさせてしまうからです。
きき酒はティーチングではなくコーチングでいこう!
これまでの酒流通者として、あるいは酒製造者としてのきき酒ではティーチングまでなんです。
コーチングは生徒さんの希望する位置にもっていってあげること。
上手になりたいならティーチングでもいいのですが、優勝したいとなりますとコーチングなんです。
私は独学できき酒の美学を完成させながら、生徒さん個々のきき酒の実力向上に気を配りました。
きき酒能力は曲線で描くことができます。
まず第一の・・・・・(話がややこしくなるのでここまでにします)。
飲み手(素人)のきき酒能力を全国優勝するまで上げるには、
造り手や売り手のきき酒能力だけでは無理ではないかと、模索して面倒をみました。
結果5年間で4名を全国大会の表彰台にあげることができました。
内訳です。
日本酒造組合中央会主催 全国きき酒選手権大会 優勝:1名
同大会準優勝:1名
同大会4位:1名
純粋日本酒協会主催 きき酒コンテスト 優勝(きき酒名人認定):1名
2011年も10月の全国きき酒選手権大会に生徒さんが出ます。
このような結果が出てきたことは、自分のきき酒美学の芯がしっかりとあるからだと思います。
●●● その芯とは静岡酒なのであります ●●●
●●● すべては静岡酒によって得られた賜物なのであります ●●●
生徒さんには一人でも多く、ご自身のきき酒美学の芯を持ってもらいたい。
その気持ちを言葉に出さずに、静岡酒を提供し、コーチングを続けています。
次回は第十一章「歴史に残したい静岡の名酒たち」を書きます。
「静岡酒、この名役者、この名演技」の第10章です。
「私の静岡酒三十年史後期」
仕事とは言いながら、酒一筋に没頭してきた私にお酒の講師をしないかと
頼まれたのが30代半ば。
依頼主はSBS学苑パルシェ校でありました。
日本酒講座を企画しているが、講師はまだ決まらない。
SBS学苑は鈴木真弓さんとすでに日本酒講座を開始しているSBS学苑浜松校の寺田さん
に相談し、私が抜擢されたというわけであります。
「私は先生と呼ばれたいほどの馬鹿はいない」と
故静岡県酒造組合専務理事栗田覚一郎さんから言われたこともあり、
当初は低頭にお断りしていましたが、当時の部長の酒講座開講への熱意に打たれ、
謹んでお引き受けした次第であります。
私は日本酒に対しては自信がありました。
酒販店であり、蔵人経験もあり、日本酒については精通した専門家であると自負していたのです。
ところがいざ開講してみますと、講座のテーマや内容に苦労しました。
ようするにネタ探しであります。
6回くらいならどうにもできますが、エンドレスで続くとなりますと、相当な数のネタが必要です。
4年間は重ならないようにネタも60本以上持ち合わせることができ、今も増え続けています。
悩みながら時間が過ぎていました。
それからきき酒。
これ自信がありましたが、教えるとなると別問題。
私は教えることからの脱却をはじめました。
教えますと、私と同じようなきき酒でなければ駄目と意識付けさせてしまうからです。
きき酒はティーチングではなくコーチングでいこう!
これまでの酒流通者として、あるいは酒製造者としてのきき酒ではティーチングまでなんです。
コーチングは生徒さんの希望する位置にもっていってあげること。
上手になりたいならティーチングでもいいのですが、優勝したいとなりますとコーチングなんです。
私は独学できき酒の美学を完成させながら、生徒さん個々のきき酒の実力向上に気を配りました。
きき酒能力は曲線で描くことができます。
まず第一の・・・・・(話がややこしくなるのでここまでにします)。
飲み手(素人)のきき酒能力を全国優勝するまで上げるには、
造り手や売り手のきき酒能力だけでは無理ではないかと、模索して面倒をみました。
結果5年間で4名を全国大会の表彰台にあげることができました。
内訳です。
日本酒造組合中央会主催 全国きき酒選手権大会 優勝:1名
同大会準優勝:1名
同大会4位:1名
純粋日本酒協会主催 きき酒コンテスト 優勝(きき酒名人認定):1名
2011年も10月の全国きき酒選手権大会に生徒さんが出ます。
このような結果が出てきたことは、自分のきき酒美学の芯がしっかりとあるからだと思います。
●●● その芯とは静岡酒なのであります ●●●
●●● すべては静岡酒によって得られた賜物なのであります ●●●
生徒さんには一人でも多く、ご自身のきき酒美学の芯を持ってもらいたい。
その気持ちを言葉に出さずに、静岡酒を提供し、コーチングを続けています。
次回は第十一章「歴史に残したい静岡の名酒たち」を書きます。
2011年10月21日
静岡酒、この名役者、この名演技 9.
しずおか地酒研究会の鈴木真弓さんのWEB酒場静岡吟醸伝に寄稿しています。
「静岡酒、この名役者、この名演技」の第9章です。
「私の静岡酒三十年史中期」
酒屋の酒知らずから一転。
猛勉強の一環として、酒造りもある程度は知らなければ。
本から一通り学んだだけの頭でっかちではいけない。
体でも覚えなければ。
祖父からお世話になっている君盃酒造さんにお願いし、
酒つくりのスタッフである蔵人として扱ってもらうことになりました。
酒造責任者である杜氏は小柄な阿部さん。
阿部さんは標準語をまったく話さず、
何を言っているのかちんぷんかんぷん。
こちらが理解できず、仕事が後手後手になる場面が多く、
いつも怒られていました。
1年目はまったく相手にされず、話しかけてくれることもほぼなかったです。
人間って、役に立たないことが悔しくても涙が出そうになるのですね。
見よう見真似でコツコツと一つづつ覚えていきました。
世間話もしないくらい仕事に集中できたおかげで、
朝一番からその日の最後までの段取りがわかりましたから、
声を掛け合わなくとも、誰が何をするのかがわかり、
私は私なりの仕事ができました。
朝は5時前には蔵元に着き、蔓延する蒸気の中、蒸し米を待ちました。
麹米の引き込みと掛け米の冷やしが次の作業。
200度以上あろうかと思う蒸し米を4度にします。
蒸し米の表面と内面の温度が若干違っていることすら駄目。
朝一番の冷え込みを利用しながら冷やします。
蒸し米は今のように機械からの風を利用しませんでした。
桶に入れて運び、布の上に広げていきます。
かわいい子供に荒風を当ててはいけないとの心配り。
何度も混ぜながら、蒸し米の温度を一定に冷やすと時間は7時くらいに。
杜氏の包丁の音が聞こえてきます。
トトトトトと空腹の私にも響くわけです。
この音が聞こえると、朝一番の仕事ももうすぐ終わり。
君盃酒造の阿部杜氏は朝飯の料理長でもありました。
私は丸河屋の仕事がありますから、ここで店に戻ります。
配達を終えて、お昼は洗米作業。
「おい、若けえの」と一番たくさん運ばせてもらいました。
私はこの時から米の良し悪しを水を通して覚えるようになりました。
水の中に入れた方がよくわかるのです。
洗ってからの米の様子から、その品種が何であるかも大体想像通り。
こういうことがわかるから、職人はやめれないなって気分も理解できます。
もろみの様子(味見)や明日の蒸しの準備をしたら、また丸河屋に。
午前中時間があれば、仕込みをしました。
櫂入れまでしますと、汗ばむくらい。
飲料の仕事は重労働で体力勝負です。
もろみを味見していますと、きき酒能力が上がっているなと実感できます。
神経質くらいの繊細さで接していますから、
醗酵中のアルコールの老ね具合までわかるようになりました。
2年目、私は勝負に出ます。
タンクも勝手に動かして配置。
田植えや刈り取りなども県外でして米を手配。
そうなんです。
できたお酒は全部自分で現金で買い取るから、自分のお酒を造らせて。
わがままを承知で1本造ろうとはじめました。
冷却装置も自前。
酒販店である以上、ここは通らねばいけない壁。
大失敗でもまだまだ先が長いから。
若さですねえ。
私も父も反対しましたが、そんなことはおかまいなしとスタート。
酒造りは私一人ではできません。
杜氏にしてみれば、自分の管理下。
社長にしてみれば、自分の商品。
私は1.8L換算で300本。
好きなようにやらせてもらい純米吟醸を完成させました。
全量買取、丸河屋の冷蔵庫に持ってきました。
お金は銀行から借りて、月々の支払いにしました。
1年かかるかどうかの時期に売り切ることができました。
3年目、気を良くした私は増産します。
300本から600本への挑戦です。
酒造りよりも販売がどうかに挑戦は移っていました。
銀行への支払いは、このお酒だけで毎月20万円。
販路をかなり広げなければなりませんでした。
夕方の6時40分くらいの新幹線で関東方面に営業に行き、
11時40分くらい品川発のムーンライトながらで帰ってきます。
営業はそれなりに動けは成果は出ました。
ただ、体にはつけが回りました。
立っている時間が長く、血液が体中には行き渡らない。
エコノミー症候群でしょうか。
血液の塊を除去しました。
ドクターストップで終止符。
私の造ったお酒は「大器晩成」であります。
もうすでに1本も残っておりません。
私の酒人生の中で、とても貴重な体験をさせてもらいました。
丸河屋は創業以来、君盃がおいてあります。
丸河屋が存在する限りは永遠においてある銘柄であります。
お世話をしてくれた阿部杜氏は今は亡き人となりました。
あの時代の写真を見るたびに、ホロってきそうになります。
君盃の市川さん、橋本さん、この場を借りて感謝申し上げます。
次回は第十章「私の静岡酒三十年史後期」を書きます。
「静岡酒、この名役者、この名演技」の第9章です。
「私の静岡酒三十年史中期」
酒屋の酒知らずから一転。
猛勉強の一環として、酒造りもある程度は知らなければ。
本から一通り学んだだけの頭でっかちではいけない。
体でも覚えなければ。
祖父からお世話になっている君盃酒造さんにお願いし、
酒つくりのスタッフである蔵人として扱ってもらうことになりました。
酒造責任者である杜氏は小柄な阿部さん。
阿部さんは標準語をまったく話さず、
何を言っているのかちんぷんかんぷん。
こちらが理解できず、仕事が後手後手になる場面が多く、
いつも怒られていました。
1年目はまったく相手にされず、話しかけてくれることもほぼなかったです。
人間って、役に立たないことが悔しくても涙が出そうになるのですね。
見よう見真似でコツコツと一つづつ覚えていきました。
世間話もしないくらい仕事に集中できたおかげで、
朝一番からその日の最後までの段取りがわかりましたから、
声を掛け合わなくとも、誰が何をするのかがわかり、
私は私なりの仕事ができました。
朝は5時前には蔵元に着き、蔓延する蒸気の中、蒸し米を待ちました。
麹米の引き込みと掛け米の冷やしが次の作業。
200度以上あろうかと思う蒸し米を4度にします。
蒸し米の表面と内面の温度が若干違っていることすら駄目。
朝一番の冷え込みを利用しながら冷やします。
蒸し米は今のように機械からの風を利用しませんでした。
桶に入れて運び、布の上に広げていきます。
かわいい子供に荒風を当ててはいけないとの心配り。
何度も混ぜながら、蒸し米の温度を一定に冷やすと時間は7時くらいに。
杜氏の包丁の音が聞こえてきます。
トトトトトと空腹の私にも響くわけです。
この音が聞こえると、朝一番の仕事ももうすぐ終わり。
君盃酒造の阿部杜氏は朝飯の料理長でもありました。
私は丸河屋の仕事がありますから、ここで店に戻ります。
配達を終えて、お昼は洗米作業。
「おい、若けえの」と一番たくさん運ばせてもらいました。
私はこの時から米の良し悪しを水を通して覚えるようになりました。
水の中に入れた方がよくわかるのです。
洗ってからの米の様子から、その品種が何であるかも大体想像通り。
こういうことがわかるから、職人はやめれないなって気分も理解できます。
もろみの様子(味見)や明日の蒸しの準備をしたら、また丸河屋に。
午前中時間があれば、仕込みをしました。
櫂入れまでしますと、汗ばむくらい。
飲料の仕事は重労働で体力勝負です。
もろみを味見していますと、きき酒能力が上がっているなと実感できます。
神経質くらいの繊細さで接していますから、
醗酵中のアルコールの老ね具合までわかるようになりました。
2年目、私は勝負に出ます。
タンクも勝手に動かして配置。
田植えや刈り取りなども県外でして米を手配。
そうなんです。
できたお酒は全部自分で現金で買い取るから、自分のお酒を造らせて。
わがままを承知で1本造ろうとはじめました。
冷却装置も自前。
酒販店である以上、ここは通らねばいけない壁。
大失敗でもまだまだ先が長いから。
若さですねえ。
私も父も反対しましたが、そんなことはおかまいなしとスタート。
酒造りは私一人ではできません。
杜氏にしてみれば、自分の管理下。
社長にしてみれば、自分の商品。
私は1.8L換算で300本。
好きなようにやらせてもらい純米吟醸を完成させました。
全量買取、丸河屋の冷蔵庫に持ってきました。
お金は銀行から借りて、月々の支払いにしました。
1年かかるかどうかの時期に売り切ることができました。
3年目、気を良くした私は増産します。
300本から600本への挑戦です。
酒造りよりも販売がどうかに挑戦は移っていました。
銀行への支払いは、このお酒だけで毎月20万円。
販路をかなり広げなければなりませんでした。
夕方の6時40分くらいの新幹線で関東方面に営業に行き、
11時40分くらい品川発のムーンライトながらで帰ってきます。
営業はそれなりに動けは成果は出ました。
ただ、体にはつけが回りました。
立っている時間が長く、血液が体中には行き渡らない。
エコノミー症候群でしょうか。
血液の塊を除去しました。
ドクターストップで終止符。
私の造ったお酒は「大器晩成」であります。
もうすでに1本も残っておりません。
私の酒人生の中で、とても貴重な体験をさせてもらいました。
丸河屋は創業以来、君盃がおいてあります。
丸河屋が存在する限りは永遠においてある銘柄であります。
お世話をしてくれた阿部杜氏は今は亡き人となりました。
あの時代の写真を見るたびに、ホロってきそうになります。
君盃の市川さん、橋本さん、この場を借りて感謝申し上げます。
次回は第十章「私の静岡酒三十年史後期」を書きます。
2011年10月20日
静岡酒、この名役者、この名演技 8.
しずおか地酒研究会の鈴木真弓さんのWEB酒場静岡吟醸伝に寄稿しています。
「静岡酒、この名役者、この名演技」の第8章です。
「私の静岡酒三十年史前期」
18歳から家業の丸河屋酒店に従事してきました。
酒屋は自営業なので、生まれてからずっとお酒に囲まれて暮らしてきました。
製品は元々木箱に入れられて運ばれていましたが、時代の変貌でしょうか、
本数が少なくなり、プラスティックへと変わりました。
まずはコカコーラが変わり、その後にビール、そして最後は日本酒も変わるのでありますが、
ほとんどのメーカーがプラスティック箱を使用するようになったのは、平成になってからのことです。
それだけ保守的な業界であるわけです。
一般には知られてはいませんが、業界人は知っていることとして、剣菱の木箱があります。
剣菱は他のメーカー同様に1.8Lが10本入る木箱に入ってくるのですが、
剣菱だけはほぼ新品なのです。
きれいな杉の箱に剣菱の焼印がしてありますので、酒問屋の倉庫の中でも一際目立っていました。
剣菱は越乃寒梅がスターになる前のスターで、さすがは剣菱だなあと箱からも威厳を感じました。
この頃の静岡のお酒はほとんどが灘・伏見の下請けであり、我々はそのことを親からも聞かされてきていましたから、灘・伏見のお酒が一流だと思っていました。
昭和の時代の静岡の酒質は灘・伏見と比べますと甘く薄いような感じでした。
酒販店が取引条件を厳しく言ってきますので、蔵元も薄くしざるを得ません。
その分、糖類などを添加して味を調整していました。
取引条件とは10本買うと1本つけるよというようなことであります。
これでは原料米も酒米を使うこともできませんから、今のような酒質は無理でありました。
条件を提示するということは、それだけ流通量があったということでありますから、
この時代はみんなが儲かっていました。儲けることができたのです。
飲酒スタイルも今のようにきき酒することもありましたが、ほとんどの場合は、酔いにつきました。
ビールだったら何本飲めるか、日本酒だったら何合飲めるか。
私の二十歳の頃はまだまだこんな飲み方が主流でしたから、
私も量を飲むことに努力しました。
挙句の果てには、急性アルコール中毒になり、救急車で運ばれます。
気がついたら仏壇の前に寝かされていました。
お線香をたき、祈っている家族の姿が見えます。
体温が34度を切りそうになり、やばいかもしれないと医師に告げられ、
必死で看病していたというではありませんか。
私は前の晩の事はうら覚えでしたが、家族を心配させてしまって申し訳ない。
酒に従事する者として恥だと猛反省しました。
このことをきっかけにお酒を学ぶという世界に入っていきます。
酒屋の酒知らずからの脱却。
お酒に関する本を読み始めました。
夏の暑い日でも好きな海にも行かずに読書三昧です。
東京は銀座にあった日本酒センターにもよく出向きました。
各地のフェアーをやっていましたから、ここで全国のお酒を知ることができました。
時代は昭和から平成へと移ります。
ボージョレーヌーボーを起点にしたワインブームが起こりました。
後の心臓によいことと、ポリヘェノールの以前のことであります。
ソムリエの資格が騒がれだし、日本酒の資格も動き出しました。
私は勉強ついでだと思って、きき酒師・酒匠・ワインアドバイザー・英検2級を同時期に受験しました。
結果はご想像の通りでございます。
今の私からすれば、すでにプロなのに資格を取ることがどうであるか疑問もありますが、
当時の私からすれば、勉強した何かの証がほしかったのでしょう。
酒類資格に同調した同業者や問屋さん、蔵元も多く、
静岡の蔵元さんらとも知り合いがたくさんできました。
この頃になりますと、静岡の蔵元も下請けをするケースもほぼなくなり、
自分で自分のブランドを築いていく夢溢れるムードに包まれていました。
私は私で自分のブランドを持ちたい。
学問だけではなく、実践的なことでお酒を知りたい。
この欲求は一人の蔵人になることに向います。
私は無理矢理君盃酒造の蔵人の仲間に入れてもらい、酒造を体験させてもらいました。
このことを中心に次回は「私の静岡酒三十年史中期」を書こうかと思います。
「静岡酒、この名役者、この名演技」の第8章です。
「私の静岡酒三十年史前期」
18歳から家業の丸河屋酒店に従事してきました。
酒屋は自営業なので、生まれてからずっとお酒に囲まれて暮らしてきました。
製品は元々木箱に入れられて運ばれていましたが、時代の変貌でしょうか、
本数が少なくなり、プラスティックへと変わりました。
まずはコカコーラが変わり、その後にビール、そして最後は日本酒も変わるのでありますが、
ほとんどのメーカーがプラスティック箱を使用するようになったのは、平成になってからのことです。
それだけ保守的な業界であるわけです。
一般には知られてはいませんが、業界人は知っていることとして、剣菱の木箱があります。
剣菱は他のメーカー同様に1.8Lが10本入る木箱に入ってくるのですが、
剣菱だけはほぼ新品なのです。
きれいな杉の箱に剣菱の焼印がしてありますので、酒問屋の倉庫の中でも一際目立っていました。
剣菱は越乃寒梅がスターになる前のスターで、さすがは剣菱だなあと箱からも威厳を感じました。
この頃の静岡のお酒はほとんどが灘・伏見の下請けであり、我々はそのことを親からも聞かされてきていましたから、灘・伏見のお酒が一流だと思っていました。
昭和の時代の静岡の酒質は灘・伏見と比べますと甘く薄いような感じでした。
酒販店が取引条件を厳しく言ってきますので、蔵元も薄くしざるを得ません。
その分、糖類などを添加して味を調整していました。
取引条件とは10本買うと1本つけるよというようなことであります。
これでは原料米も酒米を使うこともできませんから、今のような酒質は無理でありました。
条件を提示するということは、それだけ流通量があったということでありますから、
この時代はみんなが儲かっていました。儲けることができたのです。
飲酒スタイルも今のようにきき酒することもありましたが、ほとんどの場合は、酔いにつきました。
ビールだったら何本飲めるか、日本酒だったら何合飲めるか。
私の二十歳の頃はまだまだこんな飲み方が主流でしたから、
私も量を飲むことに努力しました。
挙句の果てには、急性アルコール中毒になり、救急車で運ばれます。
気がついたら仏壇の前に寝かされていました。
お線香をたき、祈っている家族の姿が見えます。
体温が34度を切りそうになり、やばいかもしれないと医師に告げられ、
必死で看病していたというではありませんか。
私は前の晩の事はうら覚えでしたが、家族を心配させてしまって申し訳ない。
酒に従事する者として恥だと猛反省しました。
このことをきっかけにお酒を学ぶという世界に入っていきます。
酒屋の酒知らずからの脱却。
お酒に関する本を読み始めました。
夏の暑い日でも好きな海にも行かずに読書三昧です。
東京は銀座にあった日本酒センターにもよく出向きました。
各地のフェアーをやっていましたから、ここで全国のお酒を知ることができました。
時代は昭和から平成へと移ります。
ボージョレーヌーボーを起点にしたワインブームが起こりました。
後の心臓によいことと、ポリヘェノールの以前のことであります。
ソムリエの資格が騒がれだし、日本酒の資格も動き出しました。
私は勉強ついでだと思って、きき酒師・酒匠・ワインアドバイザー・英検2級を同時期に受験しました。
結果はご想像の通りでございます。
今の私からすれば、すでにプロなのに資格を取ることがどうであるか疑問もありますが、
当時の私からすれば、勉強した何かの証がほしかったのでしょう。
酒類資格に同調した同業者や問屋さん、蔵元も多く、
静岡の蔵元さんらとも知り合いがたくさんできました。
この頃になりますと、静岡の蔵元も下請けをするケースもほぼなくなり、
自分で自分のブランドを築いていく夢溢れるムードに包まれていました。
私は私で自分のブランドを持ちたい。
学問だけではなく、実践的なことでお酒を知りたい。
この欲求は一人の蔵人になることに向います。
私は無理矢理君盃酒造の蔵人の仲間に入れてもらい、酒造を体験させてもらいました。
このことを中心に次回は「私の静岡酒三十年史中期」を書こうかと思います。
2011年10月19日
静岡酒、この名役者、この名演技 7.
しずおか地酒研究会の鈴木真弓さんのWEB酒場静岡吟醸伝に寄稿しています。
「静岡酒、この名役者、この名演技」の第7章です。
「静岡酒の新時代は全国の新時代」
全国・各地の鑑評会で猛威を振るうカプロン酸系の吟醸酒。
静岡など、イソアミル系(熊本・協会9号系)のタイプに新しい夜明けが来るのか?
日本酒自体が決められた原料を元に、麹菌と酵母菌に醗酵をさせていく
製造方法であり、これが変わらなければ、香味も変わらない。
これまでと違ったお米や微生物から作れば香りの成分も変わることもあるでしょう。
吟醸酒は醗酵由来の香りが主体。
酵母の違いによって与えられるのは香りの成分のバランス違いと言っても過言ではないでしょう。
つまり「イソアミル系」と「カプロン酸系」の香りのタイプに大きく2つに分かれます。
あくまで従来通りの静岡型の「イソアミル系」で勝負していくには、香りの強さだけではなく、
全体のバランスや味わいのきれいさに特徴を出していくべき。
そもそも静岡酵母開発は香りだけで考案されてきたわけではない。
静岡酵母を使った静岡型の原点とは何か?
「よ~し、もう一度静岡酵母で勝負していこう!」
「静岡酵母で全国新酒鑑評会で金賞を取ろうではないか。」
こんな合言葉があったかどうかはわかりません。
しかし、これまで他の酵母を使って出品していた蔵元たちが、
またもとの静岡酵母に戻って出品しはじめました。
平成10年代の後半のことであります。
熊本酵母で作った熊本のお酒が毎年のように金賞を受賞しています。
同系の静岡酵母で作ったお酒だって、金賞を受賞できるはず。
実質平成23年の全国においては、金賞は開運が唯一。
これまでだったら、なんだあ、たったの一つか。
と見切っていたかもしれません。
でも今は一つでもが雄たけびであります。
全国ではなく、静岡県内に目を向けてみましょう。
静岡県清酒鑑評会は全国の審査基準と違い、静岡独自の基準を持っています。
極端に言いますと、審査はどこまで理想の静岡型に近づいているのか。
清酒の良し悪しは香りが際立って高いことばかりではなく、味わいのきれいさ、まるさ、
バランス、それから余韻まで含まれています。
静岡は静岡ルールで行っています。
今後、静岡以外の各地でそれぞれのルールに従った鑑評会が開催されていくことでしょう。
これから全国の吟醸酒は様々な審査基準によって磨かれた素晴らしいお酒が誕生していくことでしょう。
静岡酵母で酵母開発をリードしてきた静岡県。
これからは鑑評会のありかたについてもリードしていくことでしょう。
つまり、静岡酒の新時代は全国の新時代へとなることでしょう。
明治の終盤にはじまった全国の鑑評会は、数年後には全国新酒鑑評会と全国清酒鑑評会に
分かれたり、灘酒のボイコットなども起こりました。
原因は審査基準であります。
あの時は「硬水仕込み」と「軟水仕込み」のお酒の対決になりました。
今は使用米で分類されてはいますが、香りのタイプの対決になってもいます。
時代は再び繰り返されるのか?
今後の吟醸酒から目を離せません。
今回のさきがけは静岡からであります。
次回は私の静岡酒三十年史の前半をお届けします。
「静岡酒、この名役者、この名演技」の第7章です。
「静岡酒の新時代は全国の新時代」
全国・各地の鑑評会で猛威を振るうカプロン酸系の吟醸酒。
静岡など、イソアミル系(熊本・協会9号系)のタイプに新しい夜明けが来るのか?
日本酒自体が決められた原料を元に、麹菌と酵母菌に醗酵をさせていく
製造方法であり、これが変わらなければ、香味も変わらない。
これまでと違ったお米や微生物から作れば香りの成分も変わることもあるでしょう。
吟醸酒は醗酵由来の香りが主体。
酵母の違いによって与えられるのは香りの成分のバランス違いと言っても過言ではないでしょう。
つまり「イソアミル系」と「カプロン酸系」の香りのタイプに大きく2つに分かれます。
あくまで従来通りの静岡型の「イソアミル系」で勝負していくには、香りの強さだけではなく、
全体のバランスや味わいのきれいさに特徴を出していくべき。
そもそも静岡酵母開発は香りだけで考案されてきたわけではない。
静岡酵母を使った静岡型の原点とは何か?
「よ~し、もう一度静岡酵母で勝負していこう!」
「静岡酵母で全国新酒鑑評会で金賞を取ろうではないか。」
こんな合言葉があったかどうかはわかりません。
しかし、これまで他の酵母を使って出品していた蔵元たちが、
またもとの静岡酵母に戻って出品しはじめました。
平成10年代の後半のことであります。
熊本酵母で作った熊本のお酒が毎年のように金賞を受賞しています。
同系の静岡酵母で作ったお酒だって、金賞を受賞できるはず。
実質平成23年の全国においては、金賞は開運が唯一。
これまでだったら、なんだあ、たったの一つか。
と見切っていたかもしれません。
でも今は一つでもが雄たけびであります。
全国ではなく、静岡県内に目を向けてみましょう。
静岡県清酒鑑評会は全国の審査基準と違い、静岡独自の基準を持っています。
極端に言いますと、審査はどこまで理想の静岡型に近づいているのか。
清酒の良し悪しは香りが際立って高いことばかりではなく、味わいのきれいさ、まるさ、
バランス、それから余韻まで含まれています。
静岡は静岡ルールで行っています。
今後、静岡以外の各地でそれぞれのルールに従った鑑評会が開催されていくことでしょう。
これから全国の吟醸酒は様々な審査基準によって磨かれた素晴らしいお酒が誕生していくことでしょう。
静岡酵母で酵母開発をリードしてきた静岡県。
これからは鑑評会のありかたについてもリードしていくことでしょう。
つまり、静岡酒の新時代は全国の新時代へとなることでしょう。
明治の終盤にはじまった全国の鑑評会は、数年後には全国新酒鑑評会と全国清酒鑑評会に
分かれたり、灘酒のボイコットなども起こりました。
原因は審査基準であります。
あの時は「硬水仕込み」と「軟水仕込み」のお酒の対決になりました。
今は使用米で分類されてはいますが、香りのタイプの対決になってもいます。
時代は再び繰り返されるのか?
今後の吟醸酒から目を離せません。
今回のさきがけは静岡からであります。
次回は私の静岡酒三十年史の前半をお届けします。
2011年10月18日
静岡酒、この名役者、この名演技 6.
しずおか地酒研究会の鈴木真弓さんのWEB酒場静岡吟醸伝に寄稿しています。
「静岡酒、この名役者、この名演技」の第6章です。
「静岡酒 苦難の時代」
金沢酵母が開発されて以降、それを使ったお酒が全国新酒鑑評会でも好成績を取り出しました。
全国の蔵元はこぞって、金沢酵母を使った吟醸酒を出品するようになりました。
醸造協会も金沢酵母を協会14号として、全国に配布し始めました。
時代はこれまでの熊本酵母から金沢酵母へと移ったのです。
静岡酵母も熊本系であるために、これまでのように高評価を得られなくなりました。
まさに「新しい潮流」が生まれました。
新旧の潮流では、お酒の香りの成分が違います。
これまでは「酢酸イソアミル」と「イソアミルアルコール」が主体であり、
新しい潮流は「カプロン酸」と「カプロン酸エチル」が主体です。
これらを「イソアミル系」と「カプロン酸系」と呼ぶようにします。
熊本酵母は「イソアミル系」が「カプロン酸系」よりも圧倒的に多く、
香りのタイプはバナナ型と表されています。
金沢酵母も質量としては、「イソアミル系」の方が若干多いのですが、
人間が香りとして感じるのは「カプロン酸系」の方が大きくなります。
同じppmの場合であっても、「カプロン酸系」の香りは強く感じられます。
そのために金沢酵母は「カプロン酸系」の一つに数えられています。
香りのタイプはライチとか赤い果実が代表です。
静岡県の蔵元もこの新しい潮流である金沢酵母をこぞって使い出しました。
県としてもこの潮流を受け入れざるを得ません。
金沢酵母を教育しなおした静岡県版金沢酵母の配布まではじめました。
これまで静岡酵母の恩恵に浸っていた蔵元が手のひらを返したかのように
金沢酵母へと移りました。
その結果として、全国新酒鑑評会でもまずまずの成績を残しますが、
静岡酵母全盛期までには遠く及びません。
酵母の進化は金沢酵母にとどまりません。
さらに「カプロン酸系」を強く出す酵母が生まれ続きます。
月桂冠がセロトニン耐性酵母を誕生させてからというもの、
次々と「カプロン酸系」酵母が生み出されました。
平成10年頃からは金沢酵母に代わって、明利酵母が主役となります。
明利酵母は強烈とも言えるほどの「カプロン酸系」の香りを造ります。
香りのタイプはリンゴ型であります。
全国の潮流も明利酵母への様変わりしはじめました。
静岡県内においても、金沢酵母を使っていた蔵元は明利酵母へと移りました。
さて、香りの高く出やすい明利酵母を使い始めた蔵が多くなった静岡吟醸、
全国新酒鑑評会での結果は。
・
・
・
金沢酵母時代よりも結果を残せません。
静岡県のお酒は素晴らしいとの名声は勝ち得はじめてから、
実質の全国新酒鑑評会での成績は右肩下がりになってしまいました。
全国新酒鑑評会などの結果がすべてではありませんが、
これを期に全国区となったため、どうしても気になる指標にはなってしまいます。
全国新酒鑑評会の成績だけを見ますと、明利酵母を使うようになってからの静岡酒は、
静岡酵母誕生前の状況に等しくなったと言えましょう。
主はこの状況をお嘆きになられました。
「良酒三蔵」と静岡経済研究所の紙面に書き、静岡酒の状況を説明されました。
私なりの要約ですが、静岡県内で真のお酒を造っているのは三蔵しかない。
その三蔵は静岡酵母以外の酵母は使っておらず、生粋の静岡型と評されている
「国香」「満寿一」「喜久醉」であります。
主は静岡酵母を使わず、明利酵母を使っていることを嘆いているわけではありません。
通年販売するお酒にとって、カプロン酸は消費者にとって、有益だけではありません。
搾った時点の新酒では、デリシャスリンゴのような香りがあります。
美味であります。
熟成の段階において、打って変わったかのような、飲みにくい匂いへと変化してしまいます。
あるとき急に変化してしまうのです。
世界中の酒類の中で、カプロン酸系が主役の香りを持つものがあるのであろうか?
それは日本酒と焼酎くらいだけではないでしょうか。
・蔵元としてお酒は農産加工品であり、商品であるがため、市場が要求するようなお酒を造るのも使命。
・一方、鑑評会などのコンテストで優秀な成績も取りたい。
・そして、自社ブランドだけではなく、静岡酒というブランドも大事。
金沢酵母誕生までは、上の3つの歯車がうまくいっていましたが、
それ以降、明利酵母全盛下にあっては、バランスもうまくとれません。
さて、この状況下、どうやって乗り切っていくのか。
新しい夜明けは来るのか。
次回につづくといたしましょう。
「静岡酒、この名役者、この名演技」の第6章です。
「静岡酒 苦難の時代」
金沢酵母が開発されて以降、それを使ったお酒が全国新酒鑑評会でも好成績を取り出しました。
全国の蔵元はこぞって、金沢酵母を使った吟醸酒を出品するようになりました。
醸造協会も金沢酵母を協会14号として、全国に配布し始めました。
時代はこれまでの熊本酵母から金沢酵母へと移ったのです。
静岡酵母も熊本系であるために、これまでのように高評価を得られなくなりました。
まさに「新しい潮流」が生まれました。
新旧の潮流では、お酒の香りの成分が違います。
これまでは「酢酸イソアミル」と「イソアミルアルコール」が主体であり、
新しい潮流は「カプロン酸」と「カプロン酸エチル」が主体です。
これらを「イソアミル系」と「カプロン酸系」と呼ぶようにします。
熊本酵母は「イソアミル系」が「カプロン酸系」よりも圧倒的に多く、
香りのタイプはバナナ型と表されています。
金沢酵母も質量としては、「イソアミル系」の方が若干多いのですが、
人間が香りとして感じるのは「カプロン酸系」の方が大きくなります。
同じppmの場合であっても、「カプロン酸系」の香りは強く感じられます。
そのために金沢酵母は「カプロン酸系」の一つに数えられています。
香りのタイプはライチとか赤い果実が代表です。
静岡県の蔵元もこの新しい潮流である金沢酵母をこぞって使い出しました。
県としてもこの潮流を受け入れざるを得ません。
金沢酵母を教育しなおした静岡県版金沢酵母の配布まではじめました。
これまで静岡酵母の恩恵に浸っていた蔵元が手のひらを返したかのように
金沢酵母へと移りました。
その結果として、全国新酒鑑評会でもまずまずの成績を残しますが、
静岡酵母全盛期までには遠く及びません。
酵母の進化は金沢酵母にとどまりません。
さらに「カプロン酸系」を強く出す酵母が生まれ続きます。
月桂冠がセロトニン耐性酵母を誕生させてからというもの、
次々と「カプロン酸系」酵母が生み出されました。
平成10年頃からは金沢酵母に代わって、明利酵母が主役となります。
明利酵母は強烈とも言えるほどの「カプロン酸系」の香りを造ります。
香りのタイプはリンゴ型であります。
全国の潮流も明利酵母への様変わりしはじめました。
静岡県内においても、金沢酵母を使っていた蔵元は明利酵母へと移りました。
さて、香りの高く出やすい明利酵母を使い始めた蔵が多くなった静岡吟醸、
全国新酒鑑評会での結果は。
・
・
・
金沢酵母時代よりも結果を残せません。
静岡県のお酒は素晴らしいとの名声は勝ち得はじめてから、
実質の全国新酒鑑評会での成績は右肩下がりになってしまいました。
全国新酒鑑評会などの結果がすべてではありませんが、
これを期に全国区となったため、どうしても気になる指標にはなってしまいます。
全国新酒鑑評会の成績だけを見ますと、明利酵母を使うようになってからの静岡酒は、
静岡酵母誕生前の状況に等しくなったと言えましょう。
主はこの状況をお嘆きになられました。
「良酒三蔵」と静岡経済研究所の紙面に書き、静岡酒の状況を説明されました。
私なりの要約ですが、静岡県内で真のお酒を造っているのは三蔵しかない。
その三蔵は静岡酵母以外の酵母は使っておらず、生粋の静岡型と評されている
「国香」「満寿一」「喜久醉」であります。
主は静岡酵母を使わず、明利酵母を使っていることを嘆いているわけではありません。
通年販売するお酒にとって、カプロン酸は消費者にとって、有益だけではありません。
搾った時点の新酒では、デリシャスリンゴのような香りがあります。
美味であります。
熟成の段階において、打って変わったかのような、飲みにくい匂いへと変化してしまいます。
あるとき急に変化してしまうのです。
世界中の酒類の中で、カプロン酸系が主役の香りを持つものがあるのであろうか?
それは日本酒と焼酎くらいだけではないでしょうか。
・蔵元としてお酒は農産加工品であり、商品であるがため、市場が要求するようなお酒を造るのも使命。
・一方、鑑評会などのコンテストで優秀な成績も取りたい。
・そして、自社ブランドだけではなく、静岡酒というブランドも大事。
金沢酵母誕生までは、上の3つの歯車がうまくいっていましたが、
それ以降、明利酵母全盛下にあっては、バランスもうまくとれません。
さて、この状況下、どうやって乗り切っていくのか。
新しい夜明けは来るのか。
次回につづくといたしましょう。
2011年10月03日
本気のきき酒トレーニング@神田「チームやました」
東京は神田にて「本気のきき酒トレーニング」講座を開催。
チームやましたさんからのご依頼でありました。
きき酒したお酒の数は42本。
時間にして4時間弱。
4対4、5対5のマッチングと、
6対6、7対7のランキングをしてもらいました。
目指せ きき酒 日本一
全国きき酒選手権での活躍を期待しております。
チームやましたさんからのご依頼でありました。
きき酒したお酒の数は42本。
時間にして4時間弱。
4対4、5対5のマッチングと、
6対6、7対7のランキングをしてもらいました。
目指せ きき酒 日本一
全国きき酒選手権での活躍を期待しております。
2011年09月24日
2011年09月23日
2011年09月13日
日本酒ナビゲーター取得講座@横浜の佐藤様宅
横浜のお客様宅において日本酒ナビゲーター取得講座を開講しました。

集まっていただいたのは、佐藤様のご友人たち。
5人の男性と3名の美女。
日本酒の美容効果大の証明者たちです。
15時スタートで真剣な講義は16時までの1時間。
その後はきき酒を40分間。
次にお酒とお料理の相性診断を1時間くらいやったでしょうか。
18時30分からは懇親会になり、いろんなお酒とお料理を
みなさんでご堪能くださいました。
ご友人の集まりですと、一杯のお酒からフルスロットルで盛り上がります。
宴会の前の余興が講義。
おつなものではありませんか。
今回は佐藤様のご好意もあり、お一人様すべての経費を入れても、
6,000円でおさめることができました。
この中には2,500円の日本酒ナビゲーター認定料も含まれています。
10名くらい集まっていただけますと、ご負担も少なく開講できます。

御受講ありがとうございました。
佐藤様にも大変おせわになりました。
集まっていただいたのは、佐藤様のご友人たち。
5人の男性と3名の美女。
日本酒の美容効果大の証明者たちです。
15時スタートで真剣な講義は16時までの1時間。
その後はきき酒を40分間。
次にお酒とお料理の相性診断を1時間くらいやったでしょうか。
18時30分からは懇親会になり、いろんなお酒とお料理を
みなさんでご堪能くださいました。
ご友人の集まりですと、一杯のお酒からフルスロットルで盛り上がります。
宴会の前の余興が講義。
おつなものではありませんか。
今回は佐藤様のご好意もあり、お一人様すべての経費を入れても、
6,000円でおさめることができました。
この中には2,500円の日本酒ナビゲーター認定料も含まれています。
10名くらい集まっていただけますと、ご負担も少なく開講できます。
御受講ありがとうございました。
佐藤様にも大変おせわになりました。
タグ :日本酒ナビゲーター
2011年09月12日
2011年09月12日
東海大学短期大学部「世界に広がる日本酒」
9月9日の晩、東海大学短期大学部にて講演してきました。
フードサイエンスシリーズの一環としての登場です。
テーマは「世界に広がる日本酒 これだけは知っておきたい」
日本酒の基本的なこと全般にわたっての話。
お酒を飲まれない方でもわかる内容にしました。

受講者は50名くらいにも達しました。
ご参加ありがとうございました。
よくぞ来ていただきました。
私なんかで大丈夫かなという不安は今でもありますが、
90分間気合を入れてがんばりました。
「先生と言われたいほどの馬鹿はいない」
ついに酒屋の親父は大学でも教鞭をとっています。
フードサイエンスシリーズの一環としての登場です。
テーマは「世界に広がる日本酒 これだけは知っておきたい」
日本酒の基本的なこと全般にわたっての話。
お酒を飲まれない方でもわかる内容にしました。
受講者は50名くらいにも達しました。
ご参加ありがとうございました。
よくぞ来ていただきました。
私なんかで大丈夫かなという不安は今でもありますが、
90分間気合を入れてがんばりました。
「先生と言われたいほどの馬鹿はいない」
ついに酒屋の親父は大学でも教鞭をとっています。
タグ :日本酒
2011年09月05日
料理酒とみりんの講座@いいんでない会
静岡市葵区アイセル21におきまして「みりんと料理酒」の講座を開講。
「いいんでない会」さんが主催で御呼ばれしました。
みりんや料理酒って、いったい何なのか?
どんな種類があるのか?

これまで発売されてきました商品を見ていきますと、
日本の歴史にいかにお酒が左右されてきたか、
いかに人々に喜ばれるように造られてきたのか。
そんな裏事情も垣間見られます。
身近なみりんや料理酒、この正体を知っている方々は、
どのくらいおりましょう。
それぞれに個性があって、誕生や存在理由もはっきりしている。
日本酒については原材料表示別にこんなにもあるのだと知っていただきました。
1時間の講演がご質問が多かったために2時間数十分にも及びました。
けっこうお酒のことって、わかっているようでわかっていない。
この機会にいろいろと聞いてみようと、みなさんお熱心でありました。

このようにお座敷でやるのも日本的でいいものですね。
こういった講演・講座もお引き受けしています。
お気軽に相談してくださいね。
次回の講演・講座は9日に東海大学短期大学部で開講。
お題は「世界に広がる日本酒 これだけは知っておきたい」
その次は翌日10日に横浜の一般消費者宅にて、
日本酒ナビゲーター取得講座を開講します。
お酒の講演・講座も普及してきています。
がんばっています。
「いいんでない会」さんが主催で御呼ばれしました。
みりんや料理酒って、いったい何なのか?
どんな種類があるのか?
これまで発売されてきました商品を見ていきますと、
日本の歴史にいかにお酒が左右されてきたか、
いかに人々に喜ばれるように造られてきたのか。
そんな裏事情も垣間見られます。
身近なみりんや料理酒、この正体を知っている方々は、
どのくらいおりましょう。
それぞれに個性があって、誕生や存在理由もはっきりしている。
日本酒については原材料表示別にこんなにもあるのだと知っていただきました。
1時間の講演がご質問が多かったために2時間数十分にも及びました。
けっこうお酒のことって、わかっているようでわかっていない。
この機会にいろいろと聞いてみようと、みなさんお熱心でありました。
このようにお座敷でやるのも日本的でいいものですね。
こういった講演・講座もお引き受けしています。
お気軽に相談してくださいね。
次回の講演・講座は9日に東海大学短期大学部で開講。
お題は「世界に広がる日本酒 これだけは知っておきたい」
その次は翌日10日に横浜の一般消費者宅にて、
日本酒ナビゲーター取得講座を開講します。
お酒の講演・講座も普及してきています。
がんばっています。