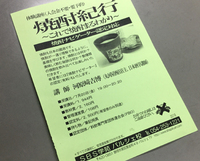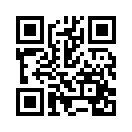2011年11月11日
静岡酒、この名役者、この名演技 第12章
しずおか地酒研究会の鈴木真弓さんのWEB酒場静岡吟醸伝に寄稿しています。
「静岡酒、この名役者、この名演技」の第12章です。
「歴史に残したい静岡の名酒たち その2.」
ブームには必ず立役者がいる。
静岡吟醸ブームの立役者について第十一章で書きました。
歴史に残したい名酒があるからこそ、ブームもあるわけです。
そんな歴史に残したい静岡の名酒としてまず開運の大吟醸を書きました。
今回はその2.です。
静岡酵母という宝を得た静岡酒。
まさに打ち出の小槌。
静岡酵母を使ったお酒をいち早く販売チャンネルに浸透させる。
そこが勝負の分かれ目であったような気がしています。
先手必勝、先発隊断然優位でした。
蔵元ではなく銘柄、まさにブランドが一人歩きした「おんな泣かせ」、
そして首都圏の業務用を席巻した「磯自慢本醸造」。
これらは間違いなく歴史に残したい静岡酒ですが、
この2つのお酒についてはこれまで書いてきましたので、
そこを参照してくださればと思います。
「おんな泣かせ」は第2章「連戦連勝 その第一歩」。
「磯自慢本醸造」は第3章「連戦連勝 首都制圧」。
全国的な吟醸酒ブームは平成とともにやってきた感があります。
この頃の酒米は五百万石が主流で生産量も一番でした。
山田錦は高嶺の花であり、高価でしかも静岡では栽培しにくかったです。
主産地の兵庫からは、こちらの希望数量は回してもらえなかったこともありました。
総合的に五百万石に人気が集中し、北陸から県全体で数量を
まとめるなどして仕入れていました。
したがって、平成がはじまってまもない吟醸酒ブームの時代、
静岡酒は五百万石が主流で一般的であり、
山田錦は酒母や麹米として使われていました。
静岡酵母 + 五百万石 = 静岡吟醸
果たしてどんなお酒を想像できるのでしょう?
どんな銘柄が思い当たりますか?
私はこのお酒を飲んだ瞬間に、平成の吟醸酒ブーム真っ只中の
静岡吟醸を思い出さずにはいられませんでした。
まさにあの頃の主流の味。
みんなが恋した静岡らしい吟醸香。
静岡酵母と五百万石が奏でるハーモニーであります。
そのお酒とは ・・・
・・・ 緑の英君であります。
「緑の英君って何だ?」
と思いながら口をつけた瞬間。
忘れもしません。
ほろっときそうになりました。
「ああ、これだよ。これなんだよ。」
「この道、静岡酒のこの道を通ったんだ。」
「この香り、この味わい。この余韻。」
これは後世に伝えなくてはいけない酒質。
平成23年、2011年の今では滅多に見かけないタイプ。
いまでのこの酒質を維持し、製造している英君さんに感謝。
そんな思いで、軽やかな静岡酒ですが、重い一杯を飲みました。
私がこのタイプの英君をはじめて飲んだのは1990年(平成2年)の冬。
静岡市葵区にあった本多和洋酒で買った「ごせっぽい」でした。
土産っぽいネーミングだから大したことないなと思いつつ、
ギフト箱を開けますと、ぷ~んと湧き上がる吟醸香にビックリ。
作り立てなのかなと思いましたが、箱からの匂いは酸化臭が伴うのが普通。
しかし「ごせっぽい」が入ったその箱からは、
酸化臭も感じさせないくらい静岡吟醸香が立っていました。
箱からの香りすらこれほどのものです。
お酒は”昇る朝日の静岡酒”の勢いを持った明るい光沢を持った吟醸酒。
甘辛ピン!の三拍子に深みのある旨味。
第一印象もいいですし、飲み飽きしない酒通好み。
静岡のお酒ってこんなに美味しくなったんだなあと
惚れ惚れしたことを鮮明におぼえています。
「ごせっぽい」は当時2級酒でした。
蔵元さんの話ですと、720mlで1,500円。
福井県産の五百万石(精米歩合55%)を使用。
吟醸酒でありました。
現在はこの銘柄は造られていないそうです。
私の脳裏にはっきりと「ごせっぽい」の印象が残っていましたので、
緑の英君を飲んだ瞬間に「ごせっぽい」が蘇りました。
「緑の英君」はこれまで通ってきた静岡吟醸の生き証人のようなお酒。
歴史に残したい静岡の名酒であります。
「静岡酒、この名役者、この名演技」の第12章です。
「歴史に残したい静岡の名酒たち その2.」
ブームには必ず立役者がいる。
静岡吟醸ブームの立役者について第十一章で書きました。
歴史に残したい名酒があるからこそ、ブームもあるわけです。
そんな歴史に残したい静岡の名酒としてまず開運の大吟醸を書きました。
今回はその2.です。
静岡酵母という宝を得た静岡酒。
まさに打ち出の小槌。
静岡酵母を使ったお酒をいち早く販売チャンネルに浸透させる。
そこが勝負の分かれ目であったような気がしています。
先手必勝、先発隊断然優位でした。
蔵元ではなく銘柄、まさにブランドが一人歩きした「おんな泣かせ」、
そして首都圏の業務用を席巻した「磯自慢本醸造」。
これらは間違いなく歴史に残したい静岡酒ですが、
この2つのお酒についてはこれまで書いてきましたので、
そこを参照してくださればと思います。
「おんな泣かせ」は第2章「連戦連勝 その第一歩」。
「磯自慢本醸造」は第3章「連戦連勝 首都制圧」。
全国的な吟醸酒ブームは平成とともにやってきた感があります。
この頃の酒米は五百万石が主流で生産量も一番でした。
山田錦は高嶺の花であり、高価でしかも静岡では栽培しにくかったです。
主産地の兵庫からは、こちらの希望数量は回してもらえなかったこともありました。
総合的に五百万石に人気が集中し、北陸から県全体で数量を
まとめるなどして仕入れていました。
したがって、平成がはじまってまもない吟醸酒ブームの時代、
静岡酒は五百万石が主流で一般的であり、
山田錦は酒母や麹米として使われていました。
静岡酵母 + 五百万石 = 静岡吟醸
果たしてどんなお酒を想像できるのでしょう?
どんな銘柄が思い当たりますか?
私はこのお酒を飲んだ瞬間に、平成の吟醸酒ブーム真っ只中の
静岡吟醸を思い出さずにはいられませんでした。
まさにあの頃の主流の味。
みんなが恋した静岡らしい吟醸香。
静岡酵母と五百万石が奏でるハーモニーであります。
そのお酒とは ・・・
・・・ 緑の英君であります。
「緑の英君って何だ?」
と思いながら口をつけた瞬間。
忘れもしません。
ほろっときそうになりました。
「ああ、これだよ。これなんだよ。」
「この道、静岡酒のこの道を通ったんだ。」
「この香り、この味わい。この余韻。」
これは後世に伝えなくてはいけない酒質。
平成23年、2011年の今では滅多に見かけないタイプ。
いまでのこの酒質を維持し、製造している英君さんに感謝。
そんな思いで、軽やかな静岡酒ですが、重い一杯を飲みました。
私がこのタイプの英君をはじめて飲んだのは1990年(平成2年)の冬。
静岡市葵区にあった本多和洋酒で買った「ごせっぽい」でした。
土産っぽいネーミングだから大したことないなと思いつつ、
ギフト箱を開けますと、ぷ~んと湧き上がる吟醸香にビックリ。
作り立てなのかなと思いましたが、箱からの匂いは酸化臭が伴うのが普通。
しかし「ごせっぽい」が入ったその箱からは、
酸化臭も感じさせないくらい静岡吟醸香が立っていました。
箱からの香りすらこれほどのものです。
お酒は”昇る朝日の静岡酒”の勢いを持った明るい光沢を持った吟醸酒。
甘辛ピン!の三拍子に深みのある旨味。
第一印象もいいですし、飲み飽きしない酒通好み。
静岡のお酒ってこんなに美味しくなったんだなあと
惚れ惚れしたことを鮮明におぼえています。
「ごせっぽい」は当時2級酒でした。
蔵元さんの話ですと、720mlで1,500円。
福井県産の五百万石(精米歩合55%)を使用。
吟醸酒でありました。
現在はこの銘柄は造られていないそうです。
私の脳裏にはっきりと「ごせっぽい」の印象が残っていましたので、
緑の英君を飲んだ瞬間に「ごせっぽい」が蘇りました。
「緑の英君」はこれまで通ってきた静岡吟醸の生き証人のようなお酒。
歴史に残したい静岡の名酒であります。
焼酎ナビゲーター取得講座開講だよ!
東海大学短期大学部「フードサイエンス」にて講演
フードサイエンス開講迫る!
熊本のお酒のお勉強
日本酒ナビゲーター・焼酎ナビゲーター認定講座 丸河屋酒店内
イチゴ酒とコーヒー酒講座@藤枝市
東海大学短期大学部「フードサイエンス」にて講演
フードサイエンス開講迫る!
熊本のお酒のお勉強
日本酒ナビゲーター・焼酎ナビゲーター認定講座 丸河屋酒店内
イチゴ酒とコーヒー酒講座@藤枝市
Posted by 丸河屋酒店 at 14:30│Comments(0)
│講演・講座・執筆