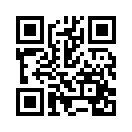2011年08月29日
9月9日は東海大学短期大学部で開講
静岡市柚木にあります東海大学短期大学部で日本酒についてお話します。
日時は9月9日の夜7時から8時半まで。
会費は無料。(だからお酒はでません)
事前申し込みの必要はなし。
テーマは「世界に広がる日本酒、これだけは知っておきたい」。
会場の東海大学短期大学部は国道一号線の柚木の交差点を入った奥。
静岡鉄道の柚木駅から歩いて数分。
国道や駅からも見えますので、すぐにわかります。

一つだけ明かりがついている部屋があります。
そこが教室です。
入り口はこちら。

右にエレベーターがあり、会場は4階です。
(なお、1階食堂のかけそばは150円)
(しかし、夜間は営業外)
教室の入り口です。

ここで私が待っています。
日本酒のこと、ちょっとでもご興味がありましたら、
時間をつくって、足をお運びください。
日時は9月9日の夜7時から8時半まで。
会費は無料。(だからお酒はでません)
事前申し込みの必要はなし。
テーマは「世界に広がる日本酒、これだけは知っておきたい」。
会場の東海大学短期大学部は国道一号線の柚木の交差点を入った奥。
静岡鉄道の柚木駅から歩いて数分。
国道や駅からも見えますので、すぐにわかります。
一つだけ明かりがついている部屋があります。
そこが教室です。
入り口はこちら。
右にエレベーターがあり、会場は4階です。
(なお、1階食堂のかけそばは150円)
(しかし、夜間は営業外)
教室の入り口です。
ここで私が待っています。
日本酒のこと、ちょっとでもご興味がありましたら、
時間をつくって、足をお運びください。
2011年08月22日
TFO文化祭で講演@渋谷
8月6日の土曜日の午後。
渋谷は水道局跡地にありますアートギャラリーにて
凸版ファームズオペレーション様の文化祭が開催されました。
私はありがたいことにお酒の講師として呼ばれ、
お酒の流儀と銘打った話しを4つさせてもらいました。

第一部
「パパママのワンランク上を目指すお酒の流儀」
・食卓に彩を添える今夜の一本
・これでパパもママも今夜も笑顔
第二部
「ビジネスマンきらり役立つ流儀」
・国内、海外でこれだけは知っておきたいお酒のこと
・お酒でライバルと差がつく
各講演は20分ほど。
会場内は飲酒が出来ませんので、お酒は見るだけ。
夏におすすめの食材と夏の日本酒とカレーにあうワインを持っていきました。

しし唐、唐辛子、伏見唐辛子、万願寺唐辛子、ピーマン(緑・赤)
パプリカ(緑、黄、橙、赤)

七田夏純、天山夏吟、鶴齢超辛口

真夏の昼間からお酒抜きでお酒の話を聞くのも、
ちょっとした苦痛だったかもしれません。
各講目ごとに拍手をいただけて、まずまずの手応えを感じました。
今年は今回のようにお酒を提供せずに話をすることが9月にもあります。
講師オーディションを含めれば、三ヶ月連続になります。
講演内容も時代とともに変化していきます。

最近はこんな格好でお話させてもらっています。
渋谷は水道局跡地にありますアートギャラリーにて
凸版ファームズオペレーション様の文化祭が開催されました。
私はありがたいことにお酒の講師として呼ばれ、
お酒の流儀と銘打った話しを4つさせてもらいました。
第一部
「パパママのワンランク上を目指すお酒の流儀」
・食卓に彩を添える今夜の一本
・これでパパもママも今夜も笑顔
第二部
「ビジネスマンきらり役立つ流儀」
・国内、海外でこれだけは知っておきたいお酒のこと
・お酒でライバルと差がつく
各講演は20分ほど。
会場内は飲酒が出来ませんので、お酒は見るだけ。
夏におすすめの食材と夏の日本酒とカレーにあうワインを持っていきました。
しし唐、唐辛子、伏見唐辛子、万願寺唐辛子、ピーマン(緑・赤)
パプリカ(緑、黄、橙、赤)
七田夏純、天山夏吟、鶴齢超辛口
真夏の昼間からお酒抜きでお酒の話を聞くのも、
ちょっとした苦痛だったかもしれません。
各講目ごとに拍手をいただけて、まずまずの手応えを感じました。
今年は今回のようにお酒を提供せずに話をすることが9月にもあります。
講師オーディションを含めれば、三ヶ月連続になります。
講演内容も時代とともに変化していきます。
最近はこんな格好でお話させてもらっています。
2011年08月21日
第二回講師オーディション本選結果
7月24日に講師オーディションの本選に出場しました。
映像関係会社、出版社、主催者の審査員と有料観覧者の
あわせて100名以上が会場にいて、独特のムードの中、
私は4番目に登場しました。
10分間の持ち時間をふるに使い、お酒の価値などを話しました。
どうしてもやりたい一発芸もでき、今回のための衣装も着れて、
自分としては満足の10分間ではありました。
結果は何も起こらなかったです。
つまり入賞などはしませんでした。
静岡から、また東京の日本酒講座受講生も来て貰い、
入賞くらいできれば格好よかったのですが。
お疲れさん会を新橋でやってもらって、帰ってきました。
予選から本選までは4日。
本選は予選と違った話をするのがルール。
4日間でよく本選の話しを組み立てることができたことは、
自分にとっての収穫になりました。
今回のエントリーで10分間スピーチの方法がわかり、
アウェイの場でやった経験もこれからも講師業に役立ちそうです。
エントリー料から衣装代や交通費などを含めますと、
きき酒師受講代金に迫るくらいの金額が必要となりますので、
来年も参加とはいかないでしょうが、今度このような場がありましたら、
笑いなどよりも、骨があって味のある話しができればと思っています。
応援に来てくれた方。
どうもありがとうございました。
映像関係会社、出版社、主催者の審査員と有料観覧者の
あわせて100名以上が会場にいて、独特のムードの中、
私は4番目に登場しました。
10分間の持ち時間をふるに使い、お酒の価値などを話しました。
どうしてもやりたい一発芸もでき、今回のための衣装も着れて、
自分としては満足の10分間ではありました。
結果は何も起こらなかったです。
つまり入賞などはしませんでした。
静岡から、また東京の日本酒講座受講生も来て貰い、
入賞くらいできれば格好よかったのですが。
お疲れさん会を新橋でやってもらって、帰ってきました。
予選から本選までは4日。
本選は予選と違った話をするのがルール。
4日間でよく本選の話しを組み立てることができたことは、
自分にとっての収穫になりました。
今回のエントリーで10分間スピーチの方法がわかり、
アウェイの場でやった経験もこれからも講師業に役立ちそうです。
エントリー料から衣装代や交通費などを含めますと、
きき酒師受講代金に迫るくらいの金額が必要となりますので、
来年も参加とはいかないでしょうが、今度このような場がありましたら、
笑いなどよりも、骨があって味のある話しができればと思っています。
応援に来てくれた方。
どうもありがとうございました。
2011年07月21日
講師オーディション 本選出場決定!
18日の予選。
落胆気味に帰ってきました。
20日に通知が来ました。
15名が出れる本選に出場が決定しました。
本選は一般の方も御覧いただけるようになります。
私の出番は11時~12時に間になります。
よろしかったら、応援に来てください。
講師オーディション
日時 7月24日(日) 会場 9時30分 開始 10時 終了 17時
会場 北とぴあ ペガサスホール 北区王子1-11-1
観覧料 1,000円
詳細とお申し込みはツタヤビジネスカレッジからどうぞ。
落胆気味に帰ってきました。
20日に通知が来ました。
15名が出れる本選に出場が決定しました。
本選は一般の方も御覧いただけるようになります。
私の出番は11時~12時に間になります。
よろしかったら、応援に来てください。
講師オーディション
日時 7月24日(日) 会場 9時30分 開始 10時 終了 17時
会場 北とぴあ ペガサスホール 北区王子1-11-1
観覧料 1,000円
詳細とお申し込みはツタヤビジネスカレッジからどうぞ。
2011年04月04日
静岡酒、この名役者、この名演技 5. 新しい潮流
しずおか地酒研究会の鈴木真弓さんのWEB酒場静岡吟醸伝に寄稿しています。
「静岡酒、この名役者、この名演技」の第5章です。
昭和の終りから平成の初期にかけて、各種の鑑評会で猛威を振るった静岡酵母。
それがどういうことでしょうか、平成の5年くらいから以前のような成績が取れません。
決して酒質が落ちているわけでもないのに。
むしろ酒質は上がっているとさえ思えました。
これぞっと世に出した新しい酵母を使った大吟醸。
それが予想通りの成績になりません。
しかも、静岡県内の業界人には好評なのに。
成績のよい静岡へのひがみなのでしょうか。
そんな何かの力が働いている気すらしました。
では、静岡酒よりも成績優秀なお酒はどんなタイプなのか?
全国新酒鑑評会で金賞受賞したお酒を利けばわかります。
・
・
・
それはこれまでの静岡酵母のお酒よりも香り高いお酒でありました。
確かに明治の終期から開催されてきた全国新酒鑑評会は香りの
高さを求める面もあり、それは磨かれたお米から造る吟醸酒が
出品されるからであります。
熊本酵母が一世風靡し、全国に普及されたのも香りの高さからであります。
静岡酵母もこれまでの酵母の香りの壁を打破したことにより、
優秀な成績をおさめることとなったわけであります。
もっと振り返りますと、昭和の時代、熊本酵母が誕生してからというもの、
ずっとこの酵母を使ったお酒が全国新酒鑑評会で成績がよく天下を取っていました。
そこへより優れたと感じさせる静岡酵母が参入し、”ここに静岡あり”
と言わせるくらいのお酒が誕生したわけです。
多方面から見れば、静岡酵母から造ったお酒を上回る酒質を目指します。
お酒の世界も技術進歩は日進月歩。
静岡酵母からよりも、香りの高いお酒を造れる酵母の開発が進んでいました。
周りを見渡せば、長野にアルプス酵母があり、秋田に花酵母、京都に月桂冠酵母、
石川に金沢酵母などなどと、静岡の成功を見習い、各県や各国税局単位での
酵母開発が行われていました。
中でも全国区に広がったのが、金沢酵母であります。
酵母の生産量が多いことも全国への広がりのひとつ。
金沢酵母で造ったお酒はこれまでにないタイプの香りを放ちました。
赤い果実を感じさせる強烈ともいえるくらいの高さです。
全国新酒鑑評会においても金賞受賞率は他の酵母を圧倒していました。
これが清酒なの? と首をかしげるくらいの強さのものもありました。
静岡県内の蔵元すら金沢酵母で出品するケースも目立ったくらいです。
全国的に大きな目で見れば、時代は熊本酵母から金沢酵母へと移ったのです。
(静岡酵母も熊本系です。)
まさに「新しい潮流」が生まれました。
この「新しい潮流」は静岡に悩みをもたらしました。
しかもその悩みは10年では拭い去れないほどでありました。
ほんと、文字だけでは計り知れないくらいの苦難の時代です。
次回はこの「静岡酒、苦難の時代」を書こうと思います。
「静岡酒、この名役者、この名演技」の第5章です。
昭和の終りから平成の初期にかけて、各種の鑑評会で猛威を振るった静岡酵母。
それがどういうことでしょうか、平成の5年くらいから以前のような成績が取れません。
決して酒質が落ちているわけでもないのに。
むしろ酒質は上がっているとさえ思えました。
これぞっと世に出した新しい酵母を使った大吟醸。
それが予想通りの成績になりません。
しかも、静岡県内の業界人には好評なのに。
成績のよい静岡へのひがみなのでしょうか。
そんな何かの力が働いている気すらしました。
では、静岡酒よりも成績優秀なお酒はどんなタイプなのか?
全国新酒鑑評会で金賞受賞したお酒を利けばわかります。
・
・
・
それはこれまでの静岡酵母のお酒よりも香り高いお酒でありました。
確かに明治の終期から開催されてきた全国新酒鑑評会は香りの
高さを求める面もあり、それは磨かれたお米から造る吟醸酒が
出品されるからであります。
熊本酵母が一世風靡し、全国に普及されたのも香りの高さからであります。
静岡酵母もこれまでの酵母の香りの壁を打破したことにより、
優秀な成績をおさめることとなったわけであります。
もっと振り返りますと、昭和の時代、熊本酵母が誕生してからというもの、
ずっとこの酵母を使ったお酒が全国新酒鑑評会で成績がよく天下を取っていました。
そこへより優れたと感じさせる静岡酵母が参入し、”ここに静岡あり”
と言わせるくらいのお酒が誕生したわけです。
多方面から見れば、静岡酵母から造ったお酒を上回る酒質を目指します。
お酒の世界も技術進歩は日進月歩。
静岡酵母からよりも、香りの高いお酒を造れる酵母の開発が進んでいました。
周りを見渡せば、長野にアルプス酵母があり、秋田に花酵母、京都に月桂冠酵母、
石川に金沢酵母などなどと、静岡の成功を見習い、各県や各国税局単位での
酵母開発が行われていました。
中でも全国区に広がったのが、金沢酵母であります。
酵母の生産量が多いことも全国への広がりのひとつ。
金沢酵母で造ったお酒はこれまでにないタイプの香りを放ちました。
赤い果実を感じさせる強烈ともいえるくらいの高さです。
全国新酒鑑評会においても金賞受賞率は他の酵母を圧倒していました。
これが清酒なの? と首をかしげるくらいの強さのものもありました。
静岡県内の蔵元すら金沢酵母で出品するケースも目立ったくらいです。
全国的に大きな目で見れば、時代は熊本酵母から金沢酵母へと移ったのです。
(静岡酵母も熊本系です。)
まさに「新しい潮流」が生まれました。
この「新しい潮流」は静岡に悩みをもたらしました。
しかもその悩みは10年では拭い去れないほどでありました。
ほんと、文字だけでは計り知れないくらいの苦難の時代です。
次回はこの「静岡酒、苦難の時代」を書こうと思います。
タグ :しずおか地酒研究会
2011年03月27日
静岡酒、この名役者、この名演技4.「次なる一手」
静岡地酒研究会の鈴木真弓さんのWEB酒場静岡吟醸伝に寄稿しています。
「静岡酒、この名役者、この名演技」の第4章です。
時は平成の初期のこと。お茶処静岡にあって、
これほど酒業界が盛り上がったことがあったでしょうか?
バブル景気にも支えられ、大吟醸があちらこちらのお店に置かれていました。
本来は鑑評会など技術を競うために、ほんの少しだけ生産されていたのであります。
大吟醸では商品化できないために、二級酒に混ぜてしまったりしていた。
それがどこにでもあるくらいになったわけです。
地酒ブームは大吟醸が主役であったわけです。
静岡の大吟醸をメインに打ち出す酒販店も多くなりました。
酒業界のみならず、一般消費者にまで浸透しはじめた静岡酒の実力。
東海四県の業界内でも地味な存在であった静岡県が一躍ヒーロー的になり、
他県を翻弄するかのようでありました。
◇
静岡酒をここまで引っ張ってきたのは、わかりやすさからすれば、
それはやはり静岡酵母でありましょう。
静岡酵母も1つだけではなく、いろんなタイプが生み出されていくこととなります。
平成の初期は本醸造クラス向きなNO-2と吟醸に適したHD-1が主流でした。
やはり開発の目的の第一は鑑評会で入賞などといった最先端の要素を持ち合わすこと。
となると、どうしても吟醸酒用酵母となります。
名古屋国税局の鑑評会で首位、文字通りに東海4県でトップになった志太泉。
主(第1章に登場)としてもこれは自身や静岡酒にとっても快挙であり、
業界としても相当な意味合いを持っていたことでしょう。
次にトップになるのはどこの蔵か。
そしてトップで居続けるためには、常に最先端な要素が必要。
最先端な酵母が必要でありましょう。
◇
主は託します。ある酵母をある蔵元らに。
自信作である新酵母。
熱心なあの蔵なら、納得のゆくお酒が出来る。
あの蔵ならトップを取れる。
さて、主の目論見はうまくいくのか?
次の一手は成功するのでありましょうか?
私はオンタイムでそのお酒を味わいました。
ある蔵元らに託した新しい試みの1本を。
私の酒人生にも大きな影響を起こした1本であります。
結果。
首位を取れませんでした。
主もこれには残念がりました。
このお酒がトップを取れないとは信じられない。
何かがおかしいのではないか?
私はトップを取った志太泉も飲んでいますし、このお酒も飲みました。
相当にすごいお酒。
完成度が高いお酒。
蔵元の魂が乗り移ったお酒。
威厳がありオーラがありました。
では、どうしてトップを取れなかったのか?
それは新しい潮流がはじまるからであります。
新しい潮流が主流となる日が来るのです。
◇
さて、静岡酵母を使ったそんなにすごいお酒でどうしてトップを取れなかったのか?
新しい潮流とは何なのか?
・・・
次の章に続くということにしておきましょうか。
「静岡酒、この名役者、この名演技」の第4章です。
時は平成の初期のこと。お茶処静岡にあって、
これほど酒業界が盛り上がったことがあったでしょうか?
バブル景気にも支えられ、大吟醸があちらこちらのお店に置かれていました。
本来は鑑評会など技術を競うために、ほんの少しだけ生産されていたのであります。
大吟醸では商品化できないために、二級酒に混ぜてしまったりしていた。
それがどこにでもあるくらいになったわけです。
地酒ブームは大吟醸が主役であったわけです。
静岡の大吟醸をメインに打ち出す酒販店も多くなりました。
酒業界のみならず、一般消費者にまで浸透しはじめた静岡酒の実力。
東海四県の業界内でも地味な存在であった静岡県が一躍ヒーロー的になり、
他県を翻弄するかのようでありました。
◇
静岡酒をここまで引っ張ってきたのは、わかりやすさからすれば、
それはやはり静岡酵母でありましょう。
静岡酵母も1つだけではなく、いろんなタイプが生み出されていくこととなります。
平成の初期は本醸造クラス向きなNO-2と吟醸に適したHD-1が主流でした。
やはり開発の目的の第一は鑑評会で入賞などといった最先端の要素を持ち合わすこと。
となると、どうしても吟醸酒用酵母となります。
名古屋国税局の鑑評会で首位、文字通りに東海4県でトップになった志太泉。
主(第1章に登場)としてもこれは自身や静岡酒にとっても快挙であり、
業界としても相当な意味合いを持っていたことでしょう。
次にトップになるのはどこの蔵か。
そしてトップで居続けるためには、常に最先端な要素が必要。
最先端な酵母が必要でありましょう。
◇
主は託します。ある酵母をある蔵元らに。
自信作である新酵母。
熱心なあの蔵なら、納得のゆくお酒が出来る。
あの蔵ならトップを取れる。
さて、主の目論見はうまくいくのか?
次の一手は成功するのでありましょうか?
私はオンタイムでそのお酒を味わいました。
ある蔵元らに託した新しい試みの1本を。
私の酒人生にも大きな影響を起こした1本であります。
結果。
首位を取れませんでした。
主もこれには残念がりました。
このお酒がトップを取れないとは信じられない。
何かがおかしいのではないか?
私はトップを取った志太泉も飲んでいますし、このお酒も飲みました。
相当にすごいお酒。
完成度が高いお酒。
蔵元の魂が乗り移ったお酒。
威厳がありオーラがありました。
では、どうしてトップを取れなかったのか?
それは新しい潮流がはじまるからであります。
新しい潮流が主流となる日が来るのです。
◇
さて、静岡酵母を使ったそんなにすごいお酒でどうしてトップを取れなかったのか?
新しい潮流とは何なのか?
・・・
次の章に続くということにしておきましょうか。
タグ :静岡酵母
2011年03月08日
日本酒講座 at 東海大学短期大学部
先日東京の早稲田大学のみなさんに焼酎の講座を開講しました。
9月9日に静岡市葵区にあります東海大学短期大学部にて日本酒講座を開講します。
東海大学短期大学部では2010年から「フードサイエンス 食の扉」という
シリーズの講座を開講しています。
2011年は第二回目のシリーズになります。
今期の内容は次になります。
担当の講師陣は私以外はみな東海大学短期大学部であります。
私などが偉そうに講演してよいのでしょうか。
5月13日 食べ物を介して人に移る悪玉ウイルスや細菌のお話し!
仁科徳啓氏 元東海大学短期大学部教授
6月10日 コピー食品の知られざる世界
本間智寛氏 東海大学短期大学部
7月8日 スポーツと栄養 勝負に勝てる食事
末永美雪氏 東海大学短期大学部
8月19日 食品添加物のお話し
三輪憲永氏 東海大学短期大学部
9月9日 世界に広がる日本酒 これだけは知っておきたい
河原崎吉博氏 丸河屋酒店
時 間 19:00 ~ 20:30
場 所 東海大学短期大学部 5号館4階
静岡市葵区宮前町101
参加資格 高校生以上
参加費 無料
その他 事前のお申し込みは必要なく直接会場にどうぞ
9月9日に静岡市葵区にあります東海大学短期大学部にて日本酒講座を開講します。
東海大学短期大学部では2010年から「フードサイエンス 食の扉」という
シリーズの講座を開講しています。
2011年は第二回目のシリーズになります。
今期の内容は次になります。
担当の講師陣は私以外はみな東海大学短期大学部であります。
私などが偉そうに講演してよいのでしょうか。
5月13日 食べ物を介して人に移る悪玉ウイルスや細菌のお話し!
仁科徳啓氏 元東海大学短期大学部教授
6月10日 コピー食品の知られざる世界
本間智寛氏 東海大学短期大学部
7月8日 スポーツと栄養 勝負に勝てる食事
末永美雪氏 東海大学短期大学部
8月19日 食品添加物のお話し
三輪憲永氏 東海大学短期大学部
9月9日 世界に広がる日本酒 これだけは知っておきたい
河原崎吉博氏 丸河屋酒店
時 間 19:00 ~ 20:30
場 所 東海大学短期大学部 5号館4階
静岡市葵区宮前町101
参加資格 高校生以上
参加費 無料
その他 事前のお申し込みは必要なく直接会場にどうぞ
タグ :日本酒講座
2011年03月07日
焼酎講座 at 早稲田大学
早稲田大学の学生さんらに焼酎講座を開講しました。
もちろん二十歳以上の方が対象であります。
おしゃべりは大学内でいいのですが、
飲酒はできないとのことで一同新宿歌舞伎町へ。

この日がお誕生日の人がいてケーキにキャンドル。

講座は焼酎のみならず、お酒の一般的なこともお話させてもらいました。
世界中で活躍するであろう早稲田の学生。
日本以外での飲酒場面での立ち振舞い方なども伝授。
思えば、私にも彼らのような年頃がありました。
あれから2.2倍以上も生きています。
こんな私ではありますが、生きた分、参考になる話もあったことでしょう。
これから社会に出て行く方々を対象とした講座も開講していきたいと思っています。
大学生や社会人一年生を対象にお話できれなばと願っています。
大学や会社からの要請があれば、出前講座をしたいと思いますので、よろしくお願いします。
もちろん二十歳以上の方が対象であります。
おしゃべりは大学内でいいのですが、
飲酒はできないとのことで一同新宿歌舞伎町へ。
この日がお誕生日の人がいてケーキにキャンドル。
講座は焼酎のみならず、お酒の一般的なこともお話させてもらいました。
世界中で活躍するであろう早稲田の学生。
日本以外での飲酒場面での立ち振舞い方なども伝授。
思えば、私にも彼らのような年頃がありました。
あれから2.2倍以上も生きています。
こんな私ではありますが、生きた分、参考になる話もあったことでしょう。
これから社会に出て行く方々を対象とした講座も開講していきたいと思っています。
大学生や社会人一年生を対象にお話できれなばと願っています。
大学や会社からの要請があれば、出前講座をしたいと思いますので、よろしくお願いします。
タグ :焼酎講座
2011年01月21日
静岡酒、この名役者、この名演技3.
静岡地酒研究会の鈴木真弓さんのWEB酒場静岡吟醸伝に寄稿しています。
「静岡酒、この名役者、この名演技」の第3章です。
第3章「連戦連勝 首都制圧」
昭和の末期から目立ちはじめた静岡吟醸。
平成になると追い風が吹きます。
平成4年には級別制度もなくなり、酒質と価格の勝負の時代が幕開け。
吟醸酒が従来の2級酒の酒税となりました。
これにより従来の特級酒よりも美味しいと評価される吟醸酒があちらこちらに誕生しました。
日本全国、吟醸酒ブームの到来です。
静岡県は静岡酵母の特性を生かして他県をリード。
静岡ならではの香味で酒通の消費者のみならず、地酒専門店(酒販店・飲食店)らを唸らせ始めました。
静岡の蔵元には地元だけにとどまらず、全国を目指した最初のグループ、いわゆる先発隊も青空天井の如く昇り調子。
人気好調の静岡吟醸を狙って、他県の酒販店も静岡詣出を繰り返しました。
取引蔵に多額の現金を持って来ては翌年のお酒をお願いする酒販店。
静岡の酒販店と仲良くなり、お目当ての蔵元との取引を切望する酒販店。
静岡県新酒鑑評会、静岡県地酒祭りなど、お酒と蔵元と出会える機会をうかがう酒販店。
これから伸びる蔵元を求めて蔵元めぐりをする酒販店・・・。
平成に入ってからは、より一層、雑誌やテレビなどのマスコミの力が強くなってきました。
これらは東京を中心に回っています。
情報は東京に一極集中。地方は東京の情報を求めています。
東京で売れれば一気に全国に広がります。
ブーメラン効果のように地元にも広がっていきます。
つまり東京でヒットすれば有名銘柄になり、あわよくば幻のお酒と騒がれる。
当時の幻のお酒とは“越の三梅”でありました。
『越乃寒梅』『雪中梅』『越の初梅』であります。
これらを追い抜く絶好の機会が吟醸酒を中心とした地酒ブームだったのです。
静岡酒の中には生産量も追いつけない蔵元や銘柄も出始めました。
その筆頭を1つ選ぶならば、
・・・ それは磯自慢でありましょう。
今回は磯自慢のお話です。
地酒ブームを商売チャンスにしようと、地酒専門飲食店が大都市を中心にたくさん誕生しました。
東京を中心とした首都圏は情報が氾濫していることもあり、地酒専門飲食店のみならず一般的な居酒屋やパブにも地酒がおかれるようになりました。
飲食店での日本酒価格は仕入れ価格の1.5倍から3倍くらいであります。
現実的に扱いやすいのは旧1級酒価格であった1.8リットル2,000円くらいでした。
もし、2,000円で3,000円くらいの酒質であったならば
・・・ 夢のようなお話です。
それが正夢になりました。
静岡酒で2,000円を切る価格で他を圧倒するような、あたかも吟醸酒のような本醸造があったのです。
使用米からでしょうか、厳密な意味では吟醸香味ではありませんが、香り高く心地よい味わい。
一口飲み、誰もが素晴らしいお酒と口ずさみたくなる印象。
洗米から火入れまで徹底した品質本位。蔵元の酒造りに賭ける情熱・醸魂が形になった1本
・・・それが磯自慢の本醸造であります。
3,000円以上の価値にも思えるのが2,000円くらいなのですから、味見した飲食店はメニューのラインナップに加えたくなるのも当然です。
こんなお酒をただただ黙って放っておく酒販店はいません。
東京都内の地酒専門酒販店が磯自慢の本醸造を武器に営業を展開し、将棋倒しのように、磯自慢の本醸造はあっと言う間に首都圏の飲食店に広がりました。
まさに首都制圧であります。
その後は静岡県内でも東京と同様のことが起こりました。
どこでも磯自慢は目にするようになりました。
そして、静岡県内の各社から、他県の吟醸酒よりも評価の高い本醸造が続々誕生したのです。
ではまた、次回第4章をお楽しみに!
「静岡酒、この名役者、この名演技」の第3章です。
第3章「連戦連勝 首都制圧」
昭和の末期から目立ちはじめた静岡吟醸。
平成になると追い風が吹きます。
平成4年には級別制度もなくなり、酒質と価格の勝負の時代が幕開け。
吟醸酒が従来の2級酒の酒税となりました。
これにより従来の特級酒よりも美味しいと評価される吟醸酒があちらこちらに誕生しました。
日本全国、吟醸酒ブームの到来です。
静岡県は静岡酵母の特性を生かして他県をリード。
静岡ならではの香味で酒通の消費者のみならず、地酒専門店(酒販店・飲食店)らを唸らせ始めました。
静岡の蔵元には地元だけにとどまらず、全国を目指した最初のグループ、いわゆる先発隊も青空天井の如く昇り調子。
人気好調の静岡吟醸を狙って、他県の酒販店も静岡詣出を繰り返しました。
取引蔵に多額の現金を持って来ては翌年のお酒をお願いする酒販店。
静岡の酒販店と仲良くなり、お目当ての蔵元との取引を切望する酒販店。
静岡県新酒鑑評会、静岡県地酒祭りなど、お酒と蔵元と出会える機会をうかがう酒販店。
これから伸びる蔵元を求めて蔵元めぐりをする酒販店・・・。
平成に入ってからは、より一層、雑誌やテレビなどのマスコミの力が強くなってきました。
これらは東京を中心に回っています。
情報は東京に一極集中。地方は東京の情報を求めています。
東京で売れれば一気に全国に広がります。
ブーメラン効果のように地元にも広がっていきます。
つまり東京でヒットすれば有名銘柄になり、あわよくば幻のお酒と騒がれる。
当時の幻のお酒とは“越の三梅”でありました。
『越乃寒梅』『雪中梅』『越の初梅』であります。
これらを追い抜く絶好の機会が吟醸酒を中心とした地酒ブームだったのです。
静岡酒の中には生産量も追いつけない蔵元や銘柄も出始めました。
その筆頭を1つ選ぶならば、
・・・ それは磯自慢でありましょう。
今回は磯自慢のお話です。
地酒ブームを商売チャンスにしようと、地酒専門飲食店が大都市を中心にたくさん誕生しました。
東京を中心とした首都圏は情報が氾濫していることもあり、地酒専門飲食店のみならず一般的な居酒屋やパブにも地酒がおかれるようになりました。
飲食店での日本酒価格は仕入れ価格の1.5倍から3倍くらいであります。
現実的に扱いやすいのは旧1級酒価格であった1.8リットル2,000円くらいでした。
もし、2,000円で3,000円くらいの酒質であったならば
・・・ 夢のようなお話です。
それが正夢になりました。
静岡酒で2,000円を切る価格で他を圧倒するような、あたかも吟醸酒のような本醸造があったのです。
使用米からでしょうか、厳密な意味では吟醸香味ではありませんが、香り高く心地よい味わい。
一口飲み、誰もが素晴らしいお酒と口ずさみたくなる印象。
洗米から火入れまで徹底した品質本位。蔵元の酒造りに賭ける情熱・醸魂が形になった1本
・・・それが磯自慢の本醸造であります。
3,000円以上の価値にも思えるのが2,000円くらいなのですから、味見した飲食店はメニューのラインナップに加えたくなるのも当然です。
こんなお酒をただただ黙って放っておく酒販店はいません。
東京都内の地酒専門酒販店が磯自慢の本醸造を武器に営業を展開し、将棋倒しのように、磯自慢の本醸造はあっと言う間に首都圏の飲食店に広がりました。
まさに首都制圧であります。
その後は静岡県内でも東京と同様のことが起こりました。
どこでも磯自慢は目にするようになりました。
そして、静岡県内の各社から、他県の吟醸酒よりも評価の高い本醸造が続々誕生したのです。
ではまた、次回第4章をお楽しみに!
タグ :磯自慢
2011年01月18日
静岡酒、この名役者、この名演技2.
静岡地酒研究会の鈴木真弓さんのブログ「WEB酒場 静岡吟醸伝」に寄稿しています。
「静岡酒、この名役者、この名演技」の第二章です。
第2章「連戦連勝 その第一歩」
昭和の終わりに満開となった静岡の大吟醸。
全国新酒鑑評会での当時の成績は脅威とまで言われた。
その牽引は静岡酵母であり、これは当時も今(平成23年)でも誰しもが知るところ。
静岡県の入賞酒のコーナーは他県に類を見ない華やかな香りが漂い、これは一体どうやっているのかと、他県の業界関係者が舌を巻くほどであった。
時代はバブルへと向かう右肩成長期。
日本酒業界も吟醸酒ブームに沸いた。
静岡酵母を駆使し、静岡酒を牽引してきた先発隊のひとつが大村屋酒造場。
全国新酒鑑評会の金賞受賞常連蔵である。
全国の地酒専門酒販店や飲食店が放っておくわけがない。
酒問屋である(株)岡永が主宰する日本名門酒会においても、石川の「菊姫」同様、島田の「おんな泣かせ」が大ブレーク。地酒に興味を持ち、酒通になるがための吟醸酒の入門酒として全国屈指の銘柄となったのである。
◇
「おんな泣かせ」は、辛口男酒の「若竹鬼ころし」と比べ、やや甘口の女酒という位置づけもあったが、人気が高く、手に入りにくさから、「男も泣かす おんな泣かせ」、そして売りたくても入手できない酒販店も困らす「酒屋泣かせ」でもあった。
筆者も泣かされた酒販店であり、当時は11月にもなると、お店に入るやいなや「おんな泣かせってお酒ありますか?」とおっしゃるお客様が毎日のように来た。
どこのお店に行っても売り切れで、来年の予約を勧められるそうである。
なければないほど欲しくなるのが人情。
手に入れたい人は血眼になって、ありそうな酒販店を回ったことだろう。
私もそんなに売れるお酒ならば、是非売りたい。どうにか店に並べることができないかと地元の地酒専門問屋にお願いしたが、「毎年、製造本数は決まっていて、売れるからといって簡単には増やせない、そういう酒だから仕方がないですよ。限りなくあれば、我々だって儲かるのにねえ」と言われた。
それでも諦め切れず、どうにかならないかと詰め寄ると、入手本数を販売実績によって振り分けるので、まずはその実績を作ってくださいと言われた。実績とは「おんな泣かせ」の販売本数ではなく、大村屋酒造場の他の製品のことのようだった。
これは蔵元からの約束事ではなく、欲しがる酒販店の多さに困ったその酒問屋が裁断したことだったと記憶している。
やはりすぐに売れる物だけを欲しがるのは虫が良すぎる!
売れる銘柄を持つにはそれなりの取り組みがあり、実績が追いついていかなければならない!
・・・これが飲食店ならば、好きなものを好きなだけ仕入れられるのになあとも嘆いた。
こんな状況であったため、「おんな泣かせ」の販売は半ば諦め、それでもなお飲みたいがために、自分の飲み分は伊勢丹などに予約をしたほどだ。
伊勢丹の予約も早い者勝ちであり、11月上旬の発売前である10月には予約も終了。
予約できる数も一人2本までであった。
私も酒販店ながら、一般消費者同様に予約名簿帳に自分の住所や電話番号、希望容量と本数を記入して入荷の連絡を待ったものだった。
◇
「おんな泣かせ」のラベルに映える、特定名称の最高の格付けとも言える純米大吟醸の文字。
酒としては珍しかった銀色の背景紙に浮かぶ浮世絵。
・・・これらを見るたびに惚れ惚れとしたのは私だけではないだろう。
約1年の熟成による角が取れたまろやかな口当たり、口の中でもほどよく薫る花のような吟醸香、よくこなれた蜜のような甘美の「おんな泣かせ」は、特級酒、一級酒、二級酒を飲んできた酒通の常識を覆させ、地酒の新しい時代を予感させる存在になった。
まさに「おんな泣かせ」は元祖静岡吟醸ブランドとなり、連戦連勝の火付け役、第一歩となったのである。
筆者も東京など静岡県外での地酒営業の際、飲食店主から「おんな泣かせ」の名が出る度に、静岡酒の知名度の向上を肌で感じ、ひそかに自慢していたものであった。
次回の第3章は21日に鈴木真弓さんのWEB酒場静岡吟醸伝からも公開されます。
「静岡酒、この名役者、この名演技」の第二章です。
第2章「連戦連勝 その第一歩」
昭和の終わりに満開となった静岡の大吟醸。
全国新酒鑑評会での当時の成績は脅威とまで言われた。
その牽引は静岡酵母であり、これは当時も今(平成23年)でも誰しもが知るところ。
静岡県の入賞酒のコーナーは他県に類を見ない華やかな香りが漂い、これは一体どうやっているのかと、他県の業界関係者が舌を巻くほどであった。
時代はバブルへと向かう右肩成長期。
日本酒業界も吟醸酒ブームに沸いた。
静岡酵母を駆使し、静岡酒を牽引してきた先発隊のひとつが大村屋酒造場。
全国新酒鑑評会の金賞受賞常連蔵である。
全国の地酒専門酒販店や飲食店が放っておくわけがない。
酒問屋である(株)岡永が主宰する日本名門酒会においても、石川の「菊姫」同様、島田の「おんな泣かせ」が大ブレーク。地酒に興味を持ち、酒通になるがための吟醸酒の入門酒として全国屈指の銘柄となったのである。
◇
「おんな泣かせ」は、辛口男酒の「若竹鬼ころし」と比べ、やや甘口の女酒という位置づけもあったが、人気が高く、手に入りにくさから、「男も泣かす おんな泣かせ」、そして売りたくても入手できない酒販店も困らす「酒屋泣かせ」でもあった。
筆者も泣かされた酒販店であり、当時は11月にもなると、お店に入るやいなや「おんな泣かせってお酒ありますか?」とおっしゃるお客様が毎日のように来た。
どこのお店に行っても売り切れで、来年の予約を勧められるそうである。
なければないほど欲しくなるのが人情。
手に入れたい人は血眼になって、ありそうな酒販店を回ったことだろう。
私もそんなに売れるお酒ならば、是非売りたい。どうにか店に並べることができないかと地元の地酒専門問屋にお願いしたが、「毎年、製造本数は決まっていて、売れるからといって簡単には増やせない、そういう酒だから仕方がないですよ。限りなくあれば、我々だって儲かるのにねえ」と言われた。
それでも諦め切れず、どうにかならないかと詰め寄ると、入手本数を販売実績によって振り分けるので、まずはその実績を作ってくださいと言われた。実績とは「おんな泣かせ」の販売本数ではなく、大村屋酒造場の他の製品のことのようだった。
これは蔵元からの約束事ではなく、欲しがる酒販店の多さに困ったその酒問屋が裁断したことだったと記憶している。
やはりすぐに売れる物だけを欲しがるのは虫が良すぎる!
売れる銘柄を持つにはそれなりの取り組みがあり、実績が追いついていかなければならない!
・・・これが飲食店ならば、好きなものを好きなだけ仕入れられるのになあとも嘆いた。
こんな状況であったため、「おんな泣かせ」の販売は半ば諦め、それでもなお飲みたいがために、自分の飲み分は伊勢丹などに予約をしたほどだ。
伊勢丹の予約も早い者勝ちであり、11月上旬の発売前である10月には予約も終了。
予約できる数も一人2本までであった。
私も酒販店ながら、一般消費者同様に予約名簿帳に自分の住所や電話番号、希望容量と本数を記入して入荷の連絡を待ったものだった。
◇
「おんな泣かせ」のラベルに映える、特定名称の最高の格付けとも言える純米大吟醸の文字。
酒としては珍しかった銀色の背景紙に浮かぶ浮世絵。
・・・これらを見るたびに惚れ惚れとしたのは私だけではないだろう。
約1年の熟成による角が取れたまろやかな口当たり、口の中でもほどよく薫る花のような吟醸香、よくこなれた蜜のような甘美の「おんな泣かせ」は、特級酒、一級酒、二級酒を飲んできた酒通の常識を覆させ、地酒の新しい時代を予感させる存在になった。
まさに「おんな泣かせ」は元祖静岡吟醸ブランドとなり、連戦連勝の火付け役、第一歩となったのである。
筆者も東京など静岡県外での地酒営業の際、飲食店主から「おんな泣かせ」の名が出る度に、静岡酒の知名度の向上を肌で感じ、ひそかに自慢していたものであった。
次回の第3章は21日に鈴木真弓さんのWEB酒場静岡吟醸伝からも公開されます。
タグ :おんな泣かせ
2011年01月17日
静岡酒、この名役者、この名演技1.
静岡地酒研究会の鈴木真弓さんのブログに「WEB酒場 静岡吟醸伝」があります。
静岡吟醸を愛すものたちの静岡吟醸に対するリレーエッセーです。
私も静岡吟醸を愛する一人として静岡酒について書かさせていただいています。
シリーズタイトルもじっくり考えてこれに決めました。
「静岡酒、この名役者、この名演技」
いかがですか?
まずは寄稿した第一作をお読みください。
第1章「静岡吟醸、はじまりの予感」
時代は昭和の終わり頃。
ここは静岡市牧ヶ谷にある静岡県工業技術センターの2階のある小部屋。
私は幾度となく通いつめ、つかみどころない酒の正体を知ろうと躍起になっていた。
酒屋の酒知らずではいられなかったからである。
私を相手にしてくれたのは、素朴で風格のあるこの部屋の主と、もう何日も家に帰って寝ていないような、ぼさぼさ頭の科学者。
お酒の本を貸してもらったり、酒議論を何時間もした。
ある日の昼過ぎにこんなことがあった。
私と、この部屋の主がいつものように酒議論をしている時、ある初老の男性が入ってきた。
喋る口調から静岡人でないことはわかり、これは酒造従事者それも杜氏ではないかと私の気持ちは高ぶった。
ところが入ってきた客の顔を見るなり、部屋の主の顔は硬直し、これまで見たことのない形相になった。 そして、「おい、帰りなさいと」私に退出命令が下された。
私は素直に部屋を出たが、これから何かがはじまるのではないか、人には見られたくない何かが・・・そうだ!よっぽどのことがあるはずだ、と思った私は、廊下で聞き耳を立てて、部屋の隙間をのぞいてみた。
主は言う。「おい、持ってきたか?」「どう、見せてみろ!」と。
初老の男は右手に握っていたあるものをそっと手渡した。
それは麹であった。
やはり男は杜氏であった。
主は手渡された麹をじっくり見て、矢継ぎ早に怒鳴った。
「お前、俺の言うことをちゃんと聞いてやってるのか?」、
「これで満足な大吟醸ができると思っているのか?」、
「これじゃあ、渡せんな!」
・・・息詰まる部屋の空気、私の心臓はもう壊れるくらいの心拍数。
怖くなって、部屋をあとにした。
この後のことはわからない。
しかし、杜氏がもらいにきたのは静岡酵母。
鑑評会に出品するための大吟醸を造るためにほしかったのだろう。
男と男のプライドの対決。その迫力に腰抜けた私だった。
この部屋の壁には日本酒の作り方が絵で紹介されていた。
『開運、土井酒造場寄贈』となっていた。
開運は静岡酵母HD-1の生まれたところであり、開運大吟醸は静岡吟醸の基本となったお手本なのだろう。
後日、私は主にこう切り出した。
「みんなが静岡酵母を使うと、似たり寄ったりになってしまうのではないでしょうか?」。
主はこう答えた。
「酒は酵母だけではない。麹もある」「麹造りが大事なんだよ」と。
更に続けて、
「酒屋だったら、今まで金賞を取ったところ以外の蔵元に力を入れろ、必ず伸びる。俺がそうする」。
主とは河村傳兵衛先生であり、ぼさぼさ頭の科学者はスタッフの大石先生でありました。
静岡吟醸伝は私以外にもたくさんの静岡吟醸を愛する方々が書いています。
是非訪問してみてくださいね。
静岡吟醸を愛すものたちの静岡吟醸に対するリレーエッセーです。
私も静岡吟醸を愛する一人として静岡酒について書かさせていただいています。
シリーズタイトルもじっくり考えてこれに決めました。
「静岡酒、この名役者、この名演技」
いかがですか?
まずは寄稿した第一作をお読みください。
第1章「静岡吟醸、はじまりの予感」
時代は昭和の終わり頃。
ここは静岡市牧ヶ谷にある静岡県工業技術センターの2階のある小部屋。
私は幾度となく通いつめ、つかみどころない酒の正体を知ろうと躍起になっていた。
酒屋の酒知らずではいられなかったからである。
私を相手にしてくれたのは、素朴で風格のあるこの部屋の主と、もう何日も家に帰って寝ていないような、ぼさぼさ頭の科学者。
お酒の本を貸してもらったり、酒議論を何時間もした。
ある日の昼過ぎにこんなことがあった。
私と、この部屋の主がいつものように酒議論をしている時、ある初老の男性が入ってきた。
喋る口調から静岡人でないことはわかり、これは酒造従事者それも杜氏ではないかと私の気持ちは高ぶった。
ところが入ってきた客の顔を見るなり、部屋の主の顔は硬直し、これまで見たことのない形相になった。 そして、「おい、帰りなさいと」私に退出命令が下された。
私は素直に部屋を出たが、これから何かがはじまるのではないか、人には見られたくない何かが・・・そうだ!よっぽどのことがあるはずだ、と思った私は、廊下で聞き耳を立てて、部屋の隙間をのぞいてみた。
主は言う。「おい、持ってきたか?」「どう、見せてみろ!」と。
初老の男は右手に握っていたあるものをそっと手渡した。
それは麹であった。
やはり男は杜氏であった。
主は手渡された麹をじっくり見て、矢継ぎ早に怒鳴った。
「お前、俺の言うことをちゃんと聞いてやってるのか?」、
「これで満足な大吟醸ができると思っているのか?」、
「これじゃあ、渡せんな!」
・・・息詰まる部屋の空気、私の心臓はもう壊れるくらいの心拍数。
怖くなって、部屋をあとにした。
この後のことはわからない。
しかし、杜氏がもらいにきたのは静岡酵母。
鑑評会に出品するための大吟醸を造るためにほしかったのだろう。
男と男のプライドの対決。その迫力に腰抜けた私だった。
この部屋の壁には日本酒の作り方が絵で紹介されていた。
『開運、土井酒造場寄贈』となっていた。
開運は静岡酵母HD-1の生まれたところであり、開運大吟醸は静岡吟醸の基本となったお手本なのだろう。
後日、私は主にこう切り出した。
「みんなが静岡酵母を使うと、似たり寄ったりになってしまうのではないでしょうか?」。
主はこう答えた。
「酒は酵母だけではない。麹もある」「麹造りが大事なんだよ」と。
更に続けて、
「酒屋だったら、今まで金賞を取ったところ以外の蔵元に力を入れろ、必ず伸びる。俺がそうする」。
主とは河村傳兵衛先生であり、ぼさぼさ頭の科学者はスタッフの大石先生でありました。
静岡吟醸伝は私以外にもたくさんの静岡吟醸を愛する方々が書いています。
是非訪問してみてくださいね。
2009年11月10日
日本酒の商品特性@執筆依頼
リビングプラスさんからのご依頼で執筆しています。

今回は日本酒の商品特性について書きました。
日本酒の商品特性・・・平和をもたらす世界一のお酒!
日本酒の商品特性
それは日本酒だけにしか持ち合わせていない良さであります。
そんなこと考えてもみないのが普通でありましょう。
しかし日本の國酒である日本酒は世界に誇れる特性を持っているのです。
1.製造技術の高さが世界一
基本的には米と水と微生物で醸し出される液体であります。
この続きはリビングプラスのページからどうぞ。
今回は日本酒の商品特性について書きました。
日本酒の商品特性・・・平和をもたらす世界一のお酒!
日本酒の商品特性
それは日本酒だけにしか持ち合わせていない良さであります。
そんなこと考えてもみないのが普通でありましょう。
しかし日本の國酒である日本酒は世界に誇れる特性を持っているのです。
1.製造技術の高さが世界一
基本的には米と水と微生物で醸し出される液体であります。
この続きはリビングプラスのページからどうぞ。
2009年10月28日
名杜氏の遺作品@専属テイスターレポート
「全国の専属テイスターがお勧めの地酒を紹介」の第二弾をアップしてあります。
専属テイスターレポートであります。

私のテーマは「とっておきの静岡酒情報」
そのvol.2として「 名杜氏の遺作品を発見!」をアップ。
これがなかなかのアクセスのようであります。
内容は以前このブログに書いたことと重複します。
名杜氏の遺作品とは何か?
いろんなお問い合わせをいただいています。
返答するのに大変なくらいです。
今日はこれから静岡駅ビルにありますSBS学苑パルシェにて日本酒の極め方講座を行います。
焼酎の一日講座も受講希望者が8名となり、開講も決定!
それでは、講座をやってきま~す。
専属テイスターレポートであります。

私のテーマは「とっておきの静岡酒情報」
そのvol.2として「 名杜氏の遺作品を発見!」をアップ。
これがなかなかのアクセスのようであります。
内容は以前このブログに書いたことと重複します。
名杜氏の遺作品とは何か?
いろんなお問い合わせをいただいています。
返答するのに大変なくらいです。
今日はこれから静岡駅ビルにありますSBS学苑パルシェにて日本酒の極め方講座を行います。
焼酎の一日講座も受講希望者が8名となり、開講も決定!
それでは、講座をやってきま~す。
2009年10月22日
専属テイスターレポートを依頼されちゃいました!
きき酒師でお馴染みのNPO法人でありますFBO料飲専門家団体連合会から
専属テイスターに選ばれております。
専属テイスターとは「きき酒師」「焼酎アドバイザー」に受かり、
その後に「酒匠」「日本酒学講師」にも合格し、
さらに専属テイスターになるべくトレーニング(専属テイスター育成会)を受け、
専属テイスター選考会で認定された者であります。
狭き門のように見えましょう。
全国で32人もいるようです。
資格というものは、これからプロになろうとしている人が取るものです。
酒の道に入って2009年で28年目です。
だから私個人的には資格は無意味。
まあ、マスコミ受けはいいと思いますがね。
酒販店を経営している方がはるかに大変でありますよ。
そんなこんなではありますが、専属テイスターレポートを依頼され、
それがオープンになったものですから、ご報告まで。
「全国の専属テイスターがお勧めの地酒を紹介」のコーナーに登場です。
専属テイスターレポートであります。

私はお笑い系ですから、こんな感じで書きますが、
他の方は偉い方も多そうですから参考になるかもしれませんよ。
専属テイスターに選ばれております。
専属テイスターとは「きき酒師」「焼酎アドバイザー」に受かり、
その後に「酒匠」「日本酒学講師」にも合格し、
さらに専属テイスターになるべくトレーニング(専属テイスター育成会)を受け、
専属テイスター選考会で認定された者であります。
狭き門のように見えましょう。
全国で32人もいるようです。
資格というものは、これからプロになろうとしている人が取るものです。
酒の道に入って2009年で28年目です。
だから私個人的には資格は無意味。
まあ、マスコミ受けはいいと思いますがね。
酒販店を経営している方がはるかに大変でありますよ。
そんなこんなではありますが、専属テイスターレポートを依頼され、
それがオープンになったものですから、ご報告まで。
「全国の専属テイスターがお勧めの地酒を紹介」のコーナーに登場です。
専属テイスターレポートであります。

私はお笑い系ですから、こんな感じで書きますが、
他の方は偉い方も多そうですから参考になるかもしれませんよ。
2009年10月03日
13年前の今日の自分
13年前の写真が出てきましたので。
三井生命にて手作りビールのセミナーを開きました。

会場は今はなくなっていますが、伝馬町にあった三井生命ビルであります。
生徒さんは三井生命の従業員さんたち。
保健のセールスレディーさんたちでありました。
ビールが出来るまでには時間がかかります。
ビールの出来具合をSBSラジオで生放送されました。

4時間番組でしたから、長かったです。
佐藤理絵アナウンサーが最後の担当の日でありました。
ビールを焦がして、挽いて、お湯で糖化して、
それを冷やして、ろ過紙、酵母を入れるまでがこの日の作業。
後日、瓶詰めしてから、みなさんにお持ちしました。
この日に作ったビールはアルコール1度未満であります。
酒税法上はビールではありませんから、誰にでも作れます。
13年前のこの日は33歳でありました。
三井生命にて手作りビールのセミナーを開きました。

会場は今はなくなっていますが、伝馬町にあった三井生命ビルであります。
生徒さんは三井生命の従業員さんたち。
保健のセールスレディーさんたちでありました。
ビールが出来るまでには時間がかかります。
ビールの出来具合をSBSラジオで生放送されました。

4時間番組でしたから、長かったです。
佐藤理絵アナウンサーが最後の担当の日でありました。
ビールを焦がして、挽いて、お湯で糖化して、
それを冷やして、ろ過紙、酵母を入れるまでがこの日の作業。
後日、瓶詰めしてから、みなさんにお持ちしました。
この日に作ったビールはアルコール1度未満であります。
酒税法上はビールではありませんから、誰にでも作れます。
13年前のこの日は33歳でありました。
2009年09月15日
宇宙一きれいな液体
リビングプラスさんからのご依頼で執筆しています。

今回はお酒の商品特性について書きました。
お酒の商品特性と書きますと、かた苦しいと思われますが、
お酒は法律においても自分では作れないものであり、
商品としてのお酒と接するわけですからご理解ください。
人類が各地でお酒を作ることに成功してきました。
お酒が消滅したわけではありませんから、
存在する大きな理由があると思って間違いありません。
お酒は地域によって様々種類があります。
ブドウが採れるところにはワインがあり、
麦が採れるところにはビールがあります。
このようにいろんな酒類がありますが、
それらに共通していることがあるわけです。
まず、精なるものが含まれています。
えっ? 精?
この続きはこちらからどうぞ。
今回はお酒の商品特性について書きました。
お酒の商品特性と書きますと、かた苦しいと思われますが、
お酒は法律においても自分では作れないものであり、
商品としてのお酒と接するわけですからご理解ください。
人類が各地でお酒を作ることに成功してきました。
お酒が消滅したわけではありませんから、
存在する大きな理由があると思って間違いありません。
お酒は地域によって様々種類があります。
ブドウが採れるところにはワインがあり、
麦が採れるところにはビールがあります。
このようにいろんな酒類がありますが、
それらに共通していることがあるわけです。
まず、精なるものが含まれています。
えっ? 精?
この続きはこちらからどうぞ。
2009年08月26日
お酒の種類、いくつあるの?
リビングプラスさんからのご依頼で執筆しています。

これまで、お酒の誕生として、日本酒・ワイン・ビールと書いてきました。
今回は、お酒はいったいいくつあるのか。
それについて書きました。
あなたのお好きなお酒は何ですか?ビールですか?それともワイン?
「飲食店ではとりあえずビールだよ。」
「ビールを飲みたいんだけど、発泡酒にしている。」
「だいたいお風呂上りに缶チューハイを1つかな。」
などなどの声が聞こえてきそうです。
それにしても星の数ほどあるお酒。
いったいいくつあるのでしょう?
もちろん商品名ならば、数え切れないくらいでしょう。
しかし、何種類?となれば、その答えは決まっています。
それはお酒の造り方に由来するからです。
お酒にはアルコールが入っています。
このアルコールをどうやって得ているのか?
その方法が限られています。
まずは作り方から見ていきます。
それでは本題に入ります。
これまで、お酒の誕生として、日本酒・ワイン・ビールと書いてきました。
今回は、お酒はいったいいくつあるのか。
それについて書きました。
あなたのお好きなお酒は何ですか?ビールですか?それともワイン?
「飲食店ではとりあえずビールだよ。」
「ビールを飲みたいんだけど、発泡酒にしている。」
「だいたいお風呂上りに缶チューハイを1つかな。」
などなどの声が聞こえてきそうです。
それにしても星の数ほどあるお酒。
いったいいくつあるのでしょう?
もちろん商品名ならば、数え切れないくらいでしょう。
しかし、何種類?となれば、その答えは決まっています。
それはお酒の造り方に由来するからです。
お酒にはアルコールが入っています。
このアルコールをどうやって得ているのか?
その方法が限られています。
まずは作り方から見ていきます。
それでは本題に入ります。
2009年07月18日
ビールの誕生
リビングプラスさんからのご依頼で執筆しています。

日本酒の誕生、ワインの誕生ときました。
今回はビールの誕生話であります。
ビール系飲料は日本で最も飲まれている酒類です。
その誕生は6,000年前にもさかのぼります。
ビールが生まれた背景。
その誕生ストーリーを私のオリジナルで書き上げました。
ビール誕生、そのはじまりはパンであります。
ビールの誕生をお読みください。
日本酒の誕生、ワインの誕生ときました。
今回はビールの誕生話であります。
ビール系飲料は日本で最も飲まれている酒類です。
その誕生は6,000年前にもさかのぼります。
ビールが生まれた背景。
その誕生ストーリーを私のオリジナルで書き上げました。
ビール誕生、そのはじまりはパンであります。
ビールの誕生をお読みください。
2009年06月14日
ワインの誕生
リビングプラスさんからの依頼で執筆しています。
6月は「ワインの誕生」について書きました。

ワインは人間が作り始めたのでしょうか?
それならいつ、どうやって?
もしかしたら、サルに学んだのかもしれませんよ。
山の中を歩いていたら、落ちた果実から出来たワインをサルたちが飲んでいた。
猿酒であります。
猿酒を昔話にしました。
「ワインの誕生、サルが先か、人間が先か?」
ワインと人間との遭遇。
どんな感じであったでしょう。
神からの贈り物。
お酒はありがたい贈り物ですね。
6月は「ワインの誕生」について書きました。
ワインは人間が作り始めたのでしょうか?
それならいつ、どうやって?
もしかしたら、サルに学んだのかもしれませんよ。
山の中を歩いていたら、落ちた果実から出来たワインをサルたちが飲んでいた。
猿酒であります。
猿酒を昔話にしました。
「ワインの誕生、サルが先か、人間が先か?」
ワインと人間との遭遇。
どんな感じであったでしょう。
神からの贈り物。
お酒はありがたい贈り物ですね。
2009年06月02日
私をあなたのお家に呼んで!
これまでお酒の講座を展開してきました。
静岡駅ビルパルシェ内にあるSBS学苑パルシェ校。
企業様・飲食店様への出前講座。
ご希望の方々には日本酒ナビゲーター(旧日本酒アドバイザー)になってもらったり。
静岡駅のSBS学苑パルシェ校まで来れない方には通信講座も行ってきました。
丸河屋酒店ということで、現物の酒を販売する他に、
知識や楽しんでもらうことも提供してきました。
今後はその延長もすすめてみます。
企業様・飲食店様以外のご家庭にも講座を出前します。
お友達など4人くらい集まる機会ってありますよね。
例えば、お誕生日会やパーティー、何かの打ち上げなどなど。
そんな時に私を呼んでください。
ちょっとしたお酒の話をしたいです。
静岡市内でしたら、私への交通費もかかりませんからお安くすみます。

こんな感じで楽しくお酒でも召し上がれ!
ごいっしょさせてくださいね。
静岡駅ビルパルシェ内にあるSBS学苑パルシェ校。
企業様・飲食店様への出前講座。
ご希望の方々には日本酒ナビゲーター(旧日本酒アドバイザー)になってもらったり。
静岡駅のSBS学苑パルシェ校まで来れない方には通信講座も行ってきました。
丸河屋酒店ということで、現物の酒を販売する他に、
知識や楽しんでもらうことも提供してきました。
今後はその延長もすすめてみます。
企業様・飲食店様以外のご家庭にも講座を出前します。
お友達など4人くらい集まる機会ってありますよね。
例えば、お誕生日会やパーティー、何かの打ち上げなどなど。
そんな時に私を呼んでください。
ちょっとしたお酒の話をしたいです。
静岡市内でしたら、私への交通費もかかりませんからお安くすみます。

こんな感じで楽しくお酒でも召し上がれ!
ごいっしょさせてくださいね。