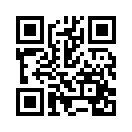2008年11月19日
ボージョレーヌーボーが待ちきれなくて
20日解禁のボージョレーヌーボー。
20日の深夜0時に解禁。
今日の深夜は日本対カタール戦がある。
それにあわせてボージョレーを何てこともいいのだが。
それまで待てな~い。
そこで個人的に大好きな1本。
今日はもちろん赤ワインである。
日本が誇る勝沼の丸藤葡萄酒工業。
銘柄は「ルバイヤート」。
これとハムで飲るとする。
ルバイヤートの赤はプライベートの定番酒。
ルバイヤートの中では一番格下であろうが、これは正直に旨い。
何より自分にあうのである。
自分がこのワインに合ってきたのである。
数種類の品種、しかも国産と海外産のブレンドであるが、これが気分にあうのである。
俺を紛らわしてくれる。
ストレートなシングル果汁から造られてしまうと、こちらも職業上、考えさせられてしまう。
でもこいつはいつでも気軽に付き合えるんだ。
丸河屋のワインセラーには常時入っている。
数店の業務店と自分と妻の御贔屓です。
カタール戦のスタートまで待てるかな。
20日の深夜0時に解禁。
今日の深夜は日本対カタール戦がある。
それにあわせてボージョレーを何てこともいいのだが。
それまで待てな~い。
そこで個人的に大好きな1本。
今日はもちろん赤ワインである。
日本が誇る勝沼の丸藤葡萄酒工業。
銘柄は「ルバイヤート」。
これとハムで飲るとする。
ルバイヤートの赤はプライベートの定番酒。
ルバイヤートの中では一番格下であろうが、これは正直に旨い。
何より自分にあうのである。
自分がこのワインに合ってきたのである。
数種類の品種、しかも国産と海外産のブレンドであるが、これが気分にあうのである。
俺を紛らわしてくれる。
ストレートなシングル果汁から造られてしまうと、こちらも職業上、考えさせられてしまう。
でもこいつはいつでも気軽に付き合えるんだ。
丸河屋のワインセラーには常時入っている。
数店の業務店と自分と妻の御贔屓です。
カタール戦のスタートまで待てるかな。
2008年11月19日
日本酒の楽しみ方講座 SBS学苑
今回のテーマは「お酒のラベル表示」。特定名称、生、原酒などを理解することにありました。
その前に「保存管理の重要性」から説明
前回に保存管理の悪い条件下におかれたお酒はどのような味になるのか?という御質問をいただいておりました。私のパソコンのディスプレイの影に隠れて置かれ続けていた1本のサンプル酒がありましたので、これが適した教材かと思いお持ちしました。(下写真の一番左)10年くらい放置されていました、かわいそうなお酒でありました。しかし日の目を見ることができました。
長期間に渡って熟成させる長期熟成酒が製品としてありますが、これは光に当てず、目的とする温度で熟成させるものです。私がお持ちしたのは、長期放置酒でありますから、市販の長期熟成酒とは違っています。長期熟成酒の香りを熟成香とすれば、長期放置酒の香りは日光臭が主体であり、それに老ね香~熟成香がしているものもであります。
光にあたったために生ずる匂いを 日光臭と呼びますので、室内の蛍光灯の光を浴びてしまったお酒の匂いも日光臭となります。売り場に置かれたお酒が長期間売れないと日光臭がつきます。しかしこの欠点を隠すがごとく、業界では今でも瓶香(びんか)と呼んでいます。実際のところ、日光臭を知らない業界の方も多く、困った点でもあります。日光臭がついたお酒の香りは、みなさんが嗅いだように、異臭的であります。
・カビ臭い・・・タンス、土壁、キノコ
・オシッコ臭い・・・狸、稲の開花臭
このように書きますと、相当良くないものと思われますが、もしかしたら使い道があるかもしれません。癖者は生かせばこれ以上のない優れ者となる可能性がありますね。
「特定名称とは?」
お酒のラベルに書いてある、本醸造とか吟醸という文字が特定名称であります。その特定名称の書かれている意味は? 醸造アルコールの添加の有無と精米歩合の違いが大きな柱ということを学びました。
つまり製造上において2タイプあることになります。1つは醸造アルコールを入れているもの、もう1つは入れていないものです。前者が本醸系であり、後者が純米系であります。

今回お持ちした6本を3本づつ、本醸系と純米系に分けて、飲み比べてもらいました。
私の方で一方的にしゃべってしまいましたが、次のことが言えます。

6本のお酒の中には、フルーティーな香りのするものもあったかと思います。本醸系と純米系にとらわれることなく、華やかな香りがするものがあり、この香りを吟醸香と呼びます。吟醸酒は吟醸香がしても当たり前ですが、本醸造でも純米でも吟醸香のするものもあります。
こうなりますと、本醸系と純米系にリンクする吟醸系があることになります。本醸造や純米酒にもあって、本来は吟醸とか純米吟醸とかの表示がされてもおかしくないものですね。
どのような特定名称を付けるかは、蔵元の判断にもよります。大吟醸を本醸造と表示しても問題はありません。逆に、精米歩合から本醸造とすべきものを大吟醸とは書けないのであります。下れるが、上れないわけです。
本醸造と純米酒の違いはわかりにくいです。
もろみを搾る前に醸造アルコールを添加するのが本醸系なのですが、この時にたった1滴のアルコールを加えたとしても、純米の表示はできなくなります。そのような少量を入れただけの本醸造は実際には見当たりません。造り手も本醸造と名乗るからには、本醸造らしいものを造りたいことでしょう。
となると、どこで違いを見分けるか?
一番特徴が出るのがスッキリ度です。アルコール添加しますと軽快になり、スッキリした辛口になります。余韻にドライ感があります。
アルコール添加しない純米酒はコクがあり、濃いです。それはアルコール添加されたお酒よりも旨味と甘味が多いからです。余韻は少々ざらついた甘味が舌の上に残ります。
世間では醸造アルコールを添加物として悪者扱いする傾向がありますが、お酒のタイプとして考えた方が前向きで幸せがやって来そうです。
これは私の意見ですが、味覚は濃いものに慣れますと、薄いものに対して鈍くなります。ですから、純米ばかりを飲んでいますと、本醸系に対してわかりにくくなってしまうような気がします。本醸系を飲んでいれば、純米の濃さがよりわかると思うのですが、いかがでしょうか。
あなたは薄味派、それとも濃い味派?

今回のおつまみはお刺身にしました。伊万里のお皿がにぎやかです。お醤油といっしょに柿酢を御用意しました。お酢にくぐらせてから、お醤油をつける食べ方もあります。お酢は締めますから、触感として硬くなります。これは酸類(H)のせいです。レモンも試してみるのも面白いですよ。

私から見た生徒さん達です。みなさん良い方ばかりで仲良く楽しいです。二十歳上の方でしたら、どなたでも御受講できますよ。
お問い合わせ、お申し込みは、SBS学苑パルシェまで、054-253-1221 です。
その前に「保存管理の重要性」から説明
前回に保存管理の悪い条件下におかれたお酒はどのような味になるのか?という御質問をいただいておりました。私のパソコンのディスプレイの影に隠れて置かれ続けていた1本のサンプル酒がありましたので、これが適した教材かと思いお持ちしました。(下写真の一番左)10年くらい放置されていました、かわいそうなお酒でありました。しかし日の目を見ることができました。
長期間に渡って熟成させる長期熟成酒が製品としてありますが、これは光に当てず、目的とする温度で熟成させるものです。私がお持ちしたのは、長期放置酒でありますから、市販の長期熟成酒とは違っています。長期熟成酒の香りを熟成香とすれば、長期放置酒の香りは日光臭が主体であり、それに老ね香~熟成香がしているものもであります。
光にあたったために生ずる匂いを 日光臭と呼びますので、室内の蛍光灯の光を浴びてしまったお酒の匂いも日光臭となります。売り場に置かれたお酒が長期間売れないと日光臭がつきます。しかしこの欠点を隠すがごとく、業界では今でも瓶香(びんか)と呼んでいます。実際のところ、日光臭を知らない業界の方も多く、困った点でもあります。日光臭がついたお酒の香りは、みなさんが嗅いだように、異臭的であります。
・カビ臭い・・・タンス、土壁、キノコ
・オシッコ臭い・・・狸、稲の開花臭
このように書きますと、相当良くないものと思われますが、もしかしたら使い道があるかもしれません。癖者は生かせばこれ以上のない優れ者となる可能性がありますね。
「特定名称とは?」
お酒のラベルに書いてある、本醸造とか吟醸という文字が特定名称であります。その特定名称の書かれている意味は? 醸造アルコールの添加の有無と精米歩合の違いが大きな柱ということを学びました。
つまり製造上において2タイプあることになります。1つは醸造アルコールを入れているもの、もう1つは入れていないものです。前者が本醸系であり、後者が純米系であります。
今回お持ちした6本を3本づつ、本醸系と純米系に分けて、飲み比べてもらいました。
私の方で一方的にしゃべってしまいましたが、次のことが言えます。
6本のお酒の中には、フルーティーな香りのするものもあったかと思います。本醸系と純米系にとらわれることなく、華やかな香りがするものがあり、この香りを吟醸香と呼びます。吟醸酒は吟醸香がしても当たり前ですが、本醸造でも純米でも吟醸香のするものもあります。
こうなりますと、本醸系と純米系にリンクする吟醸系があることになります。本醸造や純米酒にもあって、本来は吟醸とか純米吟醸とかの表示がされてもおかしくないものですね。
どのような特定名称を付けるかは、蔵元の判断にもよります。大吟醸を本醸造と表示しても問題はありません。逆に、精米歩合から本醸造とすべきものを大吟醸とは書けないのであります。下れるが、上れないわけです。
本醸造と純米酒の違いはわかりにくいです。
もろみを搾る前に醸造アルコールを添加するのが本醸系なのですが、この時にたった1滴のアルコールを加えたとしても、純米の表示はできなくなります。そのような少量を入れただけの本醸造は実際には見当たりません。造り手も本醸造と名乗るからには、本醸造らしいものを造りたいことでしょう。
となると、どこで違いを見分けるか?
一番特徴が出るのがスッキリ度です。アルコール添加しますと軽快になり、スッキリした辛口になります。余韻にドライ感があります。
アルコール添加しない純米酒はコクがあり、濃いです。それはアルコール添加されたお酒よりも旨味と甘味が多いからです。余韻は少々ざらついた甘味が舌の上に残ります。
世間では醸造アルコールを添加物として悪者扱いする傾向がありますが、お酒のタイプとして考えた方が前向きで幸せがやって来そうです。
これは私の意見ですが、味覚は濃いものに慣れますと、薄いものに対して鈍くなります。ですから、純米ばかりを飲んでいますと、本醸系に対してわかりにくくなってしまうような気がします。本醸系を飲んでいれば、純米の濃さがよりわかると思うのですが、いかがでしょうか。
あなたは薄味派、それとも濃い味派?
今回のおつまみはお刺身にしました。伊万里のお皿がにぎやかです。お醤油といっしょに柿酢を御用意しました。お酢にくぐらせてから、お醤油をつける食べ方もあります。お酢は締めますから、触感として硬くなります。これは酸類(H)のせいです。レモンも試してみるのも面白いですよ。
私から見た生徒さん達です。みなさん良い方ばかりで仲良く楽しいです。二十歳上の方でしたら、どなたでも御受講できますよ。
お問い合わせ、お申し込みは、SBS学苑パルシェまで、054-253-1221 です。